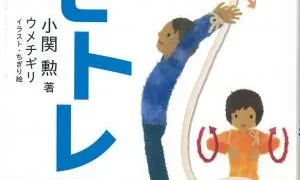子どもに願うこと

子どもが生まれてきたら、いろいろと願いごとができます。
まずは「この子が元気に育ちますように」というような思いがすごく強くでてきます。なんなら「元気で生きていてくれたら、他はなにも要らない」くらいに思ったりします。
そこから数年、子育てをしていると、だんだん、子どもについての要望が増えていきます。「利発な子どもに育つように」「運動が得意な子に育つように」「かしこい子に育つように」「ひとさまの役に立つ子に育つように」…などなど。ひとの願望というのは、膨らみ始めると本当に歯止めがありません。
生まれてきてすぐには、本当に「この子が元気で生きていてくれさえすれば」と真面目にそう祈っていた筈なのに。
そんなことを、時々、思い出します。
「ひとさまのお役に立つように」なんていう願望は、わりと、子どもにも言い聞かせる形で口にしているかもしれません。
「あなたも、ひとさまのお役に立てるようなひとになるのだよ」なんて言い聞かせがあっても、不思議ではないでしょう。
こういう願望は「こうであったら良いな」という、いわば、希望です。余禄です。ついでのお願いです。
ですが、診療をしていると、しばしば「ひとの役に立てなければ、じぶんは存在することを許されない」というような緊張をお持ちの方がいらっしゃいます。
「みんなを笑顔にしてあげられる子に育ってほしい」という願望を受け止めた子どもが「ひとが不機嫌になっているのは、私がちゃんとしていないから」などと、勘違いをすることだってあります。その結果、ひとの顏色を伺い、不機嫌なひとが近くにいるだけで動揺し、心を消耗し、くたびれ果てる、などという結果になる場面だって、あるかも知れません。
子どもが生まれてきた時、あるいは、子育てをしている時、小さい子を育てる親の年齢を考えてみると、まあ、ハタチそこそこだったりするわけです。もちろん、最近は高齢出産も増えましたから、40歳前後での子育て、なんていうのもありますが、それでも、今の世の中からすると、圧倒的に「小僧・小娘」の年齢なわけです。
そりゃ、子どもに伝えるメッセージだって、その小僧・小娘の発しているものですから、稚拙だったりするのでしょう。
とはいえ、子どもからすると、親というのは、とても大きな存在です。圧倒的な存在感があります。それに伴って、圧倒的な正しさを持っているものだ、と勘違いしがちです。
そのような、わりとじぶんに厳しい形の価値観を引き受けてしまっている方は、「あれは未熟な時代の親が、勘違いさせたのだ」と解釈しなおして、こうした価値観から、離れていただきたいものです。
そして、子育てをしている親御さんには、子育ての上でのお願いがあります。親が願うこと、祈ることは、それはそれで大事なことではありますが、子どもというのは、あくまでも、親とは別に存在する、一個の個人です。自分自身の願いを押しつけることなく、子ども自身の存在を尊重して頂きますよう、くれぐれもお願いいたします。