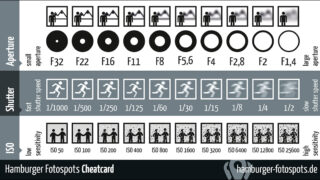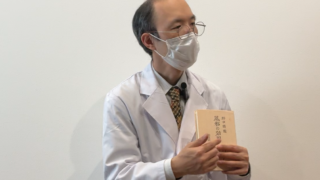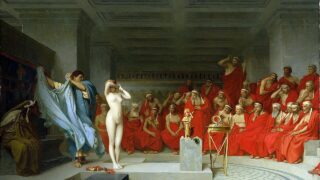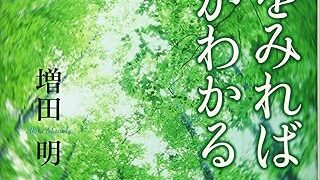ボディートーク、指導者講習の思い出

ボディートークの増田明氏が、指導者の育成をしていたのは、平成の初め頃のことだったと記憶しています。当時、わたしは学生で、他に用事もあまり無かったのか、ずいぶんとどっぷり、その世界に関わっていました。
今から考えると、師匠はちょうど、今のわたし位の年齢でした。30年前の、30歳くらい年上の師匠です。
なるほど、今わたしが学生さんたちを見ているのと、同じ雰囲気で見ておられたんでしょうかねえ…。
グループレッスンの参加者がどんどん増え始めて、いろいろな方が集まるようになって居たのを覚えています。指導者向けのグループレッスンは、メンバーが厳選されますので、話の内容も、経験も、わりと雑味が減り、学びたいことに気持ちが集注しやすかったのを覚えています。
なんだかんだ、とお勉強は得意でしたので、師匠にも評価してもらって、指導者の認定を頂きました。
当時は「これで、にしむらくんに必要なのは人生経験だな」と言われたのでした。ハタチそこそこの若者に、ひとの心と身体の話を聞かされても、なかなか、素直に頷けないですよねえ。
ひとの身体の緊張には、物理的なものとして、「腕を酷使した」とか「姿勢が悪かった」というような筋肉の疲れと、それから、心理的な緊張による、筋肉の緊張…こころのシコリ…がそれぞれ出てくる、というのがボディートークによる身体と心の理解の入口でした。
身体に出てくる心の問題、というのは、さまざまあります。
師匠はもともと、高校生の「失恋」が入口にあったようですが。
勉強をしていて、分析的な思考でひとの背中をみていると、「さぐるような」手つきになりがち、だったようです。
指導者の勉強を終えて、しばらくしていた頃。一緒に勉強していた仲間から「にしむらくんの手が、以前よりも柔らかくなった」とフィードバックをくれることがありました。
「以前は、さぐるような手つきが強くて、それがつらかったが、最近、そういう手つきが減った」というものでした。
なるほど?と考えたのですが、だいぶボンヤリした手つきになっていたようです。それはそれで、相手のニーズに見あったものだったのでしょう。
今でも、胸椎の何番には、どんな緊張が出てくる…ということを、思いだしては口にすることがありますし、指導者の認定試験や更新の際には、背骨の位置をきちんと把握できているかどうか、という実技試験がありましたので、間違いないように背骨の突起を数える、ということをやっていたりして、細かく数える技術は覚えた…はずなのですが、最近は本当にボンヤリとした印象を大事にしています。
細かく分析する、ということだけが、理解じゃないんだ、という解釈は、年齢が重なるごとに深まってきたように思います。
ひょっとすると、これが「足りなかった人生経験」というものの結晶なのかもしれません。
わたしがひとに触れる、ということを習い覚えたのは一人目の師匠に出会ったことがきっかけでしたが、二人目の師匠である、増田氏が、茫漠とした身体に、たくさんの区切りや意味を与えてくれた、ということが、とても大きいのだろうと思っています。
クリニックで、医師として仕事をしていますが、この時の積み重ねが、とても大きな基礎になっている…と折に触れて想い出すわけです。