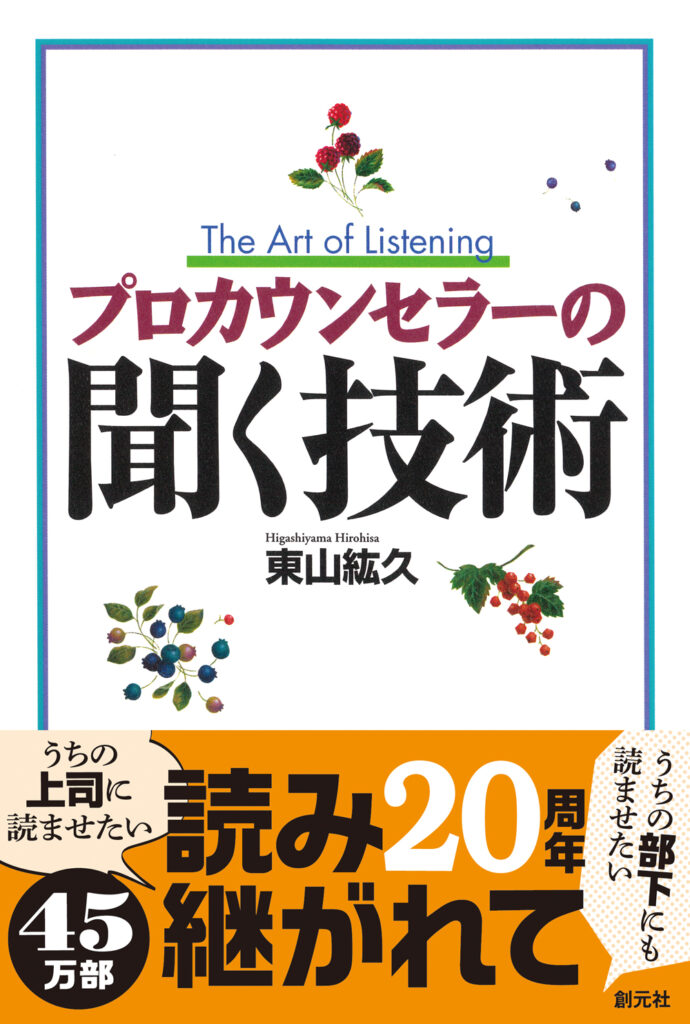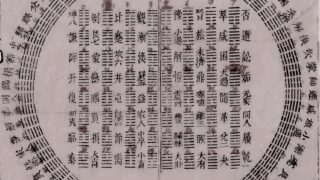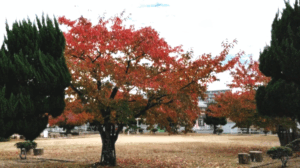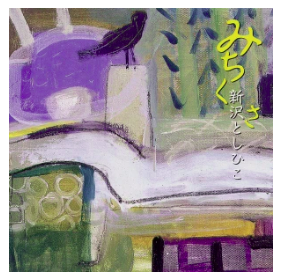うらみごとを手放す

わたしの母は女ばかり四人姉妹の末っ子でした。たいへん可愛がられて育った…というよりは、どちらかというと、「みそっかす」扱いをされていたのだ、と、しばしば、そんな思い出話を、繰り返して子供に聞かせていたのでした。
お客さんがあると、「お嬢さまがたに」ということで、お土産をくださる方があるのだけれど、だいたい「おうちのお嬢さまがた」というところの想定が「3人」になっているのでした。
で、「長女、次女、三女」とそれを分配するのだけれど、「四女」の母にまでは割り当てが来ないのです。
分配の主である、祖母が「あなたには、この次ね」と言うのだけれど、じゃあ、じっさいにその「次の時」にどうなるかというと、前の約束など忘れたかのように、また「長女…」とはじまり、母には割り当てが無いのだ…。と。
「割を食った」と感じている、片方の当事者からしか聞き取りが出来ていませんので、実際のところ、どうだったのか、はわかりません。関与していた祖母も伯母も、鬼籍に入ったり、あるいは記憶があやしくなってきたり、と、今さらそれを確認するすべもありませんし。
わたしが若い頃は、「苦労してきたんだなあ」と思いました。
が、今から考えると、かなり被害者的な意識が強かったのかもしれません。
そんな祖父母の金婚式のお祝いを、むかし、温泉旅館でやったことがありました。もう30年以上前の夏休みのことでした。
祖父母と、伯父伯母、そして従兄弟が勢揃いした…のですが。
わたしはちょうど、学校の合宿行事が重なっていて、ひとり、不参加でした。
母のうらみごとに似た形で、わたしもずいぶんと長いこと「あの時、参加できなくて…」ということを繰り返し口にしていたのですが、さすがに見かねたのでしょう。
弟が、「あなた、ずーっと、その不満を言い続けているよねえ!?」と指摘してくれました。
本当にハッとしたのでした。
怒りをはらう、ということは続けて来ていたはずですが、うらみごとを言い続けることは、「それとは別」と思っていたのでしょうか。
参加できなかった…を言い続けたら、参加できたりしたのでしょうか。そんなはずはありません。じゃあ、学校行事を欠席したら良かったのでしょうか?それもちょっと悩ましい話です。当時そのような選択肢が呈示されたわけでもありませんでしたが。
指摘されて気づいたのですが「うらみごと」のモードというのが、わたしの中に、たしかにできあがっていたのでした。
ここをひとのせいにするのも格好悪いのですが、母の「うらみごと」をそのまま聞いて、似たような愚痴をこぼすモード、というのができあがっていたのかもしれません。
母は、立派な教育を施してくれていた…とずいぶん長いこと思っていたのですが、意外と「そうじゃない」こともあったようです。
自分自身にかかわる話ですから、「立派な教育を受けた」と思いたかったのですが。
学生時代に、親の影響から少しずつ抜け出した、という話は、以前書いたことがありました。
多少抜け出した…と思っていたのだけれど、まだまだ影響というのは残っていたのだなあ、と思ったのでした。
うらみごと、というのは、どうしても「被害者モード」になりがちです。
この「被害者モード」というのが、なかなか曲者で、とっても便利なのですが、周辺へのダメージが大きくなります。
ところで。
もうひとつ、難易度が高いなあ…と思うのは「自分が、自分で思うようにいかない」という状況で「自分自身が、自分自身の被害者になる」という状況に入られる方があります。
「身体の不調で、自分が思ったように動けない」とか「心がくたびれていなければもっと羽ばたけるのに」とか。
「ひとのせいにしないのですよ」と時々言うのですが、こういう言い方をされる方は、「ええ。ひとのせいにはしていません。じぶんのせいです」とおっしゃったりします。
なのに、「じぶんのせい」で「わたしは困っている」という「うらみごと」をおっしゃる。
うらみごとを手放す、というのは、けっこう大変な作業です。怒りをはらう、というのより、難易度は高いのだろうと思います。本質的には、うらみごと、も、怒りの変種なのでしょうから、まあ、似たような作業にはなるのでしょうけれど。
うらみごと、を、なかなか素直に手放せないとしても、口にするときには、なるべく明るい形の話題にするとか、笑い話にしてゆくとか、少しずつでも、はらって頂きたいなあ、と思うことがあります。
なかなか、実践は難しいのですが、方向性ははっきりしていますので、一歩ずつ、積み重ねていけたら、と思っています。