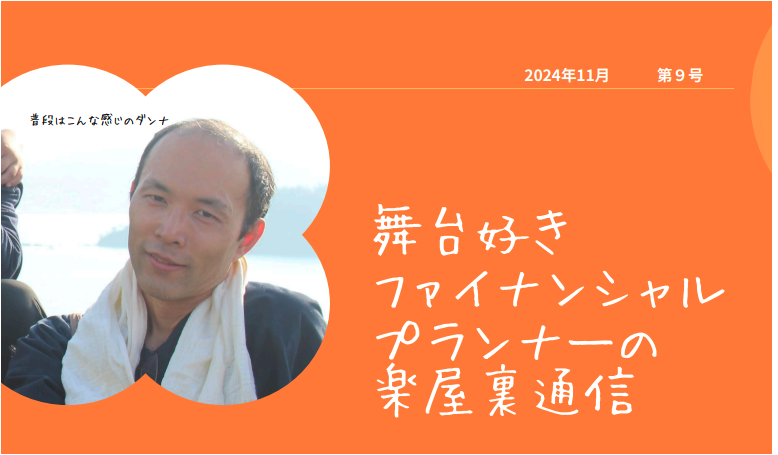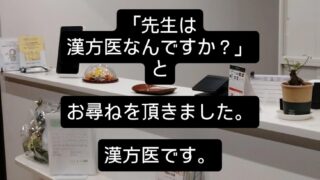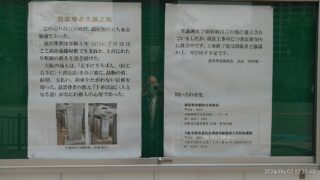おおきなひとたち

わたしが小さい頃、両親はとても「大きい」ひとたちでした。何かあれば、助けてくれる。困りごとがあって、どうしたらよいか尋ねたら、正しい答えを教えてくれる。くたびれて歩けなければ、抱えてくれる。とっても大きな存在だったと思います。
思春期の頃には、身長はさほど変わらないとか、あるいは母親の身長を追い抜いたとか、そういう年頃になりました。身体のサイズはそんなに変わらなくなったのですが、それでも、両親は「大きい」ひとたちでした。
学校の先生にもいろいろありましたが、とりわけ、高等学校の校長先生なんかは、「大きい」ひとでした。何が?と聞かれても困るのですが、やはり、大きな存在感がありました。
仕事をはじめるようになってから、しばらくは大学病院での勤務でしたが、教授は間違いなく「大きい」ひとでしたし、助教授も講師の先生方も「大きい」ひとでした。直接指導をしてくださっていた、病棟医長の先生方も「大きい」ひとの中に含まれていましたし、仕事をしながら「大きい」先生が…という言葉を使っていたのを覚えています。
診療のことや職場でのこと、どんなことを相談しても、答えて、解決までの道筋をつけてくれる、という点で、そういう「大きい」ひとの後ろについていたら、安心なのだ、とそういう風に刷り込まれていたのもあるのだろうと思います。
あたかも、ヒヨコが親鳥の後ろをついていくように、そういう「大きい」ひとの後ろをついて歩いていたのでした。
外の病院に赴任してからも、部長先生、というのは「大きい」ひとでした。本当に何か困ったことがあれば、全て相談して、解決してもらえる。そんな安心感がありました。
と、そんな生活をずっと続けていたのですが、ふと気がつくと、大学の教授はすでに退職をされており、部長もどんどんと変わり、自分よりも若い先生が関連病院の部長をされるようになりました。
そういう若い先生たちは、「大きい」ひとになるのだろうか…?と考えた時、そろそろ自分自身が「大きい」ひとの役割りを引き受ける年回りになってきたのだ、と気づいたのでした。
わたしの、父親との葛藤については、以前、取材してもらったことをご紹介しました。
だんだんわたしが父の体を診るようになってからは、関係が変わりました。今でも父は大きな存在ではあるのですが、「大きい」ひとの部分と、それから「ああ、この人のこれはどうしようもないなあ」とか、「ああ、末っ子なんだなあ」などと、どこか客観的にみている部分とが共存するようになってきたのです。
考えてみたら、駆け出しの頃に「大きい」ひととして頼りにしていた先生方も、今のわたしより若かったりします。「大きい」ひととしての役回りを引き受けていた、ということだけ、という部分も結構あるのかもしれません。
ところで。「大きい」ひととの関わりは、良いことばかりではありません。
その「大きい」ひとがわたしを責めたら、それはとても辛い話になります。
今から考えるなら、両親も若かったので、若気の至りなどもあったでしょうし、ひとの未熟さというのが出ていてもぜんぜん不思議ではないのですが…。
象の鎖、という話を以前ご紹介しました。
小さい頃に刷り込まれた世界観はなかなか変わらないこともあります。
「大きい」ひとと思っていたそのひとは、そんなに大きくなかった(なんなら今のわたしより断然若かった・未熟だった)、ということだって、あったりします。
そういう形で、今の大きくなったじぶんを認めることで、昔の「大きな」ひとから受けた影響を卒業してゆくことも、人生の中では大事なことなのかもしれないなあ、と思う次第です。