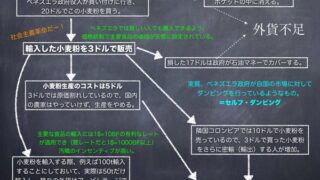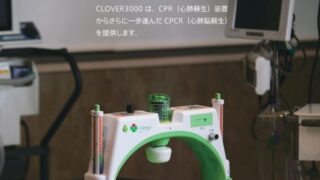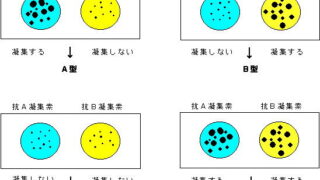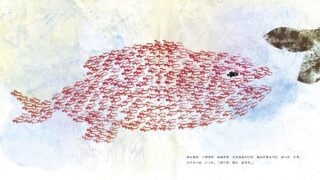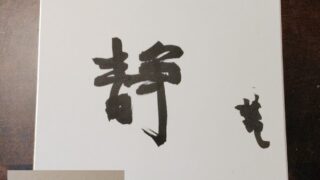ことばの賞味期限

当院は、漢方内科を標榜しています。
漢方内科ってなんだい?って話は以前、少し書きました。いわゆる「気」を前提にした診察や診療をしています。
じゃあ、その「気」っていうのは、一体どういうものなのか?って訊かれることも多いのですが、これを説明するのはずいぶん難しいのです。
説明するのが難しいものだから、存在しない、という短絡に走ってはいけません。むしろ、根源的なものであるために、その根源を、さらにもっと原則から説明する、ということができないわけです。
たとえば「ケーキ」は「小麦粉と油と卵、砂糖で作られた焼き菓子」みたいな構成要素で説明ができるかもしれません。じゃあ、「小麦粉は?」って言われたら、「植物のコムギの種子を製粉したもの」くらいの返事はできるでしょう。「種子ってなんですか?」って言われたら、それが何からできているのか、の説明は難しくなるでしょう。次の説明は「種子があると…」という形の説明になります。種子くらいの話なら、わりと見えるものですし、「これ。こんなの」って出してくれば説明できそうです。
もうちょっと抽象的なもので考えてみましょう。たとえば、算数でもよく使う「1」ってやつ。これをどんな風に使うか、とか、どういう性質をもっているか、というのは、わりと数学の時にやります。たとえば、自然数の中で、これを加算すると、次の自然数になる、とか、あるいは、乗算すると変化がない、とか。
ところが、この「1」を、厳密な根拠をもって定義づけるような説明をしようとすると、極めて難しいのだそうです。これについては、日本人の数学者、岡潔が「これはどうやっても説明ができない」と書いておられるのだとか。
数学のごくごく専門の分野に「数学基礎」という領域があって、「数学の基礎」じゃなくて、数学が成立する原理とか原則みたいなものが、どういう根拠があるのか、ということを説明する、という研究がなされています。この数学基礎の、とても分厚い教科書があって、その本をずーっと読んでいると、やっと中頃になって「…であるからこれによって1+1=2が説明される」と書いてあるのだ、と聞きました。
漢方医学の「気」も、それに似ているような感じの、ちょっとその辺にありそうなんだけれど、じゃあどういうもの?って具体的に訊かれると、答えに窮するような概念なのだろうと思っています。
もちろん、科学的には存在を証明されていません。
漢方内科、というところは、そういう意味では「非科学的な思考」を前提にした診療をやっているところ、という言い方もできるかもしれません。
医療が科学なのか、科学じゃないのか?なんていう話は、クリニックや病院を受診する時にはあまり考えません。が、医学生とか、医者は、わりと考えていたりする、らしいです。医学はきっと、科学なのだろう、と思います。医療は?医療は科学だけではなさそうですね。「アート」だ、と書いておられる方があります。アート=技術という意味でしょうが、「Ars longa, vita brevis」とは、ヒポクラテスの有名な言葉です。
脱線がすこし過ぎましたが、臨床では、科学的に正しいかどうか、よりも優先されるべき価値観があったりします。
そして、もうひとつ言うならば、科学的に正しい言説、というものは、しばしば、「枝葉を切り落とした」形で成立するものだったりします。
たとえば「太陽は(地球上からの観測では)東から登って、南天を通り、西に沈む」という記述を見てみましょう。
ひょっとすると、今日は曇っていたり、雨が降っていたりして、それが見えない時があるかもしれません。あるいは、夏の太陽と、冬の太陽は、出てくる場所も南天を通る高さも違います。
まだ、このくらいなら、もっと詳細な科学的説明を…と言われればできる範囲かもしれませんが、ヒトを含む生命活動における出来事は、科学的な説明で全てを記述することは、到底できない…と少なくとも今はそのように考えられています。
わたしの専門だった、産婦人科領域での科学的言説としては、分娩の時に新生児が生まれたあと、胎盤が娩出されます。この胎盤が自然に剥離するのを待つ場合と、積極的に剥離を促進する場合では、輸血が必要になるケースが、若干後者の方で少ない、という報告がされました。
後に「その差異は極めて小さいものであるから、必ずしも積極的な胎盤剥離を促す手法が薦められるものではない」という意見になりましたが、この場合に焦点が当てられているのは、2つの方針によって、「輸血をするか、しないか」ということで差がでたかどうか、というポイントだけです。
たとえば、子宮収縮薬をきつく使ったから、産後の後陣痛がとてもつらかった、などの「物語」は、ここには含まれません。
1対1の臨床をやっていると、しかし、こうした「物語」がとても大事になってきます。
そういう「物語」は、けっして科学的であるとは言い切れません。むしろ、科学的な判定を差しはさむなら、多くの物語が非科学的だ、と断罪されかねません。
ただし、エビデンスに基づく医療、という話をすると、科学的である論文に基づいた診療をすることが推奨される、みたいな話になってきます。
とはいえ、「物語」あるいは「ナラティブ」という視点で捉えるならば、医者が振り回しているこの「エビデンス」を重視する、という思想も、ある種の「物語」である、と言えます。
医者は一般的に、科学的な教育を受けていますから、その言説はなるべく、科学的な検証に耐えうるものにするべきだ、という価値観があるのだろうと思われます。特に、たくさんの人に届くような言葉を使うときは、科学的であるか、あるいは、少なくとも間違っていないであろうことを語るべきです。
でも、今ここの、目の前のひととの対話では、科学的であることよりも、優先されるべきことがあって、それが「物語」であると、わたしは考えています。
物語として納得すること、あるいは物語として腑に落ちる枠組みを作ること。それを目指して用いる言葉があります。
そういう言葉は、つまり、ことばの賞味期限が極めて短くなります。
今ここの、あなたとわたし、だからこそ、使われることば、ですから、同じ言葉を、別の場面に持っていった場合には、真っ赤なウソ、になりかねません。
ただし、臨床の積み重ねを、どこかで抽象化した智慧に変換してゆくためには、そのような賞味期限の短い言葉だけでは困ります。どこかで、「真っ赤なウソ」になってしまわない、そのような、射程の長い言葉を見出してゆかねばならないのかもしれません。