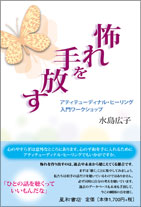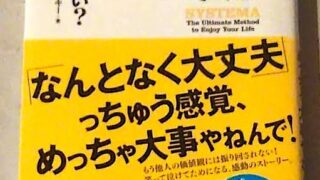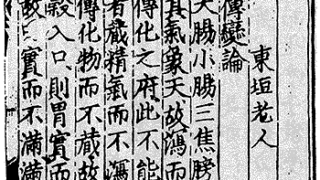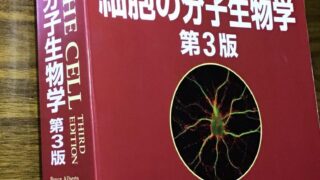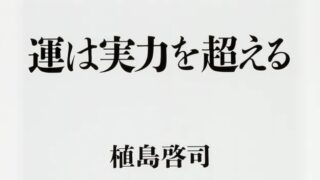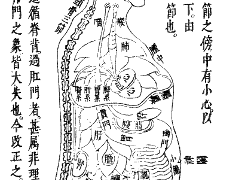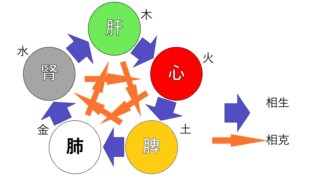ゆるす・ゆるせない・ゆるさない

こどもの頃。わりと喜怒哀楽というのは、あっという間に入れ替わったりするものでした。
「今泣いたカラスがもう笑った」と言われるような、そんなことがしばしばだったのかも知れません。
大人になると、メンツとかプライドというものが、だんだん重たくなってきます。
うっかり泣くこともなかなか出来ませんが、逆に、腹を立てたりした時に、振り上げた拳をどこかに落とすまでは、引き下がれなくなったりすることだってあるのかもしれません。
以前もご紹介しましたが、精神科医の水島広子氏がすすめている、アティテューディナル・ヒーリングでは、
平和と葛藤のどちらを選ぶか、怖れにとらわれるか手放すかは、常に自分で選択 できることをいつも心に留めておきます。
としてあり、今の(葛藤の)感情をそのまま維持するか、それとも、葛藤を手放して平和な感情を選ぶか、ということは、本人の一瞬・一瞬の選択である、ということを強調されています。
なぜ、わたしたちは、そんなにすぐに感情を切り替えることができないのでしょうか。
ボディートークの師匠である、増田明氏は、著作の中に「なぜ、家庭内暴力を振るう子供は、きょうだいが機嫌良くしていると、攻撃するのか」ということについて記述しています。
家庭内暴力で、暴れている子供は、だいたいは「息を詰めた」状態にあります。そして、いろいろな事情で、その「息を詰めた」状態を続けたいわけです。
ところで、機嫌の良いこどもは、息が緩んでいます。
緩んでいる息の声を聴くと、「ついつい、自分の息が緩みがちになる」のだそうです。このあたり、あくびの伝染に似ているのでしょう。
息を詰めた子供にとって、自分自身のアイデンティティは、この「息を詰めた」状態にあります。そこにプライドも乗っかるわけですから、家の中でのんびりした呼吸をしている者がいると、うっかり崩されそうになりますから、そのきょうだいに攻撃をする、と、攻撃された側として、呼吸を詰める…ので、本人のアイデンティティが守られる、というわけです。
ついうっかり笑ったら、それで良いじゃないですか。ねえ。
…って言えるくらいなら、そんなに深刻にはなっていないんですよねえ。きっと。
自分自身に、なんらかの形で呪いをかけたり、心にカギをかけたりして、「自分自身が緩んだ状態でいること」を、許せない、というのがあると、その「しんどい・つらい」状態から出てくることが難しくなります。
そういう意味でいうなら、やはり、あまり四角四面で厳しいひとよりは、どこか抜けていて、あるていどいい加減なひとの方が、悩みが少ない…と言えるのかもしれません。
その「まあ、いいか」と言って、許すことができるか、どうか、というあたり。
今泣いたカラスがもう笑う、でも、良いか、って自分を許せるようになれば、もっと楽になってゆくのかも知れません。
とはいえ、それは、自分のアイデンティティとの兼ね合いがけっこう難しいわけです。
少しずつでも、自分が許せる範囲を拡げていただくと、そのうち、ジワジワと楽になってくる…のかもしれませんけれど、なかなか、そこにたどり着くのが難しいなあ、と思う今日このごろです。