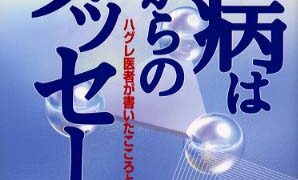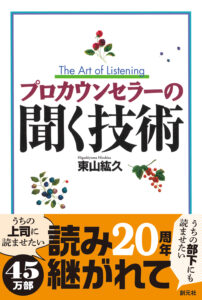わかげのいたり

中学・高校時代の思い出を引っ張り出して、話しようと思うと、まあ、あの頃は必要以上に尖っていたなあ…と思います。「若気の至り」とか、そういう言葉で片付けてよいものなのだろうか…と思うくらいに拗らせていたのでしょう。
わたしは、地元を離れていたこともあって、成人式には出席しませんでした。成人式のあとで、中学校の同窓会が開催されたのだそうですが、そういう事を教えてくれる友人も居なかったみたいで、しばらく経ってからそういうことだったのだ、と聞きました。同窓会に積極的に参加したいと思うような関係を作っていたわけでもなかったので、その時はそのまま過ぎたと思います。その後ずいぶん経ってからのことだと思います。わたしの心境も変わったから、なのか、なにかの折りに、同窓会の案内がわたしにも届き、たまたま顔を出すことにしました。
会の席で隣に座った、かつての同級生に、わたしとしてはごくごく普通に話しかけたのですが、話しかけられたその相手が、ずいぶんと挙動不審な反応をしていたのを覚えています。とても印象的でした。その後「あのにしむらと、普通に話ができるとは思わなかった…」みたいなことを言われたのです。失礼なことを言って!なんて腹が立つよりも何よりも「いったい俺はどんなやつだったのさ?」って聞き返したくなったものでした。
ずいぶんと扱いづらい、自意識過剰も良いところの、面倒くさいやつだったのだろうと思います。
高校のクラブでも「例の面倒くさいやつ対応係」が任命されていた…そうで、なんというか、任命された方には今さらの話ですが「お手数をおかけしました」と(これまた割と最近)お詫びしたところです。
大学に入った当初も、まだまだその「面倒くさいやつ」が続いていましたが、少しずつ、拗らせていたものがほどけてきた、のも、この大学生時代であったと思います。
この時期、増田明氏のボディートークのグループレッスンに参加したり、あるいは彼の主宰する子どもミュージカルに参加したりして、ひととの距離の取り方や、話の仕方を改めて修得し直したのだと思います。
そして、何よりも、尖ったままでありながらも、暖かい雰囲気の場所で受け入れてもらえた、という実感が、その尖り具合を丸めても大丈夫と感じることに繋がったのかもしれません。
まあ、今から考えると「黒歴史」的な中高生の時代だったとも言えるのですが…。他人事のように分析してみると、きっと何か自意識的なものを「持て余していた」のだろうと思います。
それが、年齢を重ねることと、暖かく受け入れてもらえたことで、だいぶと落ち着いたのではないか、というのが、わたしの理解です。
聞き取ってもらえていない、と感じると、ひとはだんだん声が大きくなります。
声が大きくなると、ますます耳を傾けてもらいづらいのですが、その矛盾には気づかないことが多い、ということもありそうです。
万人に、とは言いませんが、だれか、その言葉を拾ってくださる方がある、という確信があれば、ひょっとすると、持て余すものが小さくなっていく、のかも、知れません。