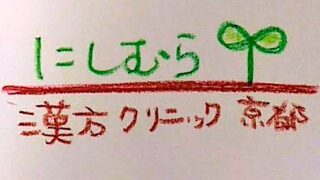わたしが書かなければならないことば
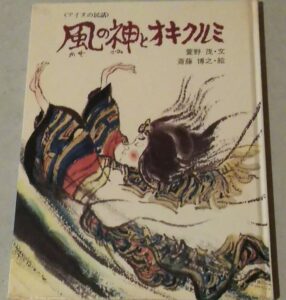
カルテは誰のものか?っていう問いが、臨床をやっていると、時々話題になります。もちろん、カルテを記入している医師のもの、という言い方ができるでしょうし、同時に、そこに書かれているものがたりの主役は、患者さんですから、患者さんのもの、ということもできる、というところです。
漢方内科として診療をしていると…と言っても、取り立ててなにか、昔と変わったつもりもありません。なので、かつて、産婦人科の片隅で女性漢方外来をやっていたときもそうでしたし、「漢方」の看板を揚げていない時も、わたしの心持ちとしては変わってはいないつもりではあったのですが…患者さんやご家族の「物語」に触れることになります。
そういう物語を、診療の文脈で拾い上げて、カルテという記録に書き込むわけですが、このところ、自分でもびっくりするくらいに「文学的」な表現が増えています。
・背中を預けられる仲間がいないまま、一人で頑張ってきた背中。
・耳の奥に張り付いた怒鳴り声。
・いろいろややこしいことがあった脈。
・頑張りが過ぎた腰。
それらは、いわばわたしが受け取った「心象風景」ではあるのですが、この心象風景は、誰のものなのだろうか…と考え込んでしまいます。
近代に至ってから、西洋医学は、人生と、疾病を、どこかで切り離すことを佳しとしました。
疾病の責任をぜんぶ引き受ける必要はない、という思想は、本当に福音に近いものだったのかもしれません。
旧約聖書の中に「ヨブ記」という小編があります。ここではヨブという名の「まったく正しい」男が、神の気まぐれで病を得るのですが、その時に親戚も友人も皆が「それはお前の生き方が、どこかで神の思し召しに背いたからであろう」とヨブを責めたてます。ヨブは自分自身が正しいと信じていますから、病に苦しみながらも、胸を張って反論します。そんなヨブから友人も家族も離れていき、彼は孤立します。正しい、と自分で主張する態度が、傲慢と捉えられて、ひとが離れていくことに繋がったのかも知れません。
コロンブスが新大陸から持ち帰ったとされる梅毒も、その後清教徒たちが「神の意向(清く正しい生活を送るべし)に背いたから、このような病気に感染したのだ」という思想から、性的に純潔を守る、という行動規範に繋がっていったのだそうです。
このように、病気の原因や責任を、病を得た個人の行動や思想に求めることを、人類はずいぶんと長い間、当たり前にやってきたのだと思います。
それが、疾病のモデルが変わることで、病を得たひとは「病気の原因と責任を持つ者」から「たまたま病におかされた気の毒な人」に格下げになったわけです。
この格下げは、ある意味で病気に苦しむひとを助けることになりました。だから福音と呼べるわけですが、同時に、病気に苦しむ当事者から責任を剥脱することを通じて、その人を軽んじるような意識が発生したのかもしれません。
現在、かまびすしい程に「インフォームドコンセント」とかあるいは「治療方針の決定には患者自身の参画が」というような表現がなされるようになったのは、責任を剥脱されたことで、個人が疎外されていたことへの反動とも言えるのかも知れません。
さて。漢方医学は、古いシステムですから、病の原因を半ば、個人に求めることもあります。
「ずいぶんと長い間、無理をしてきたことが、今の体調不良につながっている」
「睡眠時間が短いことで、寝不足なのに、昼間は職場で眠ってはいけないから、強い緊張をしており、それが次の就寝時刻になっても続いてしまっている」
「頭の緊張が強すぎて、熱が発生しているのを逃がしそびれたので、その熱が皮膚で炎症を引き起こしやすくなっている」
「夏場に食事が摂れなかったせいで、今、胃腸の力が落ちている」
などという、いわば文学的な表現を、わたしのカルテでは病態のところに書いています。
こうした、ひとの人生と、病や不調についての「文学」ないし「物語」が、当院のカルテになっている、というわけです。
おそらく、系統だった診察と評価というものを基礎とする、西洋医学の教育の中では「落ちこぼれ」の評価をもらいそうな、「主観」まみれの言葉であり、考察です。
が、このように、ひとの身体からの物語を聞き取り、またご本人のお話を聞き取ることは何か、とても大事な気がしています。不調に悩む方が、その根っこになっているような懸念を話されることが、まさに「放す」ことに繋がっていて、核心になるような言葉が放たれると、ずいぶんと心の重荷が軽くなっておられて、不調が解消する方向に向かう、と感じることがあります。
そして、個別のお話は、それぞれ個々人の、極めて個人的な悩みだったり、苦しみではあるのですが、それらを通して、今の社会が持つ歪みのようなものが浮かび上がってくるようにも思われます。
さすがに現代社会の病理をなんとか変えていく…というような大それた話にはなりませんが、ひとりずつの物語を大事にすることをやっていくことが、どこかで社会の病理の解決に繋がっている、と、そのような気がしています。