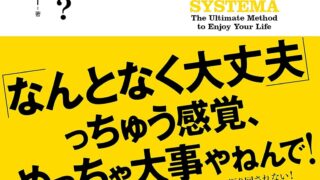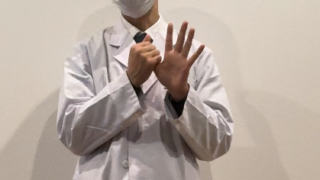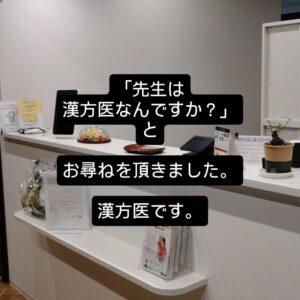カフェインは不安を高める…?

ドラマなどでは、すごくショッキングな出来事があって、駆け込んできた主人公(?)に、支えてくださる方が「ちょっとお茶でもしましょう?」と、お茶…ないしコーヒーをいれる、というような場面の描写が、時々あります。
ドラマでなくても、あふれるような不安や悩みを抱えて訪れた友人に、「お茶にしようか」と、飲み物を準備することは、時々あるのかもしれません。
温かい飲み物を摂ると、ちょっと気持ちが落ち着きます。
ところで。そういう時の飲み物として、「カフェイン入りは注意」という話もあります。
カフェインが入っていると、不安が増強するのだ、という説があります。
https://www.harpersbazaar.com/jp/beauty/health-food/a36692232/caffeine-and-anxiety-210612-lift1
カフェインが入ると、それによって、交感神経が刺激され、関連するホルモンが分泌されるようになるから…というような説明がされています。
個人差がけっこう大きいようですので、ひとによって反応が違う、というところも注意点ですが。
なるほど。カフェイン、やっぱり不安を高めるのか…。と考えていたのですが、最近、頭のはたらきについて考えている時に、ふと思い当たることがありました。
そもそも、頭は「心配事や不安を事前に想定して、その対処やシミュレーションを済ませておく」ためのシステムです。心配事も不安も持ち合わせていなくて「いけるいける。大丈夫だって!」と突っ走るひとたちには、頭…というか、面倒くさい思考そのもの…はあまり必要ありません。
そういう、突っ走る仲間を引き留めたり、あるいは「以前にこういう悪いことがあった」という記憶を引っ張り出したり、はたまた「もしこんな悪いことが待ち受けていたらどうする」と想定して、対処の準備をしてから臨むように指導したり…というように、一歩踏みとどまって、事前に対応を準備したり、心構えをさせたりすることで、集団の生存率を高める、ということのために、頭を使うひとがムラに居るとよかった、というのが、頭を使うシステムが成立して成功してきた事情ではないでしょうか。
アタマを使うからカシラなのかも知れません。
頭を使っている個体にかかる負荷は大きい気がしますが…集団の存続という報酬のためには、やむを得ない犠牲なのでしょうか。
カフェイン、というのが、不安を高める、という単純な道筋もあるのかもしれませんが、もうひとつ。カフェインというのが、「頭の働きを高める」という作用を持っているとするなら。「不安を抱える」のが頭の本来の働きです。
つまり、頭をスッキリ使えるようになれば、不安を想定することも軽々と出来るようになる、という形では、頭の本来の働きを取り戻した、と言えるのかも知れません。
フィクションの世界では、こうした不安や、恐怖感などが適度に入ると、文章のスパイスになりますが、実際の日常で、あまりスパイスが多いと、それはそれでずいぶんと辛い人生になりかねません。
特に、いましんどいことがある方の場合は、さらに困難を高める必要性はあまり無い…ように思うのですが、しんどいことがある場所を切り抜けるためには…って考えると、想定される困難とか不安とかもどんどん大きくて大変なものにしてゆかねば、対処が間に合わない、と身構えてしまうのが頭の癖としてあるのかもしれません。
そういえば、昔野田俊作氏が、「心理治療には2種類の方向がある」と書いておられました。
西丸四方先生がおおむかしに『精神医学入門』という本を書いておられて、学生時代に教科書代わりに使ったのだが、その中に「あばき療法」と「おおい療法」という面白い言葉で、心理療法の分類をしておられる。「あばき療法」というのは、精神的な問題点を自覚させる方向の治療法のことであり、「おおい療法」というのは、自己受容や他者受容を促進する方向の治療法のことだ。
「あばき療法」と「おおい療法」 https://adlerguild.sakura.ne.jp/diary/2016/08/02.html
ひとつは「あばきたてる」系の治療。分析をきっちりかけて、問題点を言語化してゆく、というような形の、「しんどい」治療方針です。
もうひとつは「覆いくるむ」系の治療。治療というか、ヒーリングというか…という話なのですが「だいじょうぶ。だいじょうぶ」と安心と安全を提供するかたちで、問題をなるべく直視しないようにする系の「やさしい」治療方針です。
カフェインを飲んで対処しよう、という方針はどちらかというと、「あばきたてる」系に近いのでしょう。
それでなんとか対処しよう、対処できる、という立場におられる方は、かなり能力が高いと言えるでしょう。
逆に、問題があまりにも大きい時には、ちょっと見ないふりをして、忘れておく、というのも大事なのかもしれません。
こういうときには、あまり頭脳明晰にしておくよりは、少しボンヤリしている方が楽になるのかもしれないなあ、なんてことを考えています。