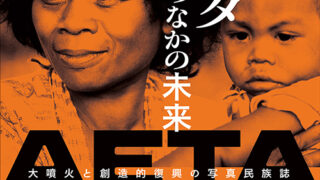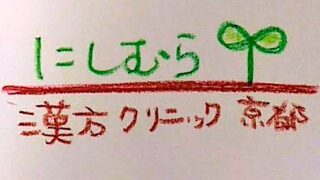タイプ論
タイプ…と言っても、タイプライターの話ではありません。
……なんてちょっとボケてみたのですが、タイプライターもすでに、骨董品になってしまいました。
ルロイ・アンダーソンの作曲で、そのものズバリ「タイプライター」という楽曲があります。オーケストラに混ざって、タイプライターの駆動音が音楽に組み込まれている、というもので、軽快なリズムで、明るい、素敵な曲です。作曲は1950年なのだそうです。当時はまさにタイプライターが現役だったのでしょうが、名曲として、時折演奏される曲は現役でも、タイプライターというものが、現役を退いて、ずいぶんと経ってしまいました。最近、この曲を演奏するタイプライターを、どうやって調達しているのだろう…?と不思議におもいつつ、今動いているものが動かなくなる頃には、この曲も演奏されなくなるのかしら?と要らぬ心配をしております。
閑話休題。
C.G.ユング氏も『タイプ論』という形で硬派な本を書いておられます。わたしは手が出せていませんが、まあ、そこまで大上段に振りかぶらなくても良い話にさせてください。
日本人に、いちばん身近なところでいうと、血液型や星座別の性格分析的な話もすべて「タイプ論」になります。『B型自分の説明書』 なんていうのもありました。血液型と性格との関係もあるように思えますが、でも科学的には「関係ない」ってことにされているみたいです。
血液型の話題だけではなくて、ひとの性格的な分類をする本がしばしば出ては話題になります。ちょっと古いですが「どうぶつ占い」なんていうのもありましたし、エニアグラム診断、なんていうのもあります。その他、最近はビジネス系でもいろいろなタイプ分類をする話を見聞きするようになりました。
わたしが以前、そのような分類のひとつとして耳にしたのは「類人猿診断」というものでした。
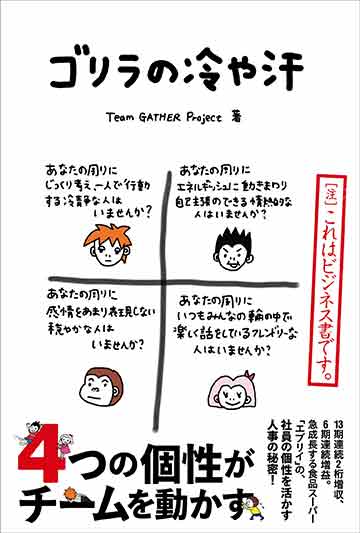
もっとも私たち人間に近いとされる大型類人猿。
チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、ボノボ。
その性格は、それぞれまったく違います。
単独行動で職人肌のオランウータン、
ムラっ気が強いけどリーダーシップのあるチンパンジー、
秩序を守る物静かなゴリラ、
愛嬌があって互いの気持ちを大切にするボノボ。
こういう、4タイプくらいの分類だと、覚えるのも容易ですし、わりと現場でも使いやすいのかも知れないな、と思います。
わたしの精神科医の師匠は、「こういうタイプ論で、自分とは違うタイプの人がたくさんいる、ということを理解するのが大事だ」と言っていました。4タイプが人数で均等に分かれると仮定しても、自分と同じタイプの人口は、決して多数派ではないのだ、と。
そして、こういう形で「他人には、他人のタイプがあるのだ」ということを承知することで、自分自身の理解にもつながります。
あるいは、他者の行動を多少なりとも理解する…あるいは理解不能なものだとあらためて認識する…ひとつのきっかけになるのかも知れない、と思います。
師匠はこうも言っていました「ああいう、タイプ論、ってだいたい、どれかひとつ、2つはものすごく生き生きとそのタイプが描かれるのだけれど、その熱が全体にまんべんなく、というわけにはいかないものだ」と。だからB型人間はとっても盛り上がったけれど、他の血液型は今ひとつだっただろ?って。
あとの具体的な話はどれがどう、と言ってませんでしたが…