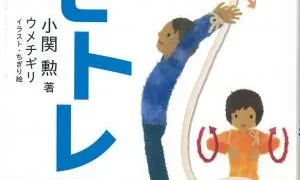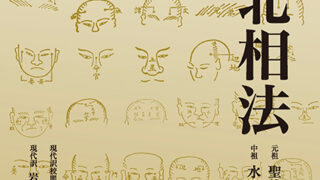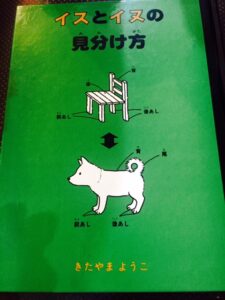ヒトは優秀なセンサー

保険診療をしていると、患者さんが個人で負担される医療費の金額はたいていの場合「3割」ということになっています。あとの「7割分」は保険者が支払いをしてくれる、というのが、現在の医療保険の制度です。
この「3割」の窓口負担をゼロにしよう、という運動も細々と続けておられる先生がたがいらっしゃいます。(医療費の窓口負担「ゼロの会」)生命に関わることでありながら、窓口負担があること自体で、受診のハードルを上げているから、もっと安価に…というか、支払い無しで受診できるように…という主張をされておられるわけです。
昔、総合病院で診療していたときに、「どうしてもっと早くに相談してくれなかったのか」と言いたくなる状態で担ぎ込まれてくる方も診せていただいたことがあります。今さら「もっと早くに来たら…」と言ったところで、時間が巻き戻せるわけでもありません。
むしろ、こんな状態になるまで、よくお一人で頑張って来られたなあ…とそういう思いをお伝えしたように記憶しています。
窓口負担を減らすことで、経済的に、生活が厳しい方が受診しやすくなる、という主張をされる方がいらっしゃる、その一方で「コンビニ受診」と呼ばれるような、安易な受診も増えかねない、という懸念をされる方もおられます。コンビニ受診、と言いたくなるような病院の使い方にも出会ったことがあります。このあたり、本当に難しいところです。
保険診療の「価格」というのは、診療報酬という形で「定価」が定められていて、2年に1回のペースで見直しがされています。いわゆる診療報酬の改訂、というのがこれにあたります。
たとえば、診療所での再診料は75点。処方箋料は60点。どれだけ時間をかけても、あるいは時間をかけないでも、再診であれば、この保険点数が適用されます。
価格の変動に対応して、1点あたりの報酬額をスライドさせられるように、という思想から、保険は「点数」を介して計算しますが、診療報酬制度が成立して以来、基本的には1点10円の計算がそのまま続いています(船員保険などでは1点20円の計算になるそうです。これもいろいろと事情があってこのようになったのだと聞きましたが、大変まれです)。
その他、いろいろと機器(レントゲンや採血などもそうした検査の一部に該当します)を使ったりする検査があれば、その分は診療報酬として請求できますが、「ゆっくりじっくり話を聞く」「身体に触れてみる」などの行為には、診療報酬が設定されていません。もうちょっと、丁寧に診療したら、報酬が増えるような構造になっていても良いように思いますが、まあ、医療費の削減が叫ばれている昨今では、難しいのでしょう。
そんな事情の中で、漢方の診療をすると、たいていの場合、お金の話をすると、診療報酬的にはきわめて渋い結果になります。なかなか採算がとれません。診察に時間がかかることと、そうした時間をかけた診察をしても、評価されて、報酬が増えるしくみが無いからです。
漢方専門でやっておられる先生方、どうやって生活を工面しておられるのでしょうか…?
当院も、まあ、ご多分に漏れず、なかなか渋い経営状態が続いています。
とはいえ、やりたいことをやりたい形で、出来るようになったのが嬉しいわけで、この場所は維持してゆきたい。それを経済的な面で成立するように…となると、完全に自費での診療、というような形になりがちなのですが、そうすると本当にお金持ちしか診療を受けられなくなってしまいます。苦肉の策として、完全予約制として、予約料をいただく形にして、ゆっくりとしたスタイルの診療をなんとか守っているところです。
診療報酬制度の中では、ヒトの手で触れたかどうか、ということには、さしたる評価がなされませんが、手で触れることで得られる情報はすごく多いわけです。
そういう意味では、ヒトの手を中心とした「生体」というものは、大変に優秀なセンサーなのだと言うことができます。
もちろん、それを上手に言葉に変換してゆくためには別の才能も必要だったりします。
わたしの臨床は、そういったヒトの身体をセンサーとして用いることで、診療をしています。最近の機械はだいぶ高性能になってきていますが、まだまだ、わたしのやっていることは、機械がマネできるようにはなっていない、と自負しています。