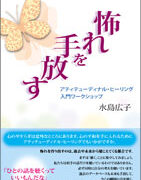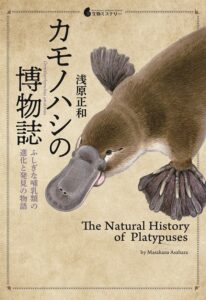モチベーション

先日「やる気が出ない」とおっしゃって受診された方がありました。時々、こうした訴えで来院される方がいらっしゃいます。
いろいろな状態の方がありますが、まあ、西洋医学の病院では「特に異常はない」とか「ストレス(等の心の問題)が原因なのではないでしょうか?」というような対応をされることが多い様子です。
漢方では、「やる気が出ない」もひとつの異常である…と考えています。多くは「気虚」と呼ばれるような状態。つまり、ガス欠ですね。
ひとが行動するには、エネルギーが必要になりますが、そもそもそのエネルギーが十分に供給されていない場合は、何かをやろう、やりたい、という気が起こりづらくなります。
ヒトの身体は漢方的な言い方をすると、「先天の気」として腎に蓄えられているものと、それから「水穀の気」として、脾(=胃腸=消化器官)で食物を消化・吸収して使うものがあります。ある意味で腎はバッテリー、脾はエンジンのような、まあハイブリッド構造になっているわけですが、これらの気が欠乏すると、てきめん、やる気が失われる、ということになります。
人間関係などのしがらみがあると、単純に「ガス欠だから、今日ははたらきません」というわけにもいかないこともありますので、何らかの形でごまかしごまかし、身体を動かすことも出てくるわけですが、まあ、あまりそればっかりやっているのも不健康になります。
可能なら胃腸の状態を整えて、水穀の気を巡らせていただきたいところです。
ということで、たいていは、そういう、胃腸を整えつつ、気を補う処方をお出しします。
「やる気が出ない」という方の多くが、こうした気虚の方のように思われるのですが、時々、気虚ではなくて、それでもやる気が出ない、という方もいらっしゃいます。こうした方は、やる気の元になるような、動機付けが見つけられない、なんていう場合もあります。
子どもが、勉強を、あるいは、宿題を、なかなかはじめないでヤキモキするような思いをされる、という親御さんも結構多いかもしれません。あるいは、ご自身が「やらなきゃないことがあるのに、なかなか手につけられない」と焦燥感にかられていたり、ということだってあるでしょう。
こうしたときに、「とりあえず手を動かす」というのも、やる気を出す良い方法だったりします。
もちろん、完全にガス欠の時には動きません。が、そうじゃない場合、意外と手を動かすことで、少しずつやる気が出てくる、という逆説的な現象が発生します。
わたしも過労うつで寝込んでいた時に、「あなたもいい加減、どこかインドにでも行っておいで!」と尻を蹴飛ばしてくださった方がありました。まあ、まだまだ過労うつで、気力が満ちていたわけではありませんが、かといって、家の中で引きこもっていても、新しい気を取り込むことが出来ない状態になっていたのだろうと思います。
当時、インドで食べた食事は、本当に空になったわたしの何かを、あらためて満たしてくれる、そんな感じがありました。
気うつの時にこそ、運動を、というのは、なので、決して筋の悪いアドバイスではありません。が、これもまた、運動できるだけの体力が無い時に、周りからやいのやいの、と言われると、かえって嫌気がさしてしまいます。このあたり、結構難しいところです。
モチベーションの話、もうちょっと別のことを書くつもりだったのですが、長くなってしまったので、明日改めて書くことにします。