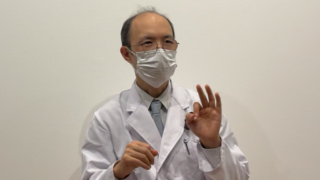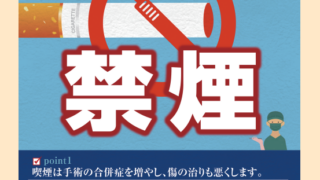主治医であること

わたしは大学病院で研修を終えて、1年、修練医として産婦人科の病棟で勤務していました。
その後近くの総合病院に赴任したわけですが、まあ、わかりやすいくらいにわたしが一番下っ端でした(研修医の先生が出入りしていたはずなのですが、あまり記憶にありません)。
赴任して早々、「外来を担当してもらうよ」と当時の部長に言われ、ええええ!?と驚きながら(大学病院では外来業務に触れる機会がなかったので…)「いや、外来やったこと無いですけれど…」と返事したら、「大丈夫だ。だれでも最初ははじめてだから」と押し切られました。小泉進次郎構文じゃねえか!って今なら思います。
大学の時に指導してくださった先輩に相談したら「大丈夫。看護師さんの言うとおりにしていたら、無事に終わるから」という智慧をくださいました…。あまり役に立ちませんでしたが。
そんな時代に、受け持ちの患者さんは少しずつ増えていったものでした。
外来の看護師さんは、時間外の受診の時に、なるべく主治医を呼び出す、という対応をしてくださっていました。時間外で受診されている、ということは思いがけない何かが起こっているわけです。そんな不測の事態に対応できるような自信はあまり無かったので、呼び出されるたびに、逃げ出したい思いでいっぱいでした。
何もこんな下っ端を呼び出さなくても…と思いながら、病棟から外来に向かっていたことを覚えています。
ある日、同じように呼び出しがかかって、外来に向かっていたのでした。たまたま、通った通路から、待合で待っておられる患者さんの顔が見える形になりました。患者さんは、余所を向いておられたので、わたしの方が、先にその方のお顔を認識したのですが、ずいぶんと険しい顔つきをされていたのでした。と、思っているところで、わたしに気づいてくださったのですが、そのとき、患者さんの険しかった表情が急に緩んだのでした。今でも覚えています。
診療の実力とか、知識の量とか、医者としての経験年数とか…いろいろと足りないものはあるかもしれないけれど、この方にとっては、わたしが主治医なんだ、という認識をあらためた経験でした。
主治医である、ということは、たぶん、そういうところにあります。
知識が足りなくて良い、とか、診療を間違ったり、失敗したりして良い、とか、そういう意味ではありませんが、どれだけ科学を重んじたとしても、臨床の現場というのは、ひととひととの関わりが主体になるわけです。
一緒になって一喜一憂することが、本当に良いのかどうか、は、疑問に残る部分もあります。が、わたしがだれかの主治医である、ということを引き受けるきっかけになった思い出です。