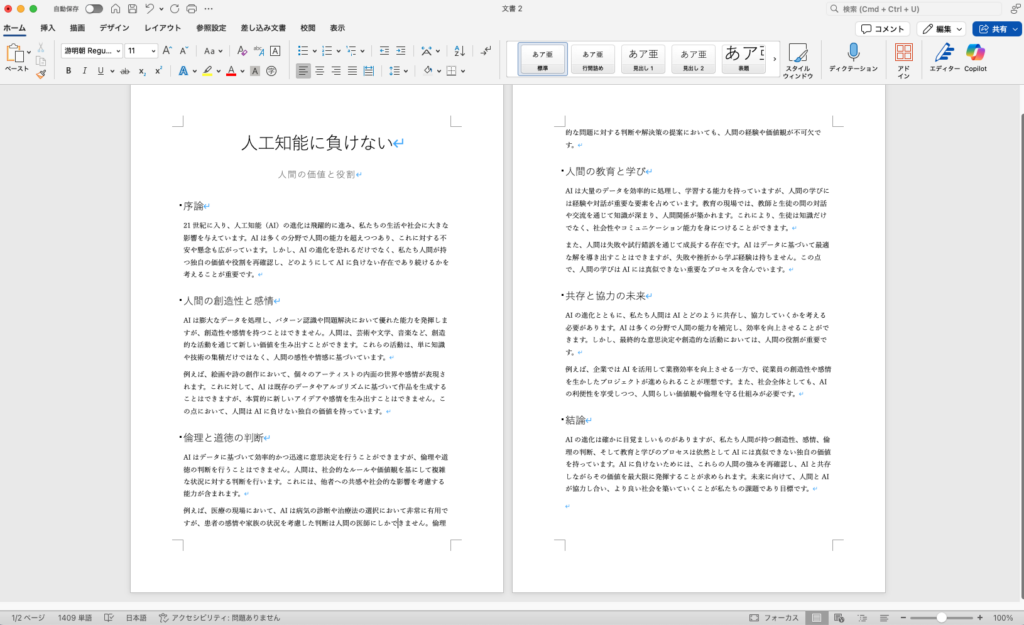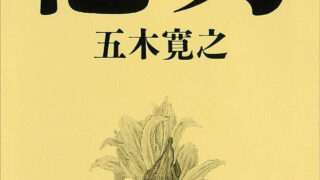人工知能はカウンセリングができるのか

最近、チャットGPTにカウンセリングして貰っている…というような話を見聞きするようになりました。最近の人工知能は、だいぶ賢くなって来たらしいです。
人工知能がカウンセリング?という話を、そういえば以前も書いたことがありました。イライザと呼ばれるシステムが存在していたことがあります。
1960年代のことだったようです。英語は、プログラミング言語に近いため、自然言語をそのまま受け止めて、整理して「あなたはこういうことをお考えなのですね」と返答する、ということを繰り返していた…のではないか、と思います。
最近の人工知能は、そこからずいぶんと進歩してきましたので、本当に自然な言葉づかいになっています。
ある種の枠組みを作って、きっちりとカウンセラー的な挙動をするようにコマンドを入れると、それなりにカウンセリングが成立するのでしょう。
ただし、このあたり、いわゆるカウンセラーにかかる、というものとは、ずいぶんと違います。たとえば「時間制限がある」とか「話を出来る日が決まっている」という、生身のカウンセラーの「枠組み」が、人工知能にはありません。
極端な話、「いつでも」「いつまでも」相談ができる、ということになります。
それが必ずしも良いことにつながるかどうか…というあたりは考えもの、でもあるようですが。
「枠組み」が治療的な効果を持つ、というのは、どういうことなのか?を考える必要があるのかもしれません。治療的、という言葉の意味だって、あらためて考えることが必要でしょう。
今までの、にんげんのカウンセラーだったら、そりゃ毎日、24時間いつでも、なんていう対応が出来ないことはわかりきっています。だからこそ、枠組みがあって、その枠組みの中で、という話になります。
治療、というのは、そういう「にんげんの制限を破綻させない」という形に適応する、ということも含まれていたのかもしれません。
つまり、「次回までの間にしんどいことがあっても、じっくり待つ」ということは、治療のスタイルと、治療提供のリソースが制限されている、ということから、重要になっていた、という視点で考えるなら、人工知能がいつでも、いつまでも対応ができるようになった結果として、依存的になる…かもしれませんが、どれだけ依存的になっても、ちゃんとそれに対応できるとも言えるわけです。
それが治療になるかどうか…という点は、治療の目標をどこに設定するか?というそもそもを考えねばならないのでしょう。
相談をされる方が、人工知能に包まれて生きる世界線があるのかもしれません。
そういえば、星新一のSF短編に、そのようなものがありました。
(ーーにしむらによるうろ覚えあらすじ紹介ーー)
人工知能(らしきもの)を搭載した「鳥」を肩に載せて、相手との交渉の通訳をさせるわけです。
本音をボソッと伝えると、極めて流麗な、耳ざわりの良い言葉に変換して、この鳥がお喋りする。相手も似たような鳥を載せていますから、その難解な言葉遣いで返事してくる。
その返答も鳥に聞かせて、「で、本音はなんて言ってるの?」って尋ねると「鳥」が端的に「お断りだ、って言ってます」的な話を返してくる。もう、そこまで行くなら、間に挟む「鳥」要らないのでは…?と思いたくなる世界ですよねえ…。
仕事が終わったら、自分の「鳥」はお休みさせて、居酒屋のマダムに供応して貰うんですって…。(星新一「肩の上の秘書」『ボッコちゃん』収載だそうです)
とりあえず、本音はどうであれ、伝える時に上手なオブラートに包む、というのが大事、って話でもありますが…。
カウンセリングの話をしていたのでした。
カウンセリングとは、いったい何を目指した、どのような行為なのか、という部分は、わりとふんわりしています。なので、場合によっては、こうした人工知能による応答がカウンセリングとして作用している、と言うこともできるでしょうし、また別の場合には、「それではカウンセリングとは呼べない」と言うこともできるのかもしれません。
にんげんがやっているカウンセリングは、じゃあ、人工知能の返答よりも優れている点があるのだろうか?あるとするなら、それはどこにあるのだろうか?っていうことになります。
いちばん簡単に答えられる部分は、人工知能に、どう話しかけて良いか分からない、という方向け、というのがあります。
つまり、人工知能の上手な使い方が分からないので、ひとに相談した方が良い、という、入口の部分。
最近、JRの駅の切符売り場もほぼ自動になりましたが、面倒くさい切符は、有人の窓口で相談したりします。
それと同じように、相談したいことがボンヤリしている、という場合には、人工知能に持ちかけるよりは、ひとに聞いて貰う方が整理が進む場合もあります。
日本国内はだんだん、労働人口が減っていきますので、どこも省ひと化してきていますから、それなりに機械相手の操作を、客側のひとたちが慣れなければいけなくなっていますが。
人工知能が、まだ到達していない点のもうひとつは、相談者の表情を読むとか、言葉の行間を読む、という名人芸の部分です。
尋ねられた言葉に、まっすぐ答えるのは、人工知能でも出来るようになりましたが、質問の背景とか、今、このタイミングでそれを尋ねてくる事情とか、そういうことを勘案して、まっすぐじゃない返答をする、というのが、にんげんのカウンセラーにはできます。
そのうち、そんなことも出来るような人工知能が出てくるのかもしれませんが、もうしばらくは、そうした「空気を読む」機能はにんげんの方が優秀なのだろうと思います。
そして、もうひとつ。
「意外性」です。
これは人工知能に実装するのが結構、難しい。
カウンセリングの中でも、まあ、名人芸の領域に入るのかもしれませんが、「意外性」をもった返答をする、とか「意外性」のある提案をする、というのは、これは生身のカウンセラーならでは、ということになるのだろうと思います。
この「意外性」をきっちり演出できる対話こそが、カウンセリングだ、としてしまうと、人工知能のやっていることは、違うよね、という話にもなってくるわけです。
それぞれのカウンセリングに求めることが違うので、まずは何を求めているのか?を整理しないと、有効かどうか、ということも判定できない、ということになるわけですが。