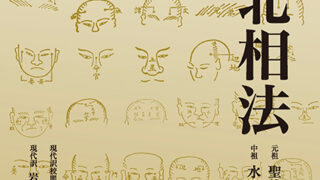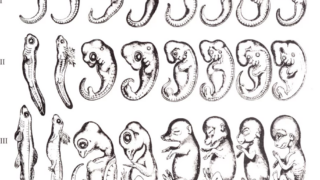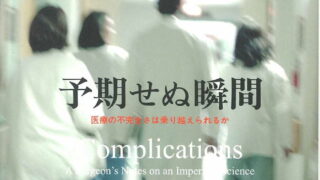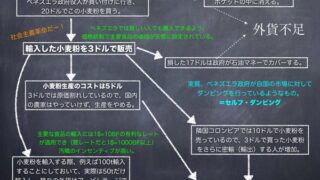人生の指針

人生の指針、というほど大きなものとも言えないかもしれません。
「迷った時には…」という話ですが、これを、わたしは父から聞いて覚えました。
わたしの父は、本当に不器用な生き方をしてきたひとだったようです。
そもそもの話からはじめると、父の父である祖父が学生のころ話に伏線があったりします。
祖父は、もともと商家の三男だったそうです。
「商家のにんげんなのだから、商業高校に行くのが当たり前。大学も商学部に進むべし!」という明治の頃の話でした。
大学に進学すること自体、珍しいことでもあった時代ですが、商業高校から、商学部ではなくて、経済学部に進学したようです。
ところが、卒業したのは文学部だった?ようで、一体なにをどうしていたのやら。
商家の気質には沿わなかったひとだったのかもしれません。
その後、公務員として真面目に働くつもりでいたのが、何かのタイミングで妙なことを吹き込んだ友人?がいたそうで、入職早々から机に足を載せて、英字新聞を読んでいた…なんていう話も聞きました。
手に負えないやんちゃだったからなのか、その後松江に赴任して高校の教員をやっていたりしていたようです。
公務員ってそんなに勤務先がいろいろ変わるの?ってビックリしましたが、当時はそういう事情があったのだとか。
晩年は京都の地方公務員として、図書館の整備などに尽力したそうですが。
まあ、そんな祖父のもとに生まれ育った末っ子の父は、どこか学究肌だったのでしょうか。
いろいろと就職の準備が進んで、さあ就職する、というところで、いきなり方針転換して大学院に進学したのだそうです。
当時は、父の祖父(わたしの曾祖父)がまだ存命で、「大学院に進学させてください」と若い頃の父が頭を下げ、曾祖父が「そんな研究しても食えたもんじゃないぞ」とおどかした、という話を、これまた当時のいとこが目撃していたと聞きました。
うーん。進路の相談を、父親(祖父)にするのではなくて、その父(曾祖父)にお願いしに行った、ってのがどうしてか、は聞いていなかったですが。
何かあったら、頼る、とか、相談する先だったみたいです。
そんな父が、しばしば口に出して言っていた「迷った時は…」という話です。
「迷った時には、お金の儲からない方に進め」というのがその指針でした。
本当に商家の孫なのかしら?と疑問に思うくらい、ちょっとノンビリした指針です。大丈夫だったのでしょうか。
お金は、とても魅力的です。
ですが、その分、判断を鈍らせる危険があります。
お金が儲かる、という話になったことで、判断が鈍る可能性がある、という話なのでしょう。
学会の発表や論文では、最近「利益相反」という話をします。
つまり、研究報告をするにあたって、どこかからお金を貰っていたりすると、その分、スポンサーに有利な主張をしがちになる可能性が高まります。
なので、事前に「わたしはどこそこの関係企業からお金を貰っています」とか、あるいは「そのような相反する関係を有していません」とか、そういうことをしっかり言いましょう、というのが学会のルールになりつつあるのです。金額の多寡ではなくて、もらっている、ということで、批判の刃が緩むのだ、という話もあります。
人生の進む方向も、スポンサーがいるとかいないとかは別にして、お金が入ってくるかどうか、という話をあまり熱心に追いかけると、自分自身の中で、利益相反状態を引き起こしてしまいそうです。
お金が絡まない時にしようとする判断とは、微妙に違ってしまいそうです。
それを戒めた言葉なのかもしれない、と思っています。
とはいえ、経済活動を続けるには、それなりの収入が無いと続かないのも実状です。
そのあたり、祖父も、父も、公務員みたいな仕事でしたから、割と超然としていたのかもしれません。うらやましいような、そうでないような。
良い時代だったということなのかもしれません。