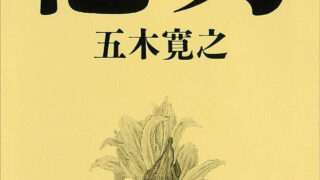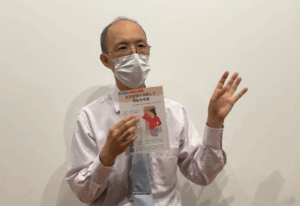便秘と漢方の話その2
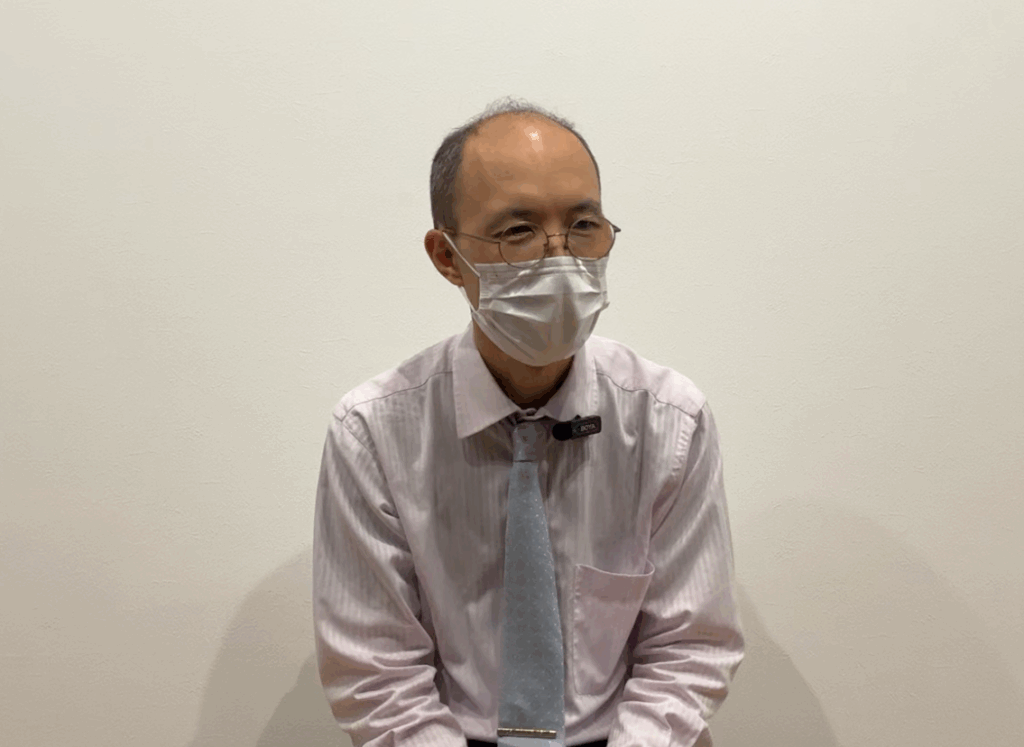
先週末に行った健康教室「便秘と漢方」の話を昨日に引き続いてやってまいります。
便秘というのは、やはりヒトの身体にとって、不調の原因になる…ということが知られていたのか、チンパンジーだったか、ゴリラだったかが、体調の悪い別個体に、下剤作用のある花を取ってきて渡した、というエピソードが観察されているのだそうです。
類人猿の時代から、下剤は薬だったのかもしれません。すごいですよねえ。
医療用で使っている漢方エキス製剤は、古くは『傷寒論』という3世紀くらいの処方をもとにされているもの…から、昭和の時代に作られた20世紀の処方まで、雑多に混ざっているのですが、この『傷寒論』という本の冒頭には、「感染症でたくさんひとが亡くなった。こういう時に治療法を間違って、下剤をつかってばかりいるから、今後そういうことが無いように、治療法のマニュアルをまとめた」というような話が書いてあります。
最近の治療法ではありませんが、漢方のもともとの治療法は「下剤をつかって下させる」か、あるいは「吐法」といって、「吐かせる」というのが主な治療の手段だったようです。
さすがに吐く方は、なかなかつらいものがあるようで、現在処方されているエキス製剤にはその効果をもつものがありません。
まあ3世紀の本の、さらにその前から下剤は治療薬だったわけですから、それは歴史があります。
そして、漢方の「気・血・水」の理論によると、便が溜まって、出てこない状態が続いているものは「血」がかたまったものだ、ということになっています。ずいぶんと乱暴な意見ですが、婦人科系のトラブルはだいたい血の問題とされる一方で、便通が改善すると症状が良くなる方も多いので、意外と見当違いでもないのかもしれません。
血の問題って、具体的には「血の道症」…今のPMSとか更年期障害とかまるまるまとめて、そう言っていたようです…に加えて、生理痛なども血の問題とされます。婦人科で漢方をやっておられる先輩は「女性の問題はともかく便秘の解消なんだ!」と豪語されていました。
そんなことで良くなるのか?ちょっと違うんじゃないの?って思ったりもするんですが、そういえば、インド伝統医学の「アーユルヴェーダ」ってのがあるんです。そのアーユルヴェーダの中で治療法に「パンチャカルマ」って呼ばれる一式があるんですが、これが、5種類のメニューってことになっています。
ヴァマナ(嘔吐療法)、ヴィレチャナ(下剤療法)、バスティ(浣腸療法)、ナスヤ(鼻洗浄)、ラクタモクシャナ(瀉血療法)
というのが5種類で、瀉血するんだ!とか吐かせるんだ…とかいろいろ思いますが、「下剤」と「浣腸」が別々に出てくるんですねえ…一緒じゃないの?って思うのですが、違うのでしょう。
アーユルヴェーダの治療では加えて、オイルマッサージで発汗させたりもします。
漢方でも発汗させるのはひとつの治療法で、「発表」なんて言います。表面を開く…「発する」という意味で、汗腺を開く、というような意味合いです。典型的には葛根湯なんかがその方剤のひとつになります。
…っと、また脱線しておりましたが、ええと、下剤の話です。
下剤作用のある生薬にはいくつか有名なものがあります。「センナ」というのがそのひとつで、有効成分は「センノシド」と呼ばれます。これは、精製されて、西洋医学の中でも便秘に対する下剤として採用されています。薬の名前も「センノシド」。昔は「プルゼニド」という名前でも処方されていました。赤い小さい粒がよく知られています。
実は、漢方で使う下剤作用のある生薬としては、「大黄」が有名です。古典落語では閻魔大王を呑み込んで…下す(なぜなら、「ダイオウ」は下剤作用があるから)という落ちの作品がありました。当時はダイオウと言えば下剤、だったのでしょう。
この大黄の有効成分が大変面白いことに「センノシド」ということになっています。結局同じ成分だった、ということのようですね。
大黄には、その他に清熱作用とか、駆瘀血作用があります。便秘自体が腸の動きをとどめる形になりますので、あまり長くなると、瘀血を形成する、と考えられます。昔は、便の塊そのものが、動きの悪くなった血だと考えられていたようなフシも見受けられます。
もうひとつ、下剤作用のある生薬としては芒硝が有名です。これは鉱石が生薬として使われているものであって、硫酸ナトリウムの結晶ということになっています。これは浸透圧を用いて、腸壁の水を腸管内に引き込んで、下剤作用を発揮するようです。
現代医学では酸化マグネシウム、というのがよく使われていますが、似たような効果を発揮していると考えても良いのかも知れません。
こういった生薬を配合された処方が、漢方の中には結構あります。それらを使うことで、便秘を解消してゆくことが多いのですが、大黄も芒硝も、お腹を冷やす働きがあります。胃腸が冷えすぎて、排便する力が無い、などの場合には、むしろ腹痛を引き起こすことも懸念されます。
そういう場合にはお腹を温めつつ、動きを引き出すような処方が選ばれたり、大黄の量を減らして他の生薬でなんとか調整する、などの工夫がされることもあります。
また、現在のエキス剤には用いられていませんが、他にも下剤作用のある植物はいくつかあります。
手近な有名どころでいうと、牽午子(けんごし)というのがあります。これはアサガオのタネですが、もともと、アサガオのタネが高価だったから、馬(=午)と交換する程の値打ちがあった、という意味で牽午子と言われているのだそうです。
わたしが聞いた話では、どこかの漢方医が、とあるお金持ちのお嬢様の便秘(ないし腹痛)をこの生薬で治療して、報酬として馬を貰って帰ってきた、というものだったのですが…そんなによく効くんだ!って思った記憶があります。
最近は、あまり治療で使われることは多くありませんが、まれに子供のおままごとなどでアサガオのタネを口にするなどして、下痢することがあるそうで、いろいろと注意も必要です。