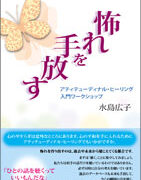健康教室「冷えと漢方」
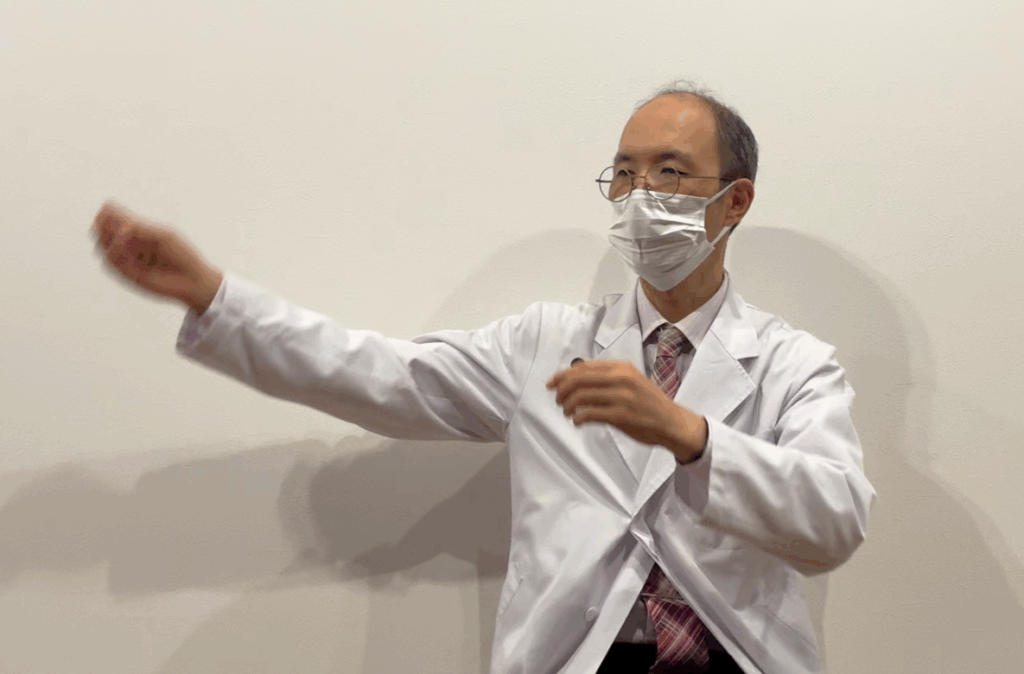
先日、2025年11月の健康教室を開催いたしました。
お題は「冷えと漢方」としてお喋りさせていただきました。
「冷え」ってけっこういろいろなところで口にしますが、西洋医学的な話の中では、あまり出てくることがありません。
あ。「キャッチ・ア・コールド」って言いますよねえ。風邪を引く、という言葉には「Cold」が入っていました。
末梢の血流がとても悪くて、寒くなると指先の色が「真っ白」に。そこから暖まってくると「→青→赤」と三色に変化するような、そんな病気があったりします。こういう症状を「レイノー現象」と呼んだりはしますから、冷え、というものそのものが皆無、というわけではないのでしょうけれど。
「冷えって、漢方では、5種類くらいあるんだってね」って妻はあるとき、帰ってきてそんなことを言いました。
ええええ?そんなにあるの?って慌てて数えてみました。
数え方によって違うんだろうなあ…と思いながらですが。
大きく分けると、「全身が冷えている」パターンと、それから「局所が冷えている」というパターンがあります。
全身が冷えているパターンには、大きく分けたら2種類くらいありそうです。
1つは「脾虚」とか「脾気虚」とか言われる、胃腸の調子が弱っている状態。
もうひとつは「腎虚」あるいは「腎陽虚」と呼ばれる、先天の気を溜める腎が弱っている状態です。
脾はいわば、エンジン、腎はバッテリー、みたいなものですから、どちらも「電源からの供給が弱い」というような状態です。
「局所が冷えている」という話になると、末梢の冷え、あるいは病的に局所がどこか冷えている、という話になりがちです。
もちろん、身体の中心から温める力が弱いと、遠方…つまり末梢では冷えが出てくることもけっこうありますが、同時に、熱を運ぶ力が弱いと冷えが出てくる、というのが、この「局所の冷え」に該当します。
巡るもの、というと、漢方では「気・血・水」ですので、それぞれの巡りが悪くなっている状態で、それぞれ冷えが発生します。巡りが悪い、だけじゃなくて、巡るべきものが足りない、というような状態でも熱の運搬が進みませんので、冷える、ということになります。
いわば、セントラルヒーティングのボイラーが不調か、それとも配管に不調があるか、というような考え方に近いでしょうか。
漢方の治療としては、基本的には、双方をうまいこと調整しつつ、熱をしっかり巡らせるようにする、ということが大事になってきますが、病態ごとに少し処方が変わります。
たとえば、局所の冷え、という方の中には「冷えのぼせ」と呼ばれる病態の方もいらっしゃいます。つまり、手足などは冷えるのだけれど、頭は熱くなっている…というような状態です。
こういう方に、ひたすら温めるような処方を使うと、のぼせてしまっていけません。
そうではなくて、巡りを改善するような処方を選ぶことになるわけです。
温める生薬として有名なところは「生姜」でしょうか。
「大建中湯」という処方には「人参・山椒・乾姜」という三種類の生薬と、それから「膠飴」というアメが入っています。山椒も刺激になりますが、温める方向性と言って良いでしょう。
特に最近では、開腹手術後のイレウス予防に用いられることが増えてきました。これも手術の時に冷えたお腹を温めているのだ…と考えることができます。
さらに冷えているような方には「附子」という生薬を用いることがあります。附子…トリカブトは、そのまま使うと神経毒の作用があって、いわゆる毒物なのですが、これを加熱することで、神経毒の成分が変質し、つよく温めるはたらきと、それから水を動かしてむくみを取るはたらき、鎮痛作用などが残ります。
巡りがわるくて冷えているという病態では、それぞれ巡りの悪さの事情によって処方がかわります。
冷えのぼせ、というキーワードでわりとよく用いられるのは「桂枝茯苓丸」でしょうか。いわゆる瘀血に対する処方として有名ですが、血流の悪化に伴って、頭の熱を逃がしきれなくなると、頭がのぼせる一方で、手足の冷えが強く出てくる、ということになります。
手足の冷え、というキーワードで出てくる処方としては「四逆散」というのがあります。こちらはもっぱらストレスによる緊張で巡りが悪くなった時に用いる処方です。
似たような名前の処方に「四逆湯」というものもあります。
これらの処方の「四逆」というのは、手足が冷えている状態を指すようです。
四逆散はどちらかというと、ストレスによる手足の冷えを捉えた命名だったようですが、四逆湯はむしろ、巡りが悪いことと、芯の温めるはたらきが低下していることの複合状態に用いるような処方です。
エキス剤としては「当帰四逆加呉茱萸生姜湯」が四逆湯に当帰を加えた「当帰四逆湯」に、さらに「呉茱萸」と「生姜」を足した処方という名前になっています。きっと一番漢字が多い処方ではないか、と思っていますが、シモヤケなどによく用いられます。
西洋医学的な話をすると、体温を作り出す部分の中心は「筋肉」ということになっています。この筋肉が機嫌よくはたらく状況は、ちゃんとカロリーもタンパク質も足りている状態であり、かつ、筋肉自体が緊張しきっていないところ、となります。
しっかり胃腸の調子を整えて、消化吸収ができるようになっていることと、筋肉がかたまっていないで、しっかり動く状態になっていることが、体温を高めて、冷えを取り除くためには大事、と言えるのかもしれません。