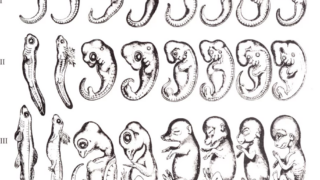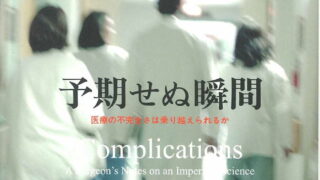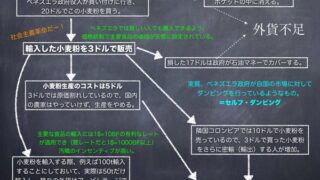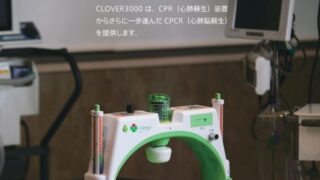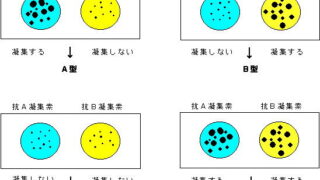原子力のはなし
夏ですので…という枕詞がかかるのは、本当はちょっと違うのだろうと思います。
けれど、8月のセミしぐれと、強い日差しは、「お盆」とともに、原子力のことを考えるような、そんな季節になって、ずいぶんと経ちました。…というより、わたしが生まれる前に、そんな季節になってしまっていました。
わたしが子どもの頃、夏休みの登校日と言えば「平和学習」というのが定番であったほどに、反戦・非核の映像を見る機会でした。
そんな原子力の、今日は、「平和利用」について少し書いてみようと思います。
質量が、エネルギーに変換されるのだ、という理論を打ち立てたのはアインシュタイン博士でした。E=MC2という式は、あまりにも有名になりました。それをきちんと説明するのは難しくても、この数式は見覚えがある、という方もけっこう多いでしょう。わたしもそのクチです。
どうしてそこが光の速度の二乗で成立するようになったのか、とか、そもそもどうやってその答えにたどり着いたのか、とか、いやいや現実はもっと複雑なのだから、もっと複雑な計算になるのだ、とか、むしろ世界はシンプルなのだ、とか…いろいろと議論が出てきそうな式でもあります。そういう議論関連のことは、わたしにはわかりませんが、それでも、この、質量をエネルギーに変換しうる、という理論と、その実践は、人類に大きな影響を及ぼしました。
最初にエネルギーを取り出した時、それは爆弾、という形で実現されました。
そういえば、星新一の短編のなかに「おみやげ」というものがあります。わたしは昔、国語の教科書でこの話を読みました。
人類がまだ類人猿とさほど区別がつかなかったころに、地球を発見した知的生命体がありました。
おみやげとして、様々な知識を残して行きます。それを頑丈な金属のタマゴの形にして、気候の変動が少ない砂漠に放置するのでした。
「技術が進歩して、この金属を加工して中身を取り出せるようになれば、その内容を理解できるだろう」という思いとともに。
それから、幾星霜。とうとう、そのタマゴが開かれる日が来ました。
しかし、それは、決して喜びを伴ったものではありませんでした。
砂漠における原子爆弾の実験で、中に詰まっていた知識ごと爆風に吹き飛ばされて、消失してしまうのでした。
そのような暴力的なエネルギーの放出からの反動があってか、戦後は「原子力の平和利用」ということが前面に押し出されたのでした。その象徴となったのが、原子力発電所です。
当時、原子力についての研究室は、最も人気の高い分野になっており、幾多の秀才が集まっていたのだそうです。
「いずれ、こうした秀才…のあとに続く秀才たちが、原子力発電の廃棄物処理について、何かの知恵を出してくれると思っていた」と、養老先生がちらっとおっしゃっていました。そのような期待をかけられていたようです。現実的には、原子力発電が実用化された途端、原子力関連の研究室の人気はがた落ちし、廃棄物については問題を先送りしてきた、ということのようですが。
2010年には『100,000年後の安全』という映画が公開されました。これは、フィンランドにつくられた放射性廃棄物処理施設の話題です。
その処分場は「オンカロ」と名付けられました。フィンランド語で「洞窟」の意味だそうです。

10万年先まで、高レベルの放射線を放出している物体を、ここに放置する、という話ですが、じゃあ、10万年先の人類が、これが危険なものだ、と認識できるだろうか…?という話題が出てきます。危険!とわざわざ書いた方が、好奇心を刺激して、むしろ掘り返す者が出てくるのではないか…という懸念だってあります。
「これだけ頑丈に守ってあるのだから、さぞ貴重なお宝が眠っているに違いない!」なんていうのは、ゲームでの定番になりつつありますので…。
じゃあ、何も書かない方が良いのか?文明が断絶して、書いてある言葉が理解されなかったらどうしたら良いのか?心配事はいっぱいあります。
日本における放射性廃棄物の処理も、なかなか難しい話が続いています。
日本では六ヶ所村に再処理工場などが設置されていますが、全ての放射性廃棄物をここで処理する、というのも難しい話のようです。
ところで、原子力発電所が、どのように原子力のエネルギーを、電力に変換しているか、ご存知ですか?
単純に言うと、原子力のエネルギーを放出させたもので、お湯を沸かして、その蒸気でタービンを回すことで、発電をしているのだそうです。結局お湯を沸かすための熱源を、石炭でするか、石油にするか、あるいは原子力にするか、ということの違いでしかないようです。もうちょっと上手にエネルギーを取り出して、ロスも無いままで電気に変換できるような、そういう技術があれば素敵なのですけれど…。
…という話になると、核分裂じゃなくて、核融合を起こしてエネルギーを取り出すのが良いのだ…という話があったりするようです(いや、核融合であっても、結局水を沸かしてタービンを回すのは変わらないのだ、という話もあるようですが)。核融合は、安全に、安定した形でエネルギーを取り出すには、まだもう少し研究が必要な様子ですが…。
技術的な話はともかくとして、知人の哲学者が「もし、技術的な問題が解決して、廃棄物処理の問題も、安全性の問題も解消されたとき。クリーンなエネルギーが十分に供給されるようになった場合…」と書いていました。「そこには、どのような社会があらわれるのだろうか」というようなことを。
エネルギーについて、「我慢しなくて良い」状態になったとして、ひとは、今まで通りの慎ましい生活を続けることができるのだろうか。我慢しなくて良い、ということで、傲慢にならないのだろうか。
原子力の話題を考えるたびに彼の投稿を思い出します。
無尽蔵のエネルギーを、手に入れた人類は、いったいどのような心持ちで、それを利用し、どのように変わっていくのか…。
技術の制約があることで、その先を、今は見ないで済んでいるわけですが、今のうちに、きちんと哲学的な議論を積み重ねておかないといけない…の、かもしれません。