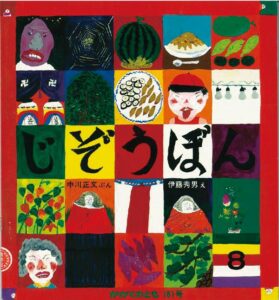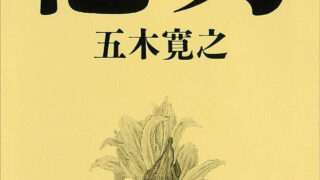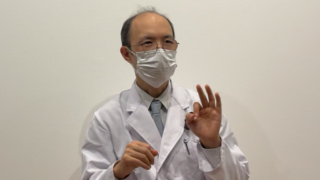地蔵盆
京都市内では、この時期に「じぞうぼん」というのが開催されます。
京都市内だけではなくて、近畿ではわりとよく知られた行事…であるようですが、町内におまつりしてあるお地蔵様にお経を唱えたり、数珠回しなるものをしたり、というのがその中心…かと思いきや、いわゆる夏祭りの様相を呈しているのがとても興味深いものです。
わたしがいちばん最初に「じぞうぼん」という言葉に触れたのは、たぶん、小学校くらいの頃のことだった…と思います。当時、わたしは福岡県に在住していましたので、周囲を見渡しても地蔵盆の風習は無く、この「じぞうぼん」という言葉はその後、長年にわたり、謎でした。え?お盆とは違うの?なんか違うらしいんだけれど、どういうこと?的な困惑をもって、絵本を眺めていたように思います。
そんな記憶をもとに、検索をしてみました。たしか、何かの絵本で、じぞうぼんの紹介…と言うには断片的な…夏祭りの描写があったのでした。
じぞうぼん
かがくのとも|1982年8月号
じぞうぼんとは、子どもたちのためにくりひろげられる上方特有のお盆です。お地蔵さんを丁寧に洗って、あんどんを作って、みなでお供え物を供えてお祈りします。おばあちゃんのあいずで、数珠まわしも始まって、子どもたちは1年の無病息災をお地蔵さんにお礼します。町のよりあいで行われたじぞうぼんの様子を描きます。(かがくのとも161号)
調べてみたら、1982年の「かがくのとも」だったようです。かがくのとも…なんですかねえ?いまひとつ、そこは、合点がいきづらいところですが…。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E8%94%B5%E7%9B%86
Wikipediaによると、そのほか、大日如来を祀っている町内では28日に大日盆とする、ような記述がありました。お地蔵様扱いされていて、地蔵盆に駆り出される大日如来さまもけっこういらっしゃるようです。
町内で、子供向けに何らかの催しをし、子どもたちの楽しみの季節でもあったようです。夏休みの終わりがけではありますが、一大イベントになったのでしょう。
最近は微妙に新学期が始まるタイミングが早まりましたので、学年暦とにらめっこせねばならなくなりましたが。
地蔵菩薩というのは、賽の河原で、水子が石積みをしているのを、見守っている…というイメージがすごく強いのですが、それはマンガの影響でしょうか?
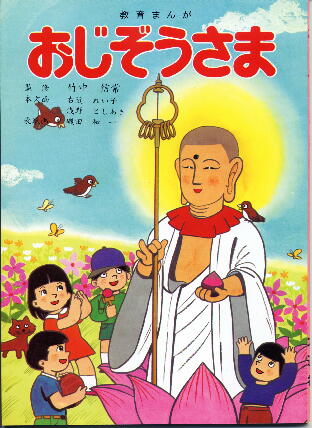
ただし、お地蔵様は、鬼からかくまってくれはしても、鬼をやっつけてくれたりはしないのです。
このあたり、どうして…?と子供心には思ったものでした。それだけ力があるなら、鬼をやっつけてくれたら良いじゃない…?って。
今なら、わかります。鬼はやっつける対象ではないし、そこの克服は子どもたちが自分でせねば意味がないのだ…ということなのでしょう。
さすがお地蔵様。きっちりと課題の分離をなさっていらっしゃる。
そんなお地蔵様は、地域の子どもたちに加護をくださっています。それを感謝する縁日に相当するのだ、ということでした。
それぞれの町内で、なさっていることは差がありますが、お地蔵様にお経をあげたのち、子どもたちの縁日的なイベントと、プレゼントなどを準備されていることが多いようです。
今日は地蔵盆の縁日の日。地域の子どもたちの健やかな成長を祈りたいと思います。