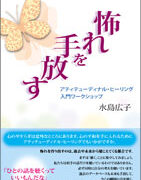坊主が取るか、医者が取るか

「坊主が取るか、医者がとるか」
昔は、そんな俚諺があったのだそうです。
どちらの出番があるか、って話で、まあ、冗談みたいに言われていますが、つまりは、医者の仕事がなくなるかどうか、ってことでしょうから、「生き死に」に関わるような状況のことを指していたわけでしょう。
江戸時代のお医者さんは、偉くなると「法眼」とかっていう職位をたまわっていたのですが、これは、お坊さんの職位です。
もともと医療を担っていたのがお坊さんだった、っていうところから来ていて、その後もあたかもお坊さんであるかのような擬制が続いていたのだ、という話を聞いたことがあります。
そういえば、昭和の中頃くらいまでは、困りごとの相談は「駆け込み寺」って言ってました。つまり、相談に駆け込む先は「お寺」だったわけで、お坊さまっていうのは、そういうムラビトたちの生活の相談からなにから、というのに対応するお仕事だったようです。
そして、もう少し遡れば、中国から伝わる書物はお寺に収められる「お経」でした。医療と仏教は、日本において、結構長い間、深く関わりを持っていたのだろうと思われます。
破れ寺も増え、無住寺もたくさんあるようですが、それでも、一昔前は、コンビニエンスストアの数よりお寺の数の方が多かった、というのですから、結構な数のお寺がありました。
誰も守るひとがいないなら、廃寺にしたら良いのに…と思わなくもないのですが、実際にお寺を潰すことになると、その時の住職は「破門」になるのだ、と聞いたことがあります。破門になると、もう、僧侶じゃなくなる…?はずなので、よほどの厳しいルールですよねえ。
仏教の教えの中には「ひとの苦しみについて」という洞察が結構多く含まれています。
なんなら、お釈迦様のことを「医王」と呼ぶ言い方もあるくらい、お釈迦様は医療にも造詣が深かったという言い伝えもあるようです(そういえば、手塚治虫の『ブッダ』の病者の中では、輸血を行うシッダールタ氏が描かれていました)。
そういう点では「坊主がとるか、医者がとるか」という表現もずいぶんと近代になってからの言い方になります。だって、それまでは「坊主がとるか、坊主がとるか」だったでしょうから。
ところで、医療の中でもいろいろな分野がありますが、例えば「痛み」というものについて、いろいろな分類をされていますが、そういう分類のひとつでは、「身体的苦痛」の他に「精神的」「社会的」そして、「スピリチュアル」な苦痛、という形で、人間存在の意味などに付随するような「苦痛」すらも、痛みの1つとして考える、という思想があります。
この「スピリチュアルな」苦痛なんていうのは、生死の狭間になくても、宗教の方が得意、なのかもしれません。
漢方の古い本にも名医の記録として、薬を使わずに治す、などという物語が残っています。
そういえば、古代医学のひとつ、アラビア医学にも似たような話がありました。
ある所の王さまが、リウマチに罹られて、身体を動かすのもあちこち痛む、という状態になったのでした。そこで、近隣から名医を探し出し、この医師に治療を命じたわけです。
名医と呼ばれた者は、王を診察し、高額の報酬を「前払い」で求めました。
王が前払いを済ませると、湯浴みの時に、いくばくかのマッサージを施したのでした。そして…。
いきなり、報酬を持って逃げ出すのです。
「治療する」と請け負った医師が、報酬を持ち逃げした、となったので、王は激怒します。
あまりにも怒りが高ぶった結果、自分で馬に乗って、追いかけてくるのですが。王さま、リウマチで、痛かったはずじゃなかったの?
そうです。この「怒りに駆られて追いかけてくる」ところまでがその名医の計算でした。
約束通り、きっちり治してみせたわけです。
こういう「相手の感情を上手に作用させて、身体の調子を整える」という方法があります。
「移精変気」と呼んだりする方法ですが、日本では、あまり漢方医がこのようなことをした、という記録は多くありません。たいていは、お坊さまがなさっていることになっています。
いや、お坊さまは医者じゃないんだし…とは言わないでください。
困ったときに相談を受けていただいて、その解消に上手に気を動かす、というのも、それはお坊さまの人徳あってのことです。
うまいこと、坊主が取る、でやっていただけたら、と思います。