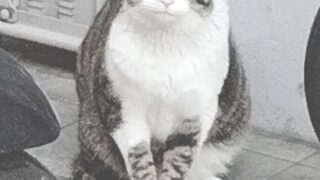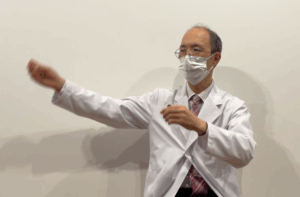奇跡は起こらなくなったのか

子供たちが小さい頃、昔話の本を読み聞かせたりしていたことがありました。
その昔、わたしが小さい頃には、うちに、「おじいちゃんの本」と呼んでいた、分厚い、童話集があったのでした。おじいちゃんが購入してきていた、位の古い、ふるい本でした。
本当に幼い頃、読み聞かせてもらっていたのを覚えています。
旧仮名遣いの本でしたが、長じてからは、自分でも読んでいたような記憶があります。
表紙にエンボス加工のようなものがあり、父は、その幼少期に、表紙のでこぼこに紙をあてて、鉛筆でこすって、その模様をうつしていたのだとか。
そういえば、表紙のでこぼこのところ、装幀が剥げてしまっていましたっけ。
(現在、現代仮名遣いに書き換えた本が出版されているようです。わたしが読んでいたのは下巻の方でしょうか。本当に息の長い本ですね。)
そんな思い出があった、ということも影響していたのでしょう。昔話の本を見つけては、たまに(仕事も忙しかったはずですので、そんなに毎日、というわけでもありませんでした)読み聞かせをしていた…と思います。
昔話の中には、かなり頻繁に「狐や狸」がひとを化かす、という話が出てきます。
最近は、めっきり減ったように思うわけですが、いったい、あの頃の狐や狸は、どこへ行ってしまったのでしょうか?
子供の物語の中に、「さいごのオバケ」というようなのがありました。昭和の終わり頃に書かれたであろう、その童話には、「最近は、オバケじゃなくても、変な物音がいっぱいあって、ひとは驚かなくなってしまいました」みたいな文章がありました。
世の中が複雑になりすぎて、狐や狸が入り込む隙間がなくなったのでしょうか。
SNSなどを見ていると、それでも、時々「狐に化かされたような」と書いておられる方があります。どうやら、山道などで、脱水とか低血糖の時に、そのような幻覚みたいなものが出てくる、ということらしいです。ひだる神へのお供え、などと言って、かならず、握り飯みたいなものを持って行くのだ、とした戒めがあったりする地域もあるようです。
山道を歩いて、低血糖を起こしたときの備え、と、現代ではそのように説明するのでしょう。
低血糖や脱水の時に起きる知覚の異常を、医学的には「せん妄」と呼ぶことがあります。
そういえば、数年前に、乳腺外科の先生が、患者さんから「わいせつ行為をうけた」と訴えられて、社会的に大きな話題を呼んだことがありました。
手術後に見る「せん妄」の中では、かなり妙なことが発生することも多いようです。
昔話には、河童、というのもよく出てきました。ちょっとした川の、淵には、河童が棲んでいて、そこで泳いでいる子供たちの尻子玉を抜くのだ、という話があります。
尻子玉ってなんだよ…って思いますが。
現代的な解釈をすると、川底が深いなどで、複雑な流れになっているところだったりします。そのようなところで川遊びをしていると、水にさらわれて連れて行かれてしまう、ということもあったのでしょう。
理屈を「あそこは水の流れが不安定で、危険だから」と説明するよりも、「河童が出るので」という方が、水の事故を防ぐ効果が高いのであれば、それは、きわめて合理的な判断であったでしょう。
そういった、狐狸のたぐいが言挙げされなくなってきた昨今では、「狐憑き」というのも激減しました。
昔は憑いた狐を落としてくださる専門家がいらっしゃったのですが、最近は高齢化にもなり、引退されたり、逝去されていたり…するのだそうです。
そもそも、狐が憑いている、ってなんだよ、なんですけれど。ねえ。
全ての物事が、まるごと科学的な説明の中におさまるようになった、わけではないのでしょうけれど、にんげんが見る事象の多くが、それによって説明されるようになると、わたし達の目が、そのような見方をする、ということもあるのかもしれません。
蒙昧な信心深さが生み出していた「奇跡」は、冷徹な科学的思考では認められなくなる、なんていう、啓蒙主義の物言いが本当に適切であったのかどうかの判定は措いておくとしても、そのような傾向が大きくはたらいたことは否めないでしょう。
じゃあ、奇跡、ってなくなったのか?って話ですが。
そんなことはありません。
日々、わたしたちがこの世界に生きていること、そのものが奇跡なのです。
そして、わたしたちが、ひととひととの中で、日々、出会いがあることだって、きっと奇跡、なのです。
いつの間にか、当たり前、と油断して、そのありがたさを軽んじてしまっているのかもしれません。