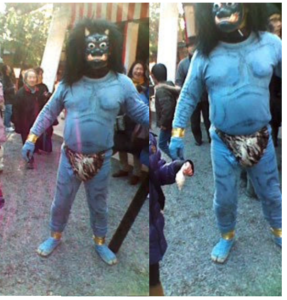強い言葉を使う時の注意点
以前、過労うつで寝込んでいたころの話です。もともとわたしは本の虫とも呼ばれたくらいに本を読んでいたのですが、体調を崩してからは、読もうとするだけで眠気が出てきてしまい、本が読めなくなりました。
その後、少し回復してきて、文字が読めるようになってきた時に、ネット小説というものに出会ったのでした。
いわゆる「ライトノベル」と呼ばれるジャンルになりますが、過労うつの者に優しかったのは、大手小説投稿サイトが、無料で読める作品をたくさん並べてくださっていたこと。一部で「書籍化するので掲載中止します」というようなものもありましたが、ほとんどは無料で読める、というのが魅力的でした(難点を挙げるなら、途中で更新が止まってしまった作品も結構多いというところでしょうか。続きが気になります)。
ちょうど「異世界への生まれ変わり」的な物語がブームになっていたのではないか、と思います。一度挫折したひとが、環境がかわり、本人が変わることで、大活躍しする物語の、まさに「主人公」である、という設定に、どこかで自分を投影していたことで、心のリハビリになったのだと思います。
さて。こうした物語では、異世界に入る時などに、すごい能力や才能みたいなものを貰うことで、大活躍するのですが、こういうすごい能力を「チート」と書いてあったりします。もともとの「チート」はズルというような意味のようです。ゲームなどで、ルールの隙をついて、極端な好成績を生み出す方法のことを言っていたのかと思います。
なので、物語の主人公が別にズルいことをしているわけではありませんし、古いライトノベルの記述だと「チートじみた」というような書き方がされていたりしたのではないか、とおもいますが、最近は、「ズルい」という意味が弱まったのか、そのまま「チート」と表記されることが増えたのかも知れません。
そんなことを考えたのは、ちょうど、乗った電車の車内広告で「ズルい」という表現をみかけたから、かもしれません。

「ズルいほどサポートが手厚い」というフレーズの広告でした。たしかに、こういうときに若い人は「ズルい」って使うような気がします。
我が家の話ですが、たまたま、なんらかの事情で家族のひとりに「良いこと」があった場合、それを他の家族が「ズルい」って言い方をすることがありました。
「それは『ズルい』じゃない。ちゃんと『うらやましい』っていう言葉があるのだから、そっちを使うようにしなさいね」と言い聞かせたものでした。
「ズルい」という言葉はとても強い言葉です。目を引きますし、わりと意味が伝わりやすい言葉でもあります。が、うっかり使っているうちに、使っているわたしの口が悪くなってしまうような、そんな怖さがあります。
仏教の教えの中に「不悪口」という戒律があります。「わるくち」ではなくて、荒い言葉を使わないように、という戒めなのだそうです。まさにこの「ズルい」という言葉は「悪口」に該当するのではないか、とわたしは考えます。
ちょっと話は変わりますが、漢方の生薬を、神農様が分類したと言われる本(『神農本草経』)があり、その中では生薬を上品、中品、下品、と分類して記述されています。
上品はどれだけ長いこと使っていても大丈夫な薬で、これを使っていると「神仙になれる」というようなことが書いてあります(一部神仙になる、ということで水銀なども混ざっていますので、鵜呑みにせずに注意が必要なのですが)。
逆に下品というのは、効果が劇的であるために、用法用量に注意が必要な薬です。「悪口」というのは、この下品の薬に近い作用があるのだろうと思います。
つまり「劇的に効果が出ることがあるけれど、使い方によっては人を傷つけるので、いつでもどこでも、誰にでも、というわけにはいかない」ということです。そして、使っている本人の徳を損ないますので、くれぐれも言葉にはご注意を。