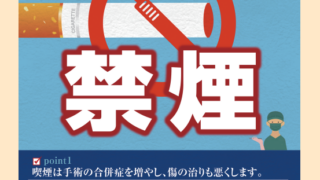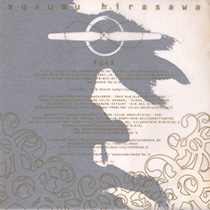当帰のはなし
漢方の話題を出すと、本当にマニアックになってしまうので…ということもあり、あまり漢方の話を書いてきませんでしたが、時々は、まっとうに漢方っぽい話をどっぷりしてみましょう。
漢方薬の中に「当帰」と呼ばれる生薬があります。「とうき」と読みます。

これを刻んだり、粉末にしたりして使います
有名な処方としては「当帰芍薬散」というのがあります。これは当帰と芍薬、という生薬を含む処方、ということになります。
他には「当帰湯」とか「当帰建中湯」「当帰四逆加呉茱萸生姜湯(長い…)」などの漢方処方の名前に挙げられています。「当帰飲子」ってのもありましたっけ。
この当帰、「血」に効く生薬として有名です。
なにしろ、この生薬の名前の由来のエピソードがあります。
それは、月経不順で、不調になった女性が、この生薬を用いて、月経が整った、という時に、「夫よ、まさに帰るべし!」と叫んだ、とか。あるいは妊娠しないために暇を言いつけられていた妻が、この生薬で体調を戻して「まさにわたしが帰るべきだ」と言った、とか。
はたまた、産後の不調にこれを使って「まさに帰るべし!」って言えるくらいに元気になった、なんて話もあるのだそうです。
多少バリエーションがありますが、まさに=当、帰るべし、ということで、「当帰」という名称になったのだ、と伝わっています。
そういう意味で、不妊とか、月経不順とか、産後とか、そういう女性のトラブルに対処するときに使う、そんな処方によく含まれている生薬です。
日本では「大和当帰」というのが有名で、大和…奈良県で栽培しています。
根っこを生薬として用いますので、採取してきて、土を除いた後、湯もみをします。
https://www3.pref.nara.jp/sangyo/yamatotouki/saibai
湯もみするのは、一年でも一番寒い、2月頃の作業になるようで、本当に大変なことをしていただいているのだなあ、と思います。
こうして大和当帰が生薬として用いられる形になります。
中国では唐当帰というのが使われていて、同じセリ科の植物でとてもよく似ているそうですが、微妙に異なるようです。また日本では「北海当帰」と呼ばれる別の品種も栽培されているようで、一応これらが「当帰」として用いられる植物になっています。
近年、植物としての大和当帰の葉っぱ部分を、食品として取り扱うことができるようになりました。スーパーフード扱いされていたりするのですが、葉っぱを採取すると、根の部分の育ちが悪くなるのだそうで、あっちもこっちも、というのは難しいようです。まあ、考えてみたら、当たり前のことなのでしょうけれど。
ちなみに大和当帰の植物としての学名(ラテン語名)はAngelica acutiloba Kitagawaアンジェリカ・アクチローバ・キタガワ、ということになっています。
ヨーロッパでは類縁のアンジェリカ(あるいはアンゼリカ。学名:Angelica archangelica )が「天使のハーブ」という名前で呼ばれ、不眠や消化不良、あるいは女性特有の症状に用いられることがあるようです。似たような成分が含まれているのだろうと思います。
そういえば、生薬名としては「トウキ(当帰)」であって、ラテン語では「Angelica Radix」としてあります。アンジェリカ種の植物の根っこ部分、という名称になります。
漢方薬系の話をすると「生薬の名前」と「生薬のもとになった植物:基原植物の名前」と、それから、「生薬を構成して作られた処方の名前」とがゴッチャになってきて、ついうっかりまぜこぜにしてしまうのですが…そういうところが話がややこしくなる原因になっているのかもしれません。
生薬の名前の由来が伝わっているものは他にもあります。けっこう面白いエピソードもありますので、また折を見てご紹介します。