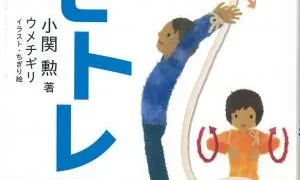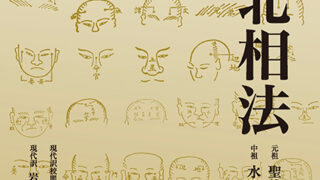待つこと・待たせること

そろそろ、大阪の万国博覧会も終幕が近づいてきました。今から慌てて「見に行きたい」と言っても、すでに入場予約が一杯なのだとか。
当初「並ばない万博」ということを謳い文句にしていたそうですが、イタリア館は6時間待ちだとか、なんとか…という話も聞きました。
ただし、これは「ほかのパビリオンが、あまり列が長いと待ち行列に並ぶこともお断りするのに対して、イタリア館は、並んででも見たい、という方には待って貰おう、というスタンスだから」という話もあるようです。どちらが良いのか、なかなか、悩ましいところです。
万博ほど大きなイベントではありませんでしたが、昔、子供向けの展示・体験のイベントを見に行ったことがありました。
参加無料だったのだと記憶しています。
体験ブースは全て「整理券」が必要だったのですが、わたしたちが入った時にはすでにほとんど全ての整理券が配布終了になっていました。
うーん。もうちょっと早い段階で来なければならなかったか…と思いつつ、しばらくうろついていると、1時間さきに、夕方の体験ブースの整理券配布があります!というアナウンスがありまして、慌てて並びました。ギリギリ、その定員に入ったのを覚えています。
会場に来る方はとてもたくさんいらっしゃって、本当に芋の子を洗うような人だかりだったのですが、体験ブースの中に入ると、ずいぶんとゆったりした時間の中で、それでも応対されているスタッフさんは人手不足気味、だいぶいろいろと混み合っている状態でした。
そもそものキャパシティと、ひとの集まりにバランスが取れていない…と、批判することは容易ですが、このあたり、バランスが取れるようにするのはとても難しいわけです。
そして、観光にしても、イベントにしても、お客さんがどのくらい来てくれるのか?というあたりは本当に未知数です。今回の万博も、最初は酷評されていましたし…。
数年前に新型コロナウイルスの感染症で、パンデミックとなり、観光などが激減した時がありました。タクシーの運転手さんにうかがったら、当時、売り上げが8割減とか、そういう話だったようです。
なかなか、続けていられない…と業界から離れることになった方もいらっしゃるようです。
自粛から一転、最近は京都市内も観光客がすごく増えて来ました。
別のタクシーの運転手の方が、「もう、お客さん降ろしたと思ったらすぐに次の方が乗ってこられる」ということを言っておられるのを読みました。
サービス、っていうのは、提供をする側と、提供をうける側と、が、ぴったり同時にニーズが満たされることは滅多にありません。どちらかが待つ必要があります。
そして、提供者側が「待っている暇もない」という状態であれば、それは、サービスの提供としては「足りていない」ないしはサービスを受ける側が待たされている、という状況になります。
このあたりのマッチングを、情報機器を駆使すればなんとかなる…と、ひょっとしたら、今回の万博をデザインされた方は、お考えだったのかもしれません。
現実には、情報機器で行う抽選の申し込みが殺到し、結局選に漏れるひとが大多数になった、ということでしょうか。
そういえば、ベトナムに観光に行ったとき、タクシーの呼び出しはスマホでやる形でした。お互いに情報機器でマッチングする…という形ですが、ちょうど年始だったこともあり、希望が集中すると、やはりなかなか呼んだタクシーもたどり着かない、ということが起こっていたようです。
情報機器だけでは、集中したニーズに対処することができない、ということなのでしょう。
…と、万博にことよせて書いてきましたが、「医療」も誰かが待つ、という形で物事が進む場所がけっこうあります。
日本の医療は、皆保険制度と、フリーアクセス制が謳われていますので、安いし、誰でも容易に受診できる、という形になっています。
ですので、世の中的には3時間待って3分診療…というような揶揄を受けることがしばしばあります。
それでも、受診を希望される方、みなさんに対応する、というのは、本当に大変なお仕事になります。
当院は、完全予約制にしておりますので、受診の日にお待たせすることはそれほど多くありませんが、その分、初診の予約が取りづらくなってきて、そちらでお待ちいただいていることもあるようです。
医師ひとりで回している小さな診療所です。何かとご不便をおかけしますが、ご理解とご協力を頂きたいところです。