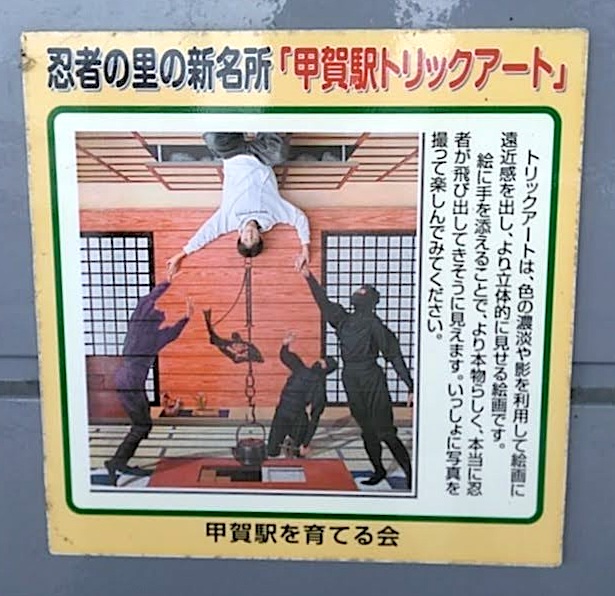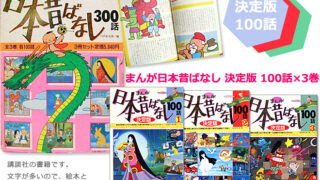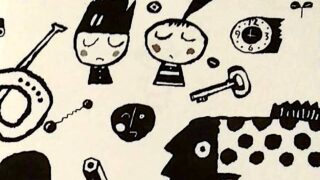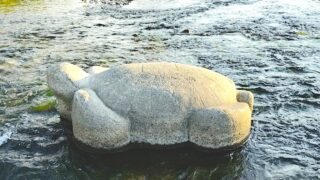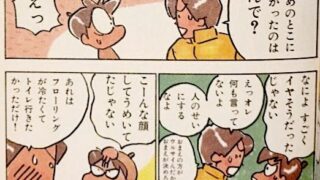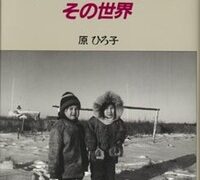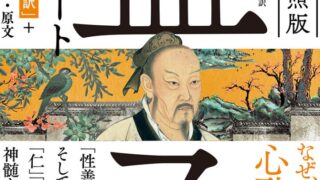文章の順番

このあいだ、中学生のこどもがふと「俳句の5・7・5、って、下の5と上の5を入れ替えたら倒置法表現になる?」と疑問を投げかけてきたので、手頃な俳句(と川柳)を探してきて、ためしてみることにしました。
古池や蛙飛びこむ水の音
→ みずのおと、かわずとびこむ、ふるいけや。
閑かさや岩にしみ入る蝉の声
→ せみのこえ、いわにしみいる、しずかさや。
おおお。わりといける感じがありますねえ。
五月雨をあつめて早し最上川
→ もがみがわ、あつめてはやし、さみだれを。
ちょっと無理があるかもしれません。俳句の区切れって、かならずしも「5・7・5」ではないんでしょうねえ。五月雨を集めて・だから、それをぶった切ると、変な倒置法表現になりそうです。
松島やああ松島や松島や
→ まつしまや、ああまつしまや、まつしまや
…これはまあ、最初からかわりませんが。
眼に青葉山ホトトギス初鰹
→ はつがつお、やまほととぎす、めにあおば。
…これも列挙ですから、あまり影響はなさそうです。
菜の花や月は東に日は西に
→ ひはにしに、つきはひがしに、なのはなや。
うーん。やっぱりちょっと違う。切れ字との関係があるのかもしれません。
雪とけて村いっぱいの子どもかな
→ こどもかな。むらいっぱいの。ゆきとけて
…だいぶ無理がありますねえ。
柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺
→ ほうりゅうじ、かねがなるなり。かきくえば。
意味は伝わりますが、雰囲気、だいぶ違いますよねえ。
言葉の語順、って大事な時は大事なんだなあ…と思ったのでした。
さて。
日常でもわたしたちは、言葉の順番を入れ替えます。
日本語は、てにをはが入って、それが文章の構成を決定していますので、まあ、語順はあまり気にしない…ということになっています。
「あのひとは優しいけれどケチだ」
「あのひとはケチだけれどやさしい」
似たような文章ですが、順序を入れ替えた「あのひと」どちらが好ましいでしょうか。
「今日は良い日だったけれど、ひどい目にあった」
「今日はひどい目にあったけれど、良い日だった」
どちらの「今日」の方がよい日だったでしょうか。
ヒトの感覚っていうのも、けっこういい加減なところがあって、何かの経験をどのように意味づけるか?というところで、その経験の最後の数分が効いてくる、みたいな研究がありました。
日本語では文章の最後に意味が決まります。英語では最初に主語と動詞が来ますが、日本語の動詞はいちばん最後に来ますので、文章の意味がギリギリ最後でひっくり返ったりすることがあります。
昭和の時代には、手旗信号のゲームがあって「赤挙げ…ないで、白挙げ…ない」なんていう意地悪があったりもしました。
最後まで聞き取らねば意味が決定しない、というのもまた面倒くさい文章構造ですよねえ。我が家も「今日はご飯食べるの?」っていう質問に「食べ…」ってボソボソと答えるひとが居ました。肝腎な最後が聞き取れないと、用事がぜんぜん済みませんけれど。
そういう日本語を使っている世界では、やっぱり、「ケチだけれど、やさしい」というひとの方が望ましいひとなのだろうと思います。
文章を、肯定的な意味の言葉で締めくくるのが良いのかもしれません。
たいてい、それをやらないような方は「でも」「だって」「どうせ」をお使いになります。
文章を肯定的な意味の言葉で締めくくってくださいね。
「わかりました。でも…」
だから、そこの部分の「でも」のあとに、もう一度「わかりました」って入れてくださいね。
「わかりました。でもだって…」
以前も書きましたが、3D、禁止してくださいね。
毎日を「今日は良い日だった」と締めくくることをやっていると、うっかり無意識がそれのつじつまをあわせるように、良い日にしてゆくことが起こるのだそうです。
どうぞ今日も良い日でありますように。