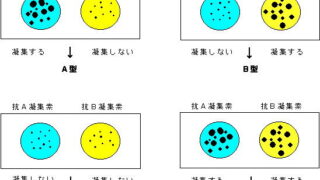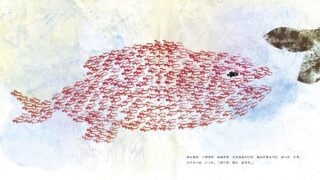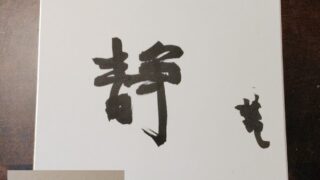植物とヒトとの不思議な関係
暑い日が続いています。こういう暑い時期は、水分をたくさん含んだ野菜を摂るのがお薦めです。たとえば、キュウリとか、ナスとか。
夏の季節野菜は、身体を冷やしてくれるような働きをもったものが多くあります。
その土地で育つ作物が、その土地の気候にあっているのだ、という話を聞いたことがありますか?
「四里四方(しりしほう)」などという表現で、地元の作物を地元で消費するのが良い、とされています。
そういえば、ジンギスカンに供されるヒツジ肉って、結構身体を温める力が強い、という話もあります。
やっぱり北海道なんかの寒いところで育つ食物は、身体を温める作用がある、ということなんでしょうか。
しかし…と不思議に思います。どうして、植物は、ヒトとの共生を選んだのでしょうか?
いや、必ずしもヒトだけではありませんけれど。
昔『植物になりたかった虫』という写真絵本を読んだことがありますが、表紙が蘭の花に擬態するカマキリの一種でした。
ハナカマキリ、と呼ばれる種らしいです。

https://www.ecochil.net/article/4416 から画像をお借りしました。
進化論的な話によると、植物もその形を変えて、進化して来ているのですが、それにあわせるような形で、昆虫…やヒトのような動物も進化してきている、ということでしょうか?
栽培する植物…農作物について考えるなら、地元で取れた作物を継続的に食べてると体調が悪くなる、という話では困ります。なので、体調が悪くならない、というのはとても大事なことです。そういう意味では、栽培するヒトが、好ましいものを栽培する、という形での選別はかかっているのでしょう。
そういえば、薬用植物園の見学に行った時に、瓜の仲間で、「これは食べると下痢するからね!」と言われたものがあったように記憶しています。見た目はしっかりみずみずしいのですが、そういう植物は、農産物にはならない、ということなのでしょう。とはいえ、そういうものばかりではなく、やっぱり夏の作物は、夏の身体を整えてくれる、というのは不思議なことだと思います。
いちばん不思議な作物が、穀物です。
植物は、自分たちでタネを遠くに拡げようとする働きを持っている…はずなのです。たとえばタンポポの綿毛などを見ると、風に乗って、遠くに移動する性質を上手に反映させています。

ところが、コムギもイネも、あるいはトウモロコシなんかも、タネ…である「実」の部分をあちこちにこぼすような稔り方をしません。
むしろ、きれいにまとまって、こぼれないようになっているわけです。自力で繁栄することを諦めて、ヒトの手を介して増える、という選択をしたようにさえ見受けられます。
もちろん、ヒトがそのような形で奇妙に変化したものを選び取った、という面も大きいのだと思いますが、やっぱり植物…というか、食べ物とヒトとの関係って、興味深いことがあるんだなあ、と思います。
じゃあ、漢方薬も地元で取れたものだけで!って言いたくなるのですが、なかなか、こちらはそうも言ってられないことが結構あります。
どうしても薬効を発揮できるように育つ環境が、日本国内では準備できない、とか、大量の土地が必要になる、とか。
遠くからはるばる運んできた生薬が、別の土地に住んでいるヒトに有効である、と判断するのも、なかなか難しいところですが、これはこれで、不思議なことだと思います。