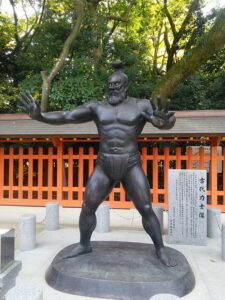治療の理論

先日、とある診療の勉強会に参加したら、講師の先生の言葉がずいぶんと刺さりましたので、ちょっとここに書いておきます。
相変わらず、こういう引用は、にしむらのうろ覚え再現、なので、細かいニュアンスはぜんぜん違っていたりするのですが。
中医学では「弁証論治」と言います。
まずは、患者さんの訴えであったり、あるいは四診(望診・問診・聞診・切診)を用いて、患者さんの所見をとり、それらを総合して「証」を立てるわけです。そしてこの「証」に応じた治療を考えます。
そういう大きな流れの中に、時々は「病名に対して処方する」という手段が選ばれることも、あるかもしれないけれど、基本的には、ちゃんと、それが証に応じた治療の1つであるように、考えてゆくのが必要です。
漢方の診療で「病名処方」と言われる診療のスタイルがあります。
基本的な話をすると、医療用の漢方エキス製剤は、それぞれ適応病名があります。その病名がついていない患者さんに保険診療として処方するわけにはいきません。そういう意味合いでは、現在、医療保険のルールに則って医療用の漢方エキス製剤を処方している診療スタイルは、病名に対して処方している、ということになりますので、「病名処方」と言える部分もあります。
ただし、同じ病名に対して有効、とされている処方であっても、それぞれ異なることがあります。
そういう差異を考慮せずに、西洋医学の病名に当てはめて「この病名だったら、これ一択」という形で処方するスタイルのことを「病名処方」と呼ぶのかもしれません。
たとえば「こむらがえりには芍薬甘草湯」というのは、わりと有名な話です。
芍薬甘草湯、本当によく効くんです。しかも、内服したらかなりすぐに。とっても良い処方薬です。
とはいえ「こむらがえり」という「病名」に、「芍薬甘草湯」という処方を、必ず当てはめる、というのは、実はいろいろと問題が出てくる場合があります。
もともと、この処方は、急場をしのぐための処方です。なので、急場をしのいでから、その先、やっぱりこむらがえりが繰り返される状態が続いているなら、ちゃんと別の弁証をして、体質的なこむらがえりを予防できるような処方を選択し、芍薬甘草湯を使わなくてもよい状態を作ってゆかねばなりません。
「めまいに五苓散」あるいは「めまいに苓桂朮甘湯」というのも、それに近いものがあるように感じます。
どちらもめまいに有効なことがあります。また、大変ありがたいことに、これらの処方は、ストライクゾーンが広く、けっこういろいろな方が内服しておられます。五苓散などは、内服することで、困ったことが起こる、ということはかなり少ないので、まずお試しで使っていただく、というのも、ありなんだろうなあ、と思います。
とはいえ、きっちり中医学とか漢方の理論をおさえておかなければ、次の段階に進むのが難しいわけです。
最初の一手はそれで良いのかもしれませんが、漢方の専門家は、次の次、くらいまで考えねばならないわけです。そのあたりを、ちゃんと弁証しておかねば、狙いがはずれた、という結果が返ってきた時に、次にどうするのか?ということを考えて組み立てることが出来なくなります。
…とは言うものの、わたしもそんなに格好良くはいきません。
理詰めだけで診療が進んでいるとは言いがたいのが現実です。
ただ、ちゃんと「自分はこう見立てた」ということを残しておくことで、効果が思ったように得られない時には反省する、ということができるようになります。
思ったように効果が発揮されない、という時には、考えることがいくつかあります。
そもそも、見立てが患者さんの状態に沿っていたのかどうか。
見立てから弁証し、治法を論じるわけですが、その理屈がきっちり通っていたのかどうか。
そして、治療の方向性があっていたと仮定したときに、その治療の効力は十分だったのかどうか。
このうち、弁証と治法との理屈の部分は、完全な座学です。しっかり勉強せねばなりません。
治療の力が足りない時は、これは頑張ることになります。あるいは、ご本人の自覚は今ひとつであっても、身体の所見として、やや改善、という状態になっておられる場合がありますので、そういうときには「もう少しこのまま頑張ってみましょう」とお伝えすることになります。
問題は「見立てが違っていた場合」です。
この「見立てが違っていた」というのにも、いろいろな種類があるように思います。
つまり、症状を引き起こす要素は複数あって、「これが大きな要因だ」と思っていたけれど、もっと大きな要因が別のところにあった、とかいう場合です。
これも時々あることなのですが、「夜に頻繁にトイレに起きる」とおっしゃる方があります。病名的には「夜間頻尿」というようなものが、ここには適用されることがあります。
とはいえ、よくよくお尋ねすると「目が覚めるので、念の為に…とトイレに行く」という方と、「トイレに行きたくて目が覚める」という方がいらっしゃいます。
前者は、尿の問題よりは、眠りが浅い、というところに問題がありそうです。
後者は、尿の問題…となるのですが、こちらも、また別の事情が隠れていることもあります。
尿が多い、というと、「冷えているから」と考えてしまうこともありますが、逆に「のぼせていて、口がすごく渇くので、水分の摂取量が多くなってしまって…」という場合もあります。
意外とそういう方の場合、温める治療ではなくて、冷やす治療が有効だったりします。
そんなことを考えながら、診療をしています。いらしてくださる方のおかげで、毎日勉強になっております。
なかなか、皆さんの症状をスパッと、あっという間に解決!とはいきませんので、その分、いろいろと試行錯誤にお付き合い頂いていることもしばしばです。
どうか、今しばらく、お付き合いをお願いいたします。