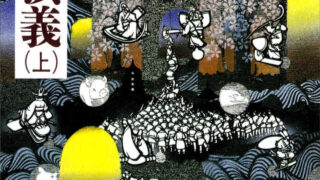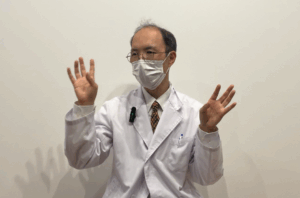漢方薬の効き方

漢方薬は穏やかに効く、って、そんなイメージをお持ちの方も結構あると思います。
江戸時代では、漢方医…というか、まあ、当時のお医者さんは、自称すれば誰でも医者になれる時代でした。ヤブ医者と呼ばれるのは「ちょっとしたかぜでもがさがさと大騒ぎするから」と落語などでは説明していますが、そんな「自称お医者」がそれなりにいらっしゃったのかもしれません。
(なお、ヤブの語源を大きな辞書で調べたところ、語源はどうやら「野巫」らしいということで、これは、政府が認めた巫…かんなぎ…とは違う、野良のかんなぎ、という意味なのだそうです。つまり野良育ちの医者がヤブ医者…あれ?わたしのこと?)
養父市(やぶし)という地域がありますが、こちらの地域では「やぶ医者」を名医のこととして、表彰する制度があったりします。これもまたとても面白い取り組みだなあ、と思います。
https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kenkofukushi/kenkoiryo/1_4/index.html
話が脱線しました。江戸のお医者さんを題材にした落語はけっこういろいろとあります。「葛根湯医者」なんていうのも有名な落語ですが、このセンセ、誰にでも「葛根湯をお上がり」と言う。しまいには付き添いでやってきた方にまで「葛根湯をお上がり」なんて言い出す、というオチになっています。
葛根湯は、とても使用範囲の広い処方であることは確かです。3世紀ころの医学書である『傷寒論』にも載っていて、首が凝っていて、汗がでていないような風邪に使う、ということが書いてありますが、ここから、「肩こり」に使ったり、あるいは、汗腺を開く、という意味合いで、乳腺炎に使ったり、というようなこともあります。
さすがに付き添いの方に…っていうのはやり過ぎ…なのかもしれませんが、実はこの付き添いの方に、すごく肩こりがあったのを見抜いた、なんていう裏話があるのかもしれません。
漢方薬の中には、このように、わりと幅広く効果を発揮するものと、それから、峻烈な効果を発揮し、上手に使わないと悪影響が出てくる、というものがあります。
ちなみに、現在の日本で、医療用エキス製剤に収載されているおよそ140種類の処方は、どちらかというと、「幅広く効果を発揮する」タイプに分類される処方が多いようにも見受けられます。
キツい効き方をする処方ってどんなのがあるの?って思われるかもしれません。
江戸時代のお医者さんは、あまり治療の効果をあげられなかった、という話がけっこう残っていますが、そんな医者が、呪術師と「技比べ」をした、という話があります。これまた物騒な話ですが、呪術師もどちらかというと、腕の悪い医者と並ぶ、くらいにどっこいどっこいだったのでしょう。
この時は、漢方医が、呪術師に「あなたは私を呪い殺してください。私はこれをあなたに処方しますから飲んでくださいね」という形で、激烈な効き目の下剤を処方したのだ、という話になっています。
お腹を壊して、雪隠に出たり入ったりを繰り返した呪術師が音を上げて降参した、という話が伝わっています。
『傷寒論』には、「近頃の医者は、なにかあるとすぐ下剤を使いたがるが、それで治るわけでないものがけっこうあるから、注意が必要で、こういう処方が良い」というような文章があります。もともと3世紀くらいの本、らしいですから、本当に古くから下剤、というのは治療薬として用いられていたのでしょう。
ゴリラだったか、チンパンジーだったかが、群れの体調不良の個体に持っていったお花が、下剤作用があることが知られていて、彼らが薬草のようにそれを使っているのではないか、という話もありました。
他には「吐法」といって、胃の中のものを出してしまうような方法もあったのだそうですが、吐くのも、吐かせるのも、どちらもなかなか大変です。こうした処方は、今はほとんど用いられなくなりました。
…と、書いていて思い出しました。むかし、犬を飼っていました。散歩に連れて行くと、空き地の草を食べていたのでした。犬って草食…?とは思いませんでしたが、その後、「ツンツンする草を食べて、胃の中を刺激し、吐くことで体調を整えるのだ」というような解説をどこかで読みました。犬も吐法を使う…。ってことは、薬については、ヒトだけの専売特許とも言えない…?のでしょうかしら?
まあ、吐法にせよ、下剤にせよ、激烈な効果を発揮する生薬は、やはり劇薬になります。なかなか使いどころを選ぶわけですが、西洋医学が発達して、手術や、抗菌薬などが普及すると、必ずしもこうした激烈な処方がその効果を発揮する場面は減ってきたと言えるのかも知れません。