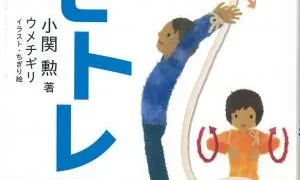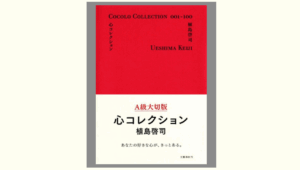白か黒か
わたしは、ネット小説をちょこちょこ読んでいるのですが、ネット小説の界隈で、一時期、異世界転生の物語が流行ったときがありました。異世界転生っていうのは、地球(あるいは日本)で生きていた時の記憶を持ったままで、ファンタジー要素(たとえば、魔法が使えるなど)の強い世界に生まれ変わる、という枠組みを持った形の、ひとつのジャンルを形成しているのかもしれません。
界隈の流行も少し変動があるのですが、当初はこの転生先に「リバーシ」を売り込んで大もうけする、というのが、資金調達の方法になっていました。
最近は「前任の転生者がすでにリバーシを持ち込んでいて…」という話になりつつあります。異世界も含めて、世の中いろいろと世知辛い時代になってきたのかも知れません。
リバーシ、って言いますけれど、もともとは「オセロ」というゲームがあったんですよねえ。あれ、日本人が発案したのだ、と聞いています。


8マスかける8マスの盤面に、白と黒のコマを置いて、挟んだ相手のコマをひっくり返して、自分の色に変えてゆく、というのがゲームの大枠です。
一時期、うちの子どもがそこそこ強く…家族でやっても誰も勝てなくなり、お店の大会に参加したことがありました。結果としては、あっという間に角を取られ、初戦敗退したのですが、強い方は本当に強いんだなあ…と、唖然として見ていたのを覚えています。
オセロの話でとても面白いのは、うまいこと挟むことができると、あっという間に白黒が反転する場合がある、というところです。
満を持して、エイヤッとひっくり返す、なんていう場面にあたると、けっこうカタルシスがあります。
ところで、オセロのコマは「白か黒か」みたいな形で、ハッキリと分かれています。
こういう事象を「離散的」と呼びます。
が、実際の世界は、このようにハッキリと分かれているものばかりではありません。なんとなく濃いグレーだったり、すこし明るい色だったり。真っ白…でもなくてややグレーかかっていたり。そのような形で、分別が難しいのが現実世界です。
わたしたちは、絵を描くときに、輪郭線を描くことが多いのですが、実世界には「輪郭線」に該当するような存在はありません。それでも、ひとの目は輪郭を大事に感じているようで、コピー機なんかは、輪郭を強調するような調整がされています(平成初期のコピーは、繰り返すと、輪郭だけが残り、ベタ黒が抜けていく、なんていうことがありました)。コピーガードなどは、その特徴を上手に使って、コピーすると、「複写」という文字などが浮かび上がるように設計されています。
実生活の中にある、連続的な変化のどこに線を引くのか?という話は、常に葛藤をもたらします。わずかだけ、線をこちらに引くわけにはいかないの?っていう話を重ねていると、気づけば線の位置が真ん中から、ずいぶんと端に寄ってしまったりすることだって起こりかねません。
「ここが真ん中」という位置取りが難しいからこそ、「中庸」という思想が、どう実践していくのか?という智慧とともに残ったのでしょう。
ゼロか100か、あるいは白か黒か、という考え方は、こうした連続的な変化をいったん見ないで済ませる、という意味では、とても強い影響を持つ考え方です。
そして、脳のクセとして、そのような考え方を好む傾向があります。
が、現実問題としては、こうした極端な話は、実は少なくて、どこかで交渉し、落とし所を、中間のどこかに決める、ということがほとんどなのかもしれません。しかも、いったん決めた線が、永久に続くのではなくて、状況によって刻々と変化している、というような、動きを伴う線なのではないでしょうか。
こうした、揺れ続ける中で、毎回少し異なる変化、というものは、頭に負担がかかります。できることなら、白黒ハッキリつけたい。とはいえ、白黒をハッキリさせずに、このまま揺れ続けることが大事なことも、場合によってはあります。
体調の変化も、「元気」と「不調」のあいだの連続的な変化があって、どこからが不調と呼ぶのか、みたいなところで悩ましい、というものではないでしょうか。
また、元気になってゆく、ということだって、「完全に不調が無くなる」ところだけではなくて、プロセスとして、強い不調の状況から、元気な方向に少しずつ動いている、という状況を呼ぶ、ということも考えられます。
そのような形で、変化や変動を味わっていただけたら、と思うところです。