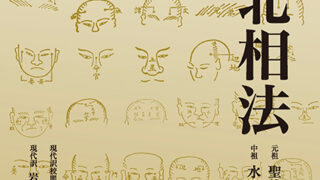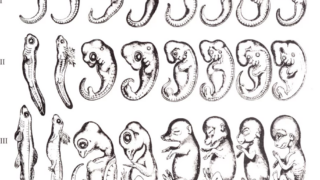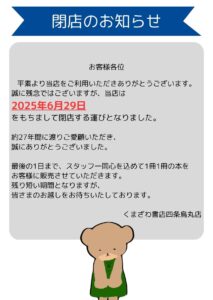科学と倫理

日本にアドラー心理学を導入した、野田俊作氏は、かれの日記「野田俊作の補正項」の中で、しばしば「科学には(善悪の)価値判断基準は無い」ということを指摘する記述をされていました。
たとえば
https://adlerguild.sakura.ne.jp/diary/2015/12/18.html
では、
現代のわれわれが抱えている問題のひとつは、理性の知(≒科学)が「普遍的」な知であり、しかも神の意図につながるものであるという迷信に、多くの人が凝り固まっていることにある。そうして、個々の問題を理性の知でもって価値判断しようとするわけだが、マックス・ウェーバーが指摘しているように、理性の知である科学が価値の領域に手を出すのは、越権行為であって、理性の知の本来の定義域を超えたことをしようとしている。
中世には、理性は現世的なこと(=科学的な真理)は知りうるが、超越的なこと(=宗教的な真理)は知りえないことになっていたし、それはいまでもそうなのだと、マックス・ウェーバーは言っている。およそ価値の問題は超越的な問題であり、理性が解答を出すことはできない問題なのだ。
として、価値判断は、科学以前にある「超越的」な問題だと指摘しています。
「べし」「べからず」というのは、価値判断ですから、これは科学を超えた場所にある。
ついつい、「科学的に正しい」云々という言い方をしたくなる部分がありますが、「科学的に正しい」ということが「善」であるとは言っていないわけです。
そういえば、昔イギリスに語学研修に行っていた時に、イタリア人のグループと接することがありました。
その中の一人が、かなり英語文法的には正しくない表現を使っていたので、「キミの英語は文法的に正しくない」と、(同時にそれはイタリア人グループの別のひとりも似たようなことを言ってくれたのですが)指摘したら、彼は「いいんだ。俺は文法的に喋っていないんだから」と返答しました。
語学研修の中では、たぶん、文法的に正しい表現を選ぶこと、文法的に正しい表現に慣れていくことが推奨されるのでしょう。が、「文法的に喋っていないんだ」って気持ちよく否定する、という道もあるのだなあ、と、思いのほか清々しくその言葉を聞いたのでした。
もちろん、科学的な知見が、倫理的行動を裏付ける、ということがあっても良いわけです。
たとえば、自己犠牲を発揮する個体が多い集団は、集団として繁栄する可能性が高い、みたいな研究結果が出ることだってあるかもしれません。そうなれば、自己犠牲を発揮することは、集団繁栄のためには良いことである、という価値を強化するかもしれません。
もちろん、こうした発見が価値を後押しする、という場合には、その手前に「集団が繁栄することは良いことである」という、無根拠で超越的な価値観があるわけです。
野田氏は、アドラー心理学を極力「科学的」に呈示することを心がけていたようですが、アドラー心理学の中にある「共同体感覚」というものについては、「科学的」な枠組みの中ではその根拠を呈示することが出来なかった、としているようです。
倫理とは、どこかで、科学を超えた価値基準が優先するのだろうと思います。
科学だから「善い」とか、あるいは非科学だから「悪い」というようなことはありませんし、逆に、非科学だから「善い」、あるいは科学だから「悪い」ということもありません。
科学の出来ることと、科学の語り得ないことがある、それだけのことです。
そして、非科学であれば語り得ることもある、ということでしょう。
ただし、非科学の語りは、科学によって「正しいとも正しくないとも言えない」というものと、「科学的にはだんぜん正しくない」というものがあり得ます。
前者の中でも、なんらかの形での検証が必要な話も多いわけですから、こうした非科学の語りが、不用意にひとを傷つけないようにしなくてはなりません。