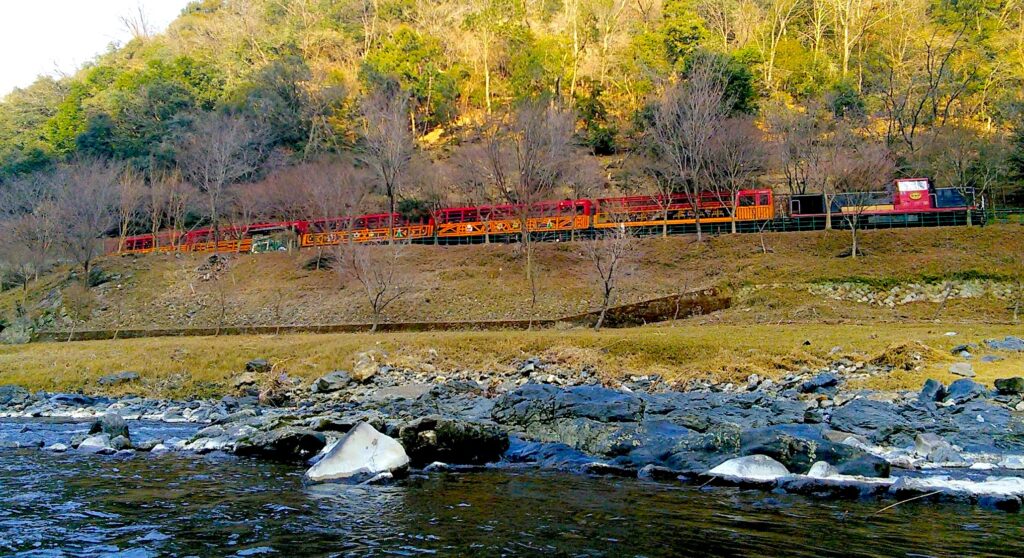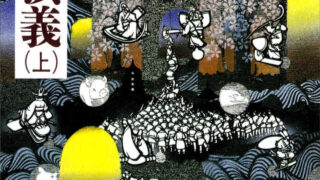筋肉の地層

ひとさまの身体に触れるようになったのは、わたしが医学部を目指すきっかけでした。
肩こり…そして、いわゆる五十肩というものには、医者としての人生よりも長く触れてきました。
最初に本格的に学んだのは、師匠の背中からでした。比喩表現ではなくて、実際に師匠が、「ごろん」とうつ伏せになって「じゃ、やってくれ」ってところから始まったので…。
センセ、これ何ですか?って、いろいろ聞きながらあちこち触れていたのが、一番のはじまりでした。師匠もあまり多くを語るひとではなかったので、「うーん…それは肝臓かなあ…」とか「うーん…それは腎臓かなあ…」とか、なんだかボンヤリしたお返事をいただいていたのでした。
ヒマにあかせて、かなり長いこと、背中を揉んでいたのですが、いちど終わった、と思っていたところに戻ると、なにかシコリが残っている…というか、さっきまで無かったところにシコリを見つける、ということもありました。
なんだか、地層みたいなものなのだろうか…?と思った記憶があります。
ずいぶん最近になって、腹部の打鍼というのを学びました。木槌でトントンとするやつです。これの講習会の時に、講師の先生が、「いったんトントンして、お腹が落ち着くでしょ。で、もうちょっとやっていると、また出てくるからね。良いところで区切りをつけてね…」という話をされていて、おおお。お腹にも地層があるのか!と感動的でした。
ひとつ、いま出ている層を整理すると、その奥から、別の層が出てくることがあります。
薄紙を剥がしていくように、ひとつひとつ、それを取っていくと、一番奥に、何かつよいシコリが残っていることもありますし、そんなことも無いまま消えてゆくこともあります。
解剖学的な筋肉の層とは違った形の、地層のようなものだと、わたしは感じています。
そして、たいていの場合は、奥にあるものの方が古いようです。最近の症状を解決してゆくと、その奥に、古いものが出てくる、そんな気がします。
二人目の師匠は、わりと細かく、丁寧に教えてくれるひとでした。
身体への触れ方とか、あるいは、見方、整理調整のやり方は、この二人目の師匠に習い覚えたことが多いように思います。
背中から診て、あとでお腹…というスタイルはこの二人目の師匠から習ったことでした。この師匠のお腹の見方は、中級指導者になるところで教えてくれる…という話でしたが、そこまでたどり着かずじまいでした。
なので、お腹への触れ方と、調整の仕方は、その後に学んだ打鍼とか、あるいは按腹とかの組み合わせでやっています。
少しずつ、手の感覚が上等になってきたからか、最近はお腹の奥の方の様子をうかがえるようにもなってきました。
腸腰筋はお腹…というよりは腰の部分にあるのですが、お腹側からの方が触れやすい場所です(腸腰筋に触れる、と言いますが、指が触れているのはあくまでもお腹の皮膚、あるいはそのお腹を覆う服です。とはいえ、奥にそのようなものを感じることは可能なのだと思います)。
また、シコリの固さによっても、蓄積された年月を想像することができます。最近できた、強い緊張と、長年の積み重ねで残った、かたいシコリとはやはり、雰囲気が違いますし、実際に緩まるまでの手間も後者の方がかかる、という印象があります。
考古学のフィールドワークをしていると、発掘調査している層の遺跡の、さらに下に、もうひとつ古い遺跡が残っていることもあるのだそうです。
ひとの身体にも、同じような形で、遺跡…ではありませんが、そのひとの人生の軌跡が、残っている、そんな気がします。