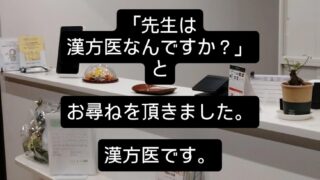耳鳴の話

どこかで書いていた…と勝手に思い込んでいたのですけれど、みみなりの話。書いていませんでした。今さらですが、書いておきます。
耳鳴のことは、まずは耳鼻科で相談してください。緊急で対応が必要な病態、というのも結構あるそうですので、特に急に発症した耳鳴については、早急な受診をお薦めします。
わたしがこれから書く話は、慢性化していて、気にし始めるとどんどん大きくなる、というタイプのものの話、です。
わたしも教科書で学んだわけではなくて、どこかのラジオ放送だったか、テレビの話だったか、ということで、その情報源もうろ覚えなのですが、耳鳴というのは「補充現象」だ、と聞いたのです。
補充現象?って言われても分からないですよねえ。
ちょっと順番に話をしてみましょう。
まず、一般に音っていうのは、空気の振動です。これを、耳の奥にある「蝸牛」と呼ばれる場所で、神経の電気信号に変換する細胞がいます(網膜細胞が、光を神経信号に変換するのと似たような話です)。残念ながら、網膜細胞もそうですが、この蝸牛の「有毛細胞」と呼ばれる細胞も、一度壊れると再生しません。今は再生医学の研究も頑張っておられますから、そのうち再生する話になるのかもしれませんが…今のところは再生しない、と思っておいてください。
年齢が重なると、この有毛細胞が減っていきます。大きな音に長時間さらされる、などの事があったりすると、もっと早くに進むこともあるようです。こういう形で、音…空気の振動を、神経の信号に変えられなくなるのがひどくなると「感音性難聴」という状態になります。この「感音性難聴」の一歩手前あたりに耳鳴っていうのはあるような話のようです。
有毛細胞が神経の信号を脳に伝えて、脳の中の、音を認識する部分までの間に、この神経信号を中継する細胞がいます。この細胞は単に信号を中継するだけではなくて、意識が向けられた音のボリュームを大きくする、という働きがあります。
カクテルパーティー効果、という表現を聞かれたことがあるかもしれません。カクテルパーティのような、大人数がガヤガヤとおしゃべりしているような場所で、でも、聞きたい話はしっかり聞き取れる、というのは、この中継細胞が、意識を向けた音のボリュームをあげて、しっかり拾ってくれるから、なのだそうです。
ところで、きっと、この中継細胞と、有毛細胞は1対1でつながっているのだと思いますが、有毛細胞が先に減っていきます。有毛細胞がいなくなった「中継細胞」は、仕事がなくなります。いつまで経っても、上流の有毛細胞からは信号が伝わってきません。
で、どうするか?というと、自分が担当していた「音」を再現するのだと思います。
つまり、信号は(今は)伝わって来ていないけれど、きっと、多少は何らかの音があるに違いない。なので、その「かすかに有るか無いか分からない程度の音信号だけれど、それを増強するのだ」ってことにしている、ということなんじゃないか、と思うのです。
そして、それが気になるってことは、意識が向くわけで、意識が向いてくると、中継細胞はこの音を増幅します。
これが(慢性的で、特に健康上問題の無い)耳鳴が鳴り続けている仕組みのようです。
なので、いちばん良い対策は「聞こえている耳鳴をなるべく意識しないようにする」ということです。とはいえ、これを意識するな、と言われるほどに意識してしまいがちになるわけで…。なかなか難しいところです。
「耳鳴 原因」あたりで検索かけるといろいろ耳鼻科の先生が書いておられる文章が出てくるのですが…たとえばこちら。
漢方診療の話では、耳の問題は、腎が弱ると出てくる、とされています。そういえば、腎臓の形と耳の形、似ています…似ているって話だけで進められるかどうかはおいておきますが、腎の気を補う、つまり補腎をすると、耳鳴が多少なりマシになることもあるようです。鍼をつかったり、漢方薬をつかったり、という方法があります。完全に耳鳴りが消える、というわけではないのですが、あまり気にならなくなる、程度に改善することもあるようです。
いちばんは「気にしないこと」なんですけれど、これが難しいんですよねえ。