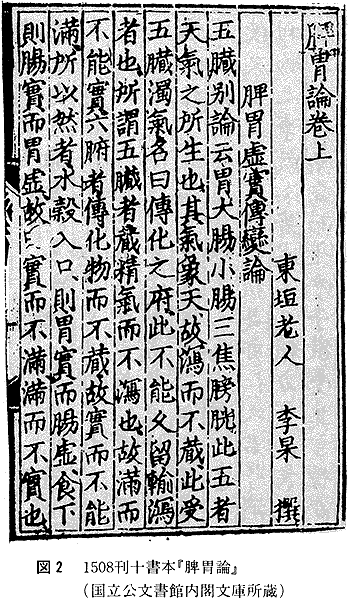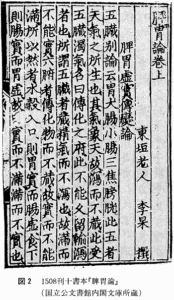肝腎要

かんじんかなめ、と書いて変換したら「肝心要」というのがでてきました。最近は「肝心な」という方が一般的な表現になりつつあるようです。
わたしの漢方の師匠は「肝腎」という話を結構してくれました。肝心じゃなくて、肝腎。「腎」が入るのです。
肝臓と腎臓が大事なのだよ、というのが師匠の説で、そのために…と「孔雀湯」という漢方薬を調合していたのでした。
(2011年の原発事故以降、師匠が満足いく生薬が入手できなくなったとして、孔雀湯の調合はなさっておられません)
昨日は「胃腸が大事」と言ったところです。
その舌の根も乾かぬうちに「肝腎が大事」って書いて良いのか、って思いますよねえ。
そのうち、「呼吸が大事」とか、「思考が大事」とかも言い始めると、結局、全部大事って言ってるんじゃねえの!ってなりそうです。
じっさい、全部大事、なんだろうと思いますけれど。
なんというか、大事の重み付けが違う、と言ったら良いのでしょうかしら。胃腸は大事です。はい。
肝臓…と、師匠が言った時、それは、五臓の「肝」だったのか、どうか、というのは、今ひとつハッキリしません。
わたしがボンヤリとしか聞いていなかったからだと思います。ふわふわと話を聞いて、ふわふわと分かったような気になって、というのを繰り返していたように思います。
そういうふんわりした理解、って大事だと思うのです。もう一人の師匠も「ふんわりと・すっきりと・しっとりと」と理解の三段階のことを言っていました。
ええと、肝臓の話でした。西洋医学的な話をすると、ここは、身体の中でも化学反応を行う「工場」みたいな場所です。
なので、身体に不要なものも、有害なものも、ここに持ってきて分解し、無害なもの・身体の外に出してゆける形に変化してゆく、なんていうことをやるわけです。
そして、腎臓。腎臓は、尿の形で不要なもの、悪いものを外に出してゆく場所です。
漢方の師匠は、それらが合わさることで、身体の中から悪いものを無害なものに変化させたり、外に出したりしてゆく、というところを「大事だ」と睨んでいたのでしょう。
胃腸の、いわゆる「食べること」が大事という前提は、その前段階として、当たり前、だったのかもしれません。
そういえば、健啖家だったように思います。
このあたり、いろいろな方が健康法などがありますが、提唱者ご自身が「当たり前」に思っておられる部分は当然の前提になっていて、わざわざおっしゃらない、ということもありそうです。
師匠は、こうも言っていました。
「薪ストーブの火が強くなって、どんどんと燃やせるようになったら、少しくらい湿気た薪でも火がついて、燃えてゆく。ひとの身体も、元気になれば、少しくらいの「悪いもの」でも燃やすことが出来るようになる」
だから、多少、「不健康なもの」を摂ったとしても、それが大きく悪さをすることはない、そんな身体にしてゆきましょう、という話だったように思います。
そのためには、やはり、元気になってゆくことが大事なのだと思います。
そして、元気になった状態で、元気なまま死ぬのが良いのだ、とも言っていました。
それが彼岸にわたるために必要なエネルギーになるのだ…というようなことだったと思います。
まあ、彼岸にわたるのに必要なエネルギーみたいな話はともかくとして、肝腎要。大事にしていただきたいところです。