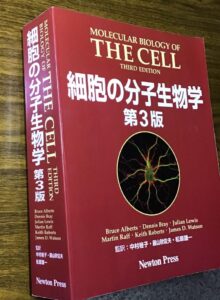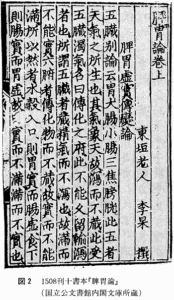臨床と基礎

昨日に引き続き、医学部教育の思い出を少し。
基礎医学は「ヒトの身体はどのように成立しているのか」というあたりのことを、わりと理論的に追いかける、というようなことをやっていた、のだろうと思います。
現実的には、生化学反応を全て網羅し、ひとりで研究する、などということは到底不可能ですから、その中のごくごく一部の研究、ということになります。
とはいえ、多分に思弁的になります。もちろん、実験自体は、手を動かし、結果を見るわけですが…。
比べて、臨の学問は、いきなり病気のひとや怪我をしたひとがあらわれます。
ヒトの身体がどうなっているか…?みたいな話は、現場ではあまり細かくは追求されません。とりあえず目の前に居る方の心臓がちゃんと動いている、とか、出血をなんとか止める、とか、そういう話が大事になってきます。
昨日書いたような、レベル学習…?そんなの、何の役に立つの?っていうのが、現場の声、だったりすることもしばしばあります。
医学そのものが、「目の前に居る患者さんをどうしたらよいのか?」から始まった学問だと考えるなら、いちばん最初に「基礎医学」があったわけではなくて、いろいろ考えはじめた結果、細かい方向に学問が進んで、「基礎医学」が出来た、と言えるのかもしれません。
そういえば、数学基礎論、という学問がありますが、これもまた、ずいぶんとマニアックな議論をしておられるのだそうです。
(数学基礎論の話はこちらで言及しました。分厚い教科書の半ばころに「…であるから1たす1は…」と書かれているのだそうです)
そういう点で考えるなら、数学基礎論よりも、基礎医学に携わる研究者の数は断然多いわけです。基礎と言っても、本当に哲学的な部分よりは、もう少し臨床にも通底する話題を取り扱っておられるから、かもしれません(本庶佑氏がノーベル賞を受賞されたのも、免疫抑制の機構が、癌治療に応用できた、という点が大きく評価されているのだと思います)。
なので、生化学の知識と、生化学的な思考方法が、医師には必要なのだ、というのは、まあ、間違いが無い話なのかもしれません。
とはいえ、生きているヒトの身体はかなり複雑で、理論がうまく行っているから、ということで実践すると、思いがけない結果になる、ということもしばしばあります。
最近聞いた、そうなの?という話は、ノンカロリーの人工甘味料について。
この甘味料はそれほどカロリーとしては大きくないのだそうですが、実は、この人工甘味料を使っていると、腸内細菌の状態が変化して「太りやすくなる細菌」が増えるのだそうです。いわゆる「デブ菌」と呼ばれるものなのだとか。
なかなか、うまい話にならないのだなあ…と感心したのでした。
なので、理屈が成立するかどうか、ということを調べるために、臨床では、比較試験というのをやります。一方のグループにはこの治療を行って、もう一方には別の治療を行って、どちらがより長生きするのか?(あるいはどちらが症状がより解消するのか?)を調査することで、治療法の良し悪しを判定する、ということが必要になるのだ、とされています。
じゃあ、臨床の現場で、どちらかの治療が「良い」という結論になった場合に、それは何故ですか?という部分を十分に説明できる根拠は、無かったりします。もちろん、いろいろと比較しているところで調査をしますから、ある程度想像はできるのだろうと思いますが…。まれに「この治療が良いはず」と考えて研究プログラムを組んだのに、思いのほか、その治療を行う方が早くに亡くなることが多い、などの「有害事象」が発生して、研究自体が止まることだってあります。こういう時に「何が悪かったのか?」は判定できないこともあるようです。
どこまでも、試してみる…ということがつきまとうのが臨床の判断と研究になります。
そして、毎回の臨床で問題になるのは「この治療をすると、6割のひとが改善した」という研究報告があるとして、目の前にいる方が、「この6割に入る方なのか、それとも…?」という部分は、決して分からない(なるべく予測が正確に出るようには頑張っているのですが)ということです。
このあたりも、「エイヤッ」と、試してみる、という話にしかなりません。
こういう不確実性の中に、医学と医療の現場は動いているわけです。