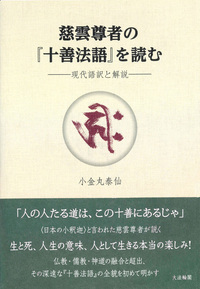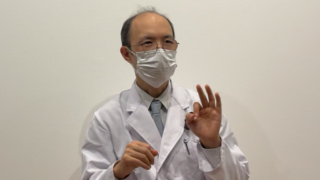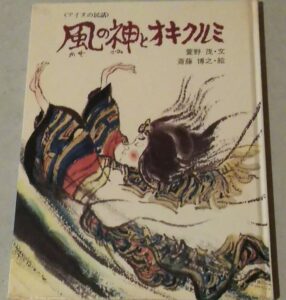自他の境界

先日「自分の分限」を超えたものに手を出すことは「偸盗」である、という話を書きました。
偸盗戒の説明はまだ続いています。分限の話のすぐ後ろに、宝間比丘という方の逸話が続きました。
はじめて僧の戒を受け終わったところで、お釈迦様に礼拝し、これからの修行の留意事項を尋ねたところ「あなたの物でなければ取ってはならない」というお言葉を頂いたのだそうです。それを受けて、宝間比丘は深く考えます。
今、釈尊が申された「自分の物でなければ取ってはならない」という教示は、何を意味するのであろうか。他人の金銀財宝や地位に欲をおこしてはならないことは、いまさら釈尊の教えを待つほどのことでもない。今あらためて丁寧に示されたということは、そのことではなく他に重要な意味があってのことであろう。
さて、今ここに自分の物とおっしゃるけれども、自分の物とは一体何であろうか。これまで在家の生活で得てきた家や財産や地位は、出家した時から自分の物ではなくなっている。再びこれに心を寄せるべきでない。次に妻も家族も出家すれば自分のものではない。頓着することはならない。次にこの自分の身体、頭や目や手足は自分の物であろうか。これもただの肉の塊で、父母の肉と血を分けていただいたものである。生まれ落ちて以後、衣服と食物、寝具、医薬で養ってきた物に過ぎない。最後には朽ち果てて土に帰るのであるから、自分の物とも言えない。
(中略)
また、心は善悪、邪正、是非、得失を分別するが、心は自分の物であろうか。この心それ自体も自分で心だと知っているわけではない。自分で心だとも言わない。認識を意味する「意」や、その主体である「心」という名称も外から仮に名付けたものであり、結局は感覚器官が捉えた影のようなもので実体はない。自分の物でもなく取ることはできない。
このように憶念した時、物にとらわれた心を完全に離れて、何のわだかまりもなく心が開けて、初めて聖者の境地に入り、さらに思惟して全ての煩悩を断じ尽くした涅槃を得たとある。
(小金丸泰仙著『慈雲尊者の『十善法語』を読む』大法輪閣、2020年)
時々、自分の境界を乗り越えてはいけない、という話をするわけですが、場合によってはそれが難しい、という方がいらっしゃいます。
感受性が高すぎて、家族や親しい人の感情をそのまま引き受けてしまう、という方もあります。
上手に自他の境界線を引くことができたら良いのですが、なかなか難しいこともあるようです。
わたしも、昔々は、そんなところがありました。
今でも覚えているエピソードがあります。
わたしは3人兄弟でしたが、時折、母は、「今日はあなたのための日」ということで、一日、街中での映画や買い物などに連れて行ってくれたものでした。面白そうな映画を調べていって、あれにしようか、これにしようか…とワクワクしていたものでした。
帰って来ると、家族が「どんな映画だった?」と訊いてきます。一生懸命わたしが説明しようとすると、わりとすぐに母がそれを受けて、理路整然と説明し始める、というのが常でした。
母が横で説明しているのを聞きながら、へええ。そういう映画だったんだ…となっていたわけですから、似たようなことが繰り返されると、わたしも喋り始める前に、母の顔を見るようになったりするわけです。
わたしと、母とが、別の人格であって、同じ映画を見たとして、それの感想が違っていても、あるいは映画の要約が違っていてもぜんぜんかまわないのだ、ということに思い至るのは、ずいぶんと後になってからのことです。
ありがたいことに「わたしの感想や解釈」を、それなりに家族は尊重してくれましたから、そのうちにわたしは「わたしの輪郭」をあらためて描くことができるようになりました。
それまではどこかで「母の言っていることはすべて正しい」というようなイメージが強く残っていましたので、これから離脱できなかったら、ある種の「呪縛」になっていたのかもしれません。
…ある種の「マザコン」と呼ばれても仕方のないような話でした。いやお恥ずかしい。
母は、たしかにわたしの良い理解者でいてくれました。
幼少期、いろいろと拗らせたわたしは、わりと容易に孤立しがちでしたから、そういう子どもを抱えて、極端な鬱屈をさせることなく、成長を見守ってもらえたことや、折々で味方になってくれたことはとてもありがたいことではありますが、やはり彼女もひとりの人間ですから、無謬というわけにもいきませんし、感性や視点の違いというのは、どこかで必ず生じるものです。
その違いを、最初のうちは、呑み込んでいましたが、違って良いのだ、そもそも同じはずがないのだ、ということに気づいた時には、ずいぶんと涙も流れたものでした。
ここで、自分の境界をはっきりと意識したことは、わたしが安定する上で、とても大きな一歩だったと思っています。
そして、この境界をしっかり意識しつつ、場合によって、多少のおせっかいと共に踏み込むことが、援助職としての医療者の立ち姿になるのだろうと思っています。