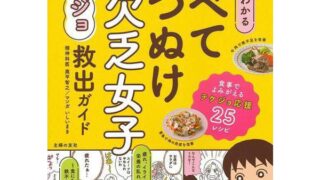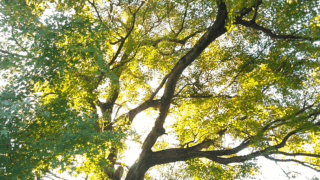葛根湯の話

カッコントウ。漢方をあまりご存知ない方でも、わりと有名な処方だと思います。
「風邪のひきはじめに」…なんていうフレーズと一緒にCMも流されていたりしたこともありました。
医療用漢方製剤には、製薬メーカー各社がそれぞれ、番号をつけています。
いちばん大手の会社が、葛根湯に「1」をつけているんですよねえ。
この医療用の漢方エキス製剤についている番号、欠番があったりすることもあるのですが、もともとは研究開発やっておられた方の研究ノートの番号…ということらしいです。まあ、研究に着手した順番、みたいなことになっているのかもしれません。
時々数字遊びみたいな関係も見つかるのですが…。
ところで、葛根湯が一番最初に着手されたのか…?という話になります。ひょっとすると、研究が始められた時代、とてもよく使われていた処方だったのかもしれません。
『傷寒論』という、3世紀ころに成立したとされる古典であり、漢方家の基本的な教科書とも言われている書物の冒頭に出てくる、というのも、その理由の1つだと思います。
…と思って冒頭を確認してみましたが、いちばん最初に出てくる処方は「桂枝湯」でした。どこまで行ったら出てくるか…?と探してみたら、太陽病篇の中巻の冒頭にありました。
落語にも出てきます。「葛根湯医者」という小咄があります。
https://www.eisai.co.jp/museum/herb/familiar/plant.html
以前もブログで紹介していました。
やっぱり、落語で出てくる、くらいには有名な処方だったんでしょうねえ…。
この葛根湯ですが、風邪の時には、汗が出ていないところで使って、汗をかくのが大事、ということになっています
なので、この薬を飲んだあとに、おかゆとか、うどんとか、温かい食べ物を摂って、布団にくるまって温まって汗をかくべし、というような指導をされる先生もあります。
場合によっては、短期勝負だ、ということで、汗が出るまで、3時間おきに内服するのだ、とか、倍量使うのだ、という指導をされる先生もいらっしゃったようです。
そんな話を真に受けた、学生時代のにしむらは、風邪を引いた時に葛根湯を内服したのでした。
ふむふむ。この葛根湯は、成分の構成をみると、ちょっと生姜の量が少ない。ってことは、ここにショウガをおろして、一緒に入れたら、ちょうど良くなるか?
そして、そもそもの量が少ない、と言われることが多いわけなので、すこし多めに内服しよう……なんていうことを考えて、複数の包みをさらさらとコップにあけ、おろしショウガを追加し、そして、お湯を注いで内服したのでした。
『傷寒論』の中には項や背中がつっぱるように凝っている状態のひとに…とも書いてあります。
当時すごく肩こりも強かったので、この条文が該当する!と思ったのですが、飲んでまもなく、多めに内服したのに、「あれ?ちょっと効きが悪い…?」と思ってしまったのでした。
うーん。まだちょっと効きが悪いのかあ。
そしたら、ここから「追い葛根湯」だな。…とばかりに、間をさほどあけずに、再びいくつかの包みをあけて、内服したのです。
今から考えるなら、もうちょっと待ちなさい、と指導するところなのですが。
その後布団をかぶって横になっていたのですが、まもなく、急に動悸が始まりました。
心臓がドキドキして、止まりません。
え?なに?なに?と不安になりましたが、動悸は止まりません。むしろ、不安がさらに動悸を増強しているようにも感じます。このまま暴走して止まらなかったら…?なんていうことを考えたら、本当に不安が高まってきました。
まあ大変…。
ええい、ままよ!と、いろいろを放り投げて、そのまま寝てしまうことにしました。
起きた時には動悸はおさまっていたのですが、本当に動悸の最中は、どうにかなってしまうかと思いました。
今になって考えるなら、葛根湯に含まれる「麻黄(マオウ)」という生薬は、交感神経の緊張を引き起こす作用があります(エフェドリン、という昇圧薬が、このマオウから分離され、西洋薬として用いられています…これを抽出したのは日本人の研究者ですし、エフェドラというのが麻黄(マオウウ)の基原植物の名称です)。
葛根湯を内服して、15分くらいで、この麻黄(マオウ)の成分が吸収され、効果を発現してきたのでしょう。
しかも、立て続けに、指定の量よりもはるかに多い量が入りましたので、すごい動悸になり、けっこう長く続くことになった、ということだったのではないかと思います。
やっぱり用法用量は守らないと、エラい目にあうなあ…と骨身にしみた思い出でした。
『傷寒論』が書かれた時代は、重さの単位も「グラム」なんていうものがありませんから、単位としては「両」とか「枚」とか、そういうものが用いられているわけです。これを一升の水でわかして、水が半分になるまで…みたいなことが書かれていますが、現在はグラム単位での表記に書き換えられています。
じゃあ、たとえば、葛根3両、って書いてあった部分を、葛根3gに読み替えたら、大抵は、使用している生薬の量は少なくなります。
そんな少ない量の生薬で効果が出るのか?という議論はけっこうありますが、ひとによっては効果が出るし、ひとによってはもっと量が必要、ということもあります。
この辺、漢方薬が「シグナル」として働いているのか、それとも「材料」として作用しているのか、というあたりでも違いがありそうです。
クリニックで診療していても、「思いのほか、急激に改善する」方と、「薬の力がなかなか及ばない」のか、改善に時間がかかる方がいらっしゃいます。
なかなか良くならないのは、わたしのうでが今ひとつだからじゃないか、と言われるとそうなのかもしれませんが、ゆっくり良くなる方もけっこういらっしゃいますので、しばらくはお付き合いくださいませ。