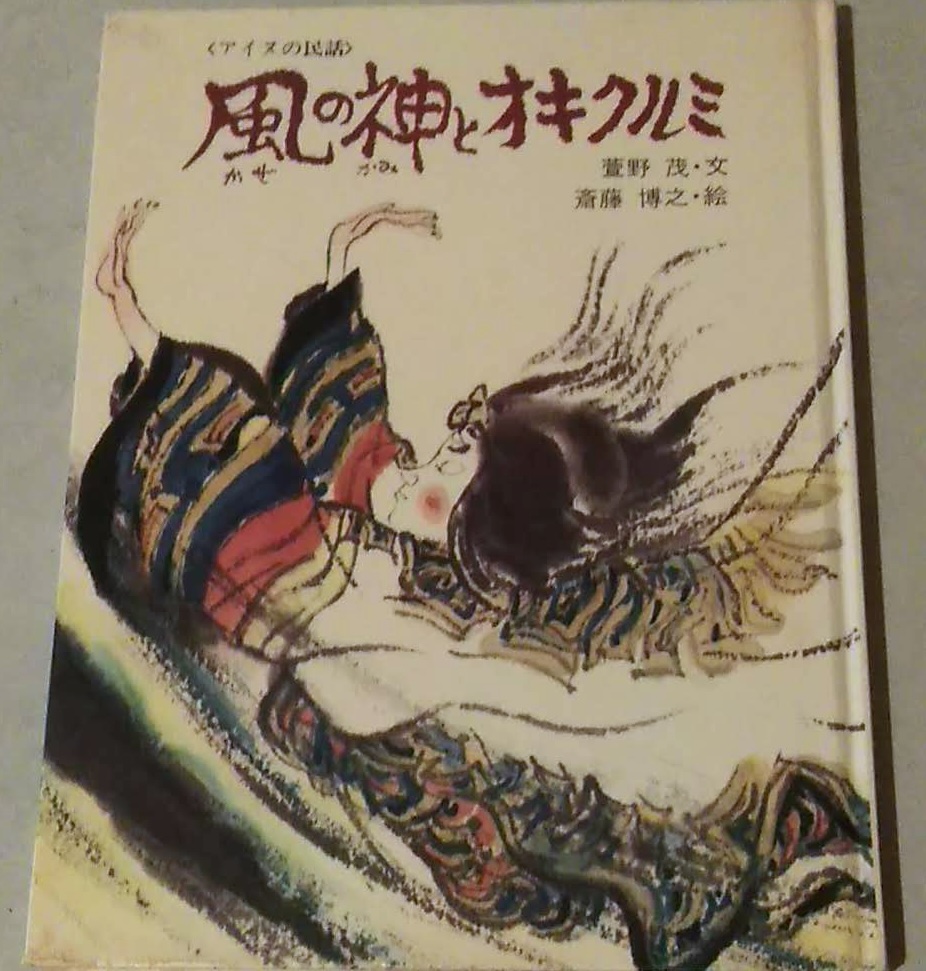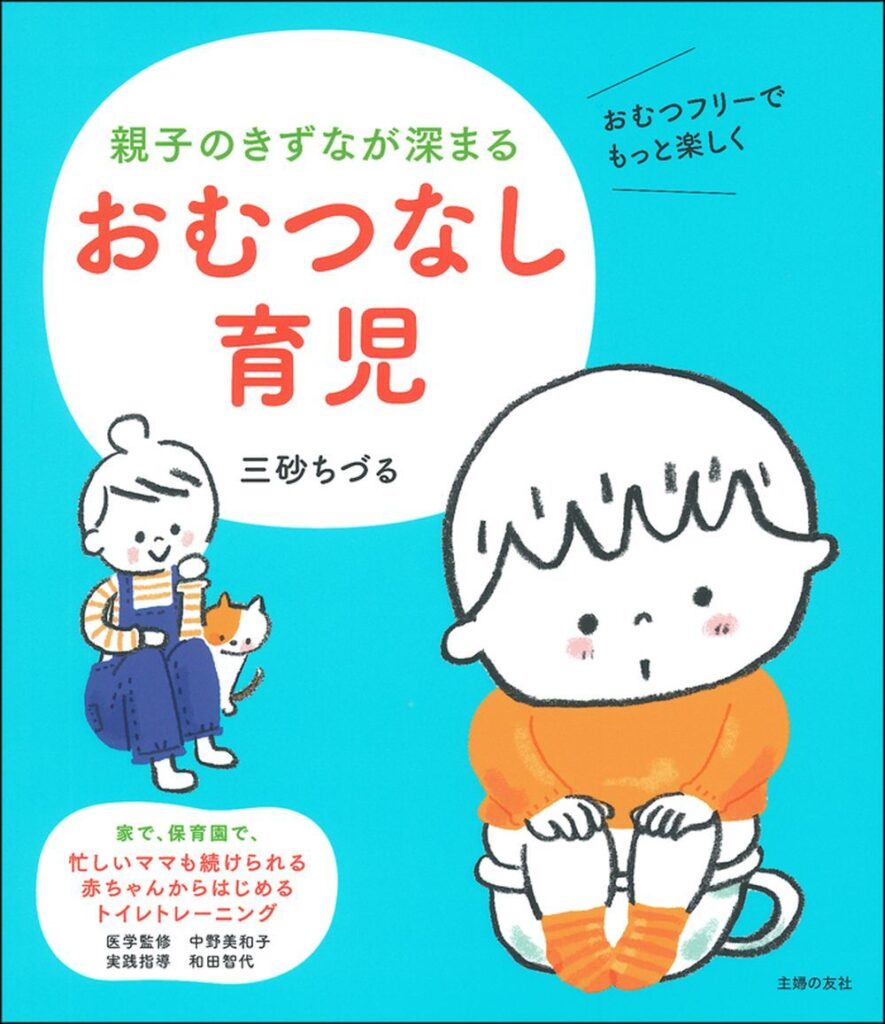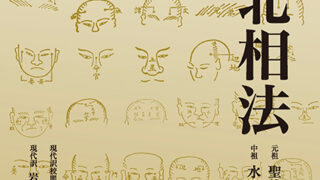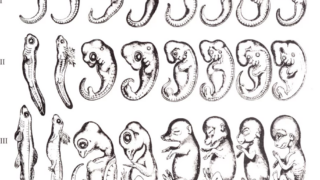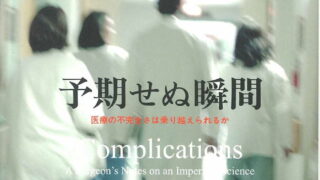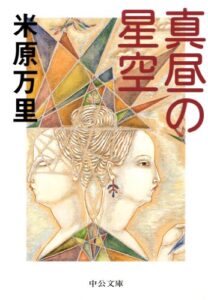責任を引き受ける

以前も少し「責任」という言葉にまつわるお話を書きました。
「ひとが引き起こしてしまったことに対して責任を取る」という話を、野田俊作氏の言葉を引用して書いたものです。
一方で、西洋医学の恩恵は、「病気になったことを、個人の責任に帰さない」ということだ、という話も書きました。
じつは、この「西洋医学の恩恵」の話は、三砂ちづる先生に教えていただいた話です。
三砂先生の話は、『おむつなし育児』のご紹介の時に少しだけ触れました。疫学の研究者で、津田塾大学で学生さんたちの指導をされています。どこにいらっしゃるのも着物をお召しになっておられますが、文章にも姿勢にも一本芯が通った方です。
西洋医学が、病の責任を個人から取り除いた、というのは、福祉の意味合いでみるなら、大きな恩恵になるのですが、同時に、「患者自身を無力で矮小な存在に陥れる」という反作用もありました。
病気になったことの原因も根拠も、個人の生活には関係無い、と断言し、健康問題と、本人の生活の関係をすべて消去してしまうならば、逆に、本人の生活を改善することで元気になってゆく、ということの根拠も消えてしまいます。個人の健康問題が、本人の生活と関係無いものとしてしまうならば、病を得るのも「運が悪かった」にしかなりませんし、そこから回復するのも「運が良かった」という話にしかなりません。思ったように元気にならない、などの悩みにも「あなたにできることは何にもありません」というメッセージが常に突きつけられる、ということになりかねません。それはどれほどに患者個人の勇気をくじくことになるか、計り知れない影響がありそうです。
ですから、西洋医学の文脈においても、「無力な存在」に陥った患者を勇気づけるための方策を講じなければならなくなりました。
その「患者を勇気づける」方策のひとつが「患者を中心とした診療方針の決定」になります。インフォームドコンセントとか、インフォームドチョイス、と呼ばれる形で、患者自身の意志が、診療に反映されることを大事にしてゆく、という方向性ができたのでした。
個人の人生をいったん疎外して、患者の身体を客体化したり、あるいは、医療的な介入をそのまま無防備な状態で受け入れることを強要する、という状態は患者個人を極めて脆弱な状態に陥れさせることになるでしょう。こうした疎外が続くならば、患者は、生きていく意欲さえ喪失してゆきかねません。
少し話は跳びますが、わたしは、いろいろとヒーリングなどの話題に興味を持っていた時期がありました。ヒーリング、っていう話になるとちょっと怪しいものもありますが、関連の本を読みあさった時代がありました。
そんな本の中に「ホ・オポノポノ」というタイトルが含まれたものがありました。なんだそのほのぼのするような名称は…と思ったのですが、どうやら、ハワイの現地語から来た言葉のようです。
この「ホ・オポノポノ」の本をわたしが読んだときに、そこには「起こることは全て、自分に責任がある」という意味のことが書いてありました。
全て、っていうなら、極端なことを言うと、隕石が落ちてきても、あるいは大きな地震が起こっても…?そういうことさえも、「自分に責任がある」って、それは一体どういうことなの??ってその「責任」の重さにおののいたのでした。
そういえば、野口整体でも「自分に起こったことは、全て自分の責任」という思想があります。交通事故でぶつけられたとして、ルール上は10:0で相手が悪い、という状況であったとしても、自分の責任として引き受ける、という思想があるのだそうです。
実際に野口整体の指導をされている先生が、交通事故に遭ったこともあったのだそうですが、その時に、相手の方に自分の身体を調整する手助けだけはしてもらった、という話を聞きました。まあこれもこれで、筋金入りの思想と実践です。
もちろん、他者にそれを押しつけるわけにはいきません。自分自身が納得して、それを引き受けるかどうか、という話に限定されたことです。
ところで、「全てのことは自分の責任」という言い方をすると、とても重たいのですが、「全てのことは、自分のあり方と、自分の動きで、決められる」という言い方になれば、これは個人万能の思想になります。表現の仕方は違いますが、言い換えると、おおよそ、同じような事を表現しているだけだったりします。
つまり、「ホ・オポノポノ」や野口整体の思想は、西洋医学が剥脱した個人の責任を、取り戻し、個人を有能で、世界に対して強い影響力を持った存在として認識することで、個人を勇気づけ、力を与えている、とも言えるわけです。
どちらが「正しい」認識なのか、という議論は、この文脈の中では、あまり意味を持たないと思います。
正しいこと、が必要なわけじゃなくて、個人が、自分自身に、あるいは世界に絶望せずに、生きていく方策を見出すための指針です。
時には、責任の重さにため息をつき、時にはそれを一時的に棚上げすることも、必要なことがあるのでしょう。ただし、ずっと責任を回避し続けていると、どんどん個人の力を喪失することになりそうですので、それらの両方がよい塩梅で採用される必要があるのかもしれません。
心理学の治療にも二種類ある、ととある方が書いていました。
全てをあばきたてて、詳細を検分するような形の治療方法と、それから、何もかもをひっくるめて引き受けて、真綿でくるむように、覆い尽くし、抱えることで治療してゆく方法だそうです。
責任を明確にすることが、場合によっては、治療のプロセスになるのでしょうし、逆に責任を棚上げさせることも、場合によっては、治療のプロセスになる気がしています。
とはいえ、適切なタイミングで、適切な選択肢を選ぶ、ということも結構難しいのかもしれません。
現状、しんどい状況にある方が、ちょうど良いタイミングで、ちょうど良い方法を選ぶことができますように、と祈ってやみません。