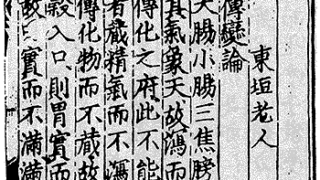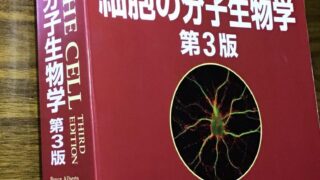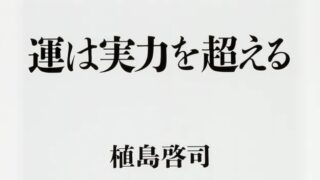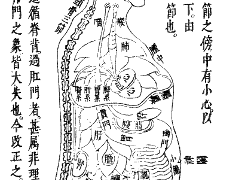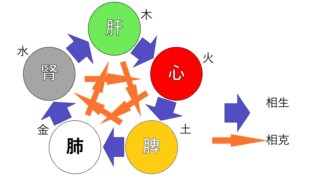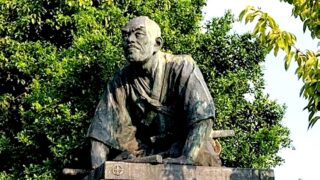近畿産婦人科学会に参加してきました

昨日は、近畿産婦人科学会の学術集会(年に2回程度開催されています)に参加して、少しばかり勉強をしてきました。
産婦人科学会での大きな話題は「婦人科の癌の治療」とか「帝王切開を含む手術」といったところですが、それ以外にもいくつかの話題がありました。
ひとつは、不妊治療を巡る、倫理的な話のこと。
1970年代後半に、いわゆる「試験管ベビー」が、世界ではじめて生まれました。そこから50年が経過し、今では世界で1000万人が体外受精による出生になっているのだとか。
日本では、体外受精が保険適用になったこともあり、また、全体の少子化とか、出産年齢の高齢化とかもあるのでしょうか、今では、生まれてくる8人にひとりが、体外受精による妊娠なのだそうです。
こないだまで、25人にひとり(なので、だいたいクラスにひとりくらいは居るよね)って話をしていたのですが…時代はずいぶんと変わってきたようです。
体外受精は、技術的にはいろいろと、「自然ではあり得ない」ことを発生させることができます。
生物学的な母親…という言い方も難しいですねえ。ええと、遺伝子的な意味で母親、つまり、卵子を提供したひと、と、それから、実際に妊娠したひとが別、ということが可能になるのが、体外受精です。
場合によっては、この妊娠のために用いる精子の提供者が、出産するひとの配偶者じゃない、ということだって起こりえます。
えええ?ってなるでしょ。
実は、不妊治療のハシリの頃は、昭和24年とか、そういう話になるらしいのです。当時南方から帰国した兵隊さんたちが、男性不妊になっていて…とか、そういう話なんですって。(気候が暑かったから、って説明でしたけれど、本当かしら?)
で。当時からしばらく、慶応大学病院では、慶応大学の学生さんたちに、精子の提供をして貰っていた、という話があります。これは、不妊治療としては有名な話で、「非配偶者間人工授精(AID)」と呼ばれています。
当時は「慶応に入れるくらい頭の良い学生の、若い精子なんだから良いだろ」みたいな話だった…のかもしれない、と言われています。
そういえば、ちょっと前に、女性から男性に性適合手術を受けた方が結婚されて、その妻が妊娠出産されて…というときに、父親の認定はどうなるのか?みたいな話が話題になりました。
戸籍を受け付ける担当が、「この方、どう考えても父親になれないでしょ」っていう理由で受理を拒んだとか、そういう話だったように記憶しています。
民法では「婚姻状態にある女性が出産した場合、その夫を、出生した子の父親と推定する」という規定があります。夫が男性不妊であるかどうか、は考慮しない、というのが、法律のルールだったわけで、受付担当者がなまじっか科学的に解釈を差しはさんだことでややこしくなった、という話なのですが。
不妊治療の中では、体外受精というのをするようになってきたのですが、男性不妊がある場合、体外受精の時に、ドナーの精子提供を受ける…という話は、日本では「ちょっと待て」という声明が出て、そこから20年くらい、「ちょっと待て」が続いていたのだそうです。
最近、待ちくたびれて…という話を時々耳にするようになりました。
なかなか、このあたり、難しい話がいっぱいあります。
もうひとつ問題になっているのは、「出生前診断」の話題です。いろいろな遺伝性の病気が、遺伝子を調べることで分かるようになりました。そうしたら、それらの病気の遺伝子について、受精卵の段階で調べることができる…って話にもなります。今までは、流産するかしないか、というポイントだけが調べるところだったのですが、だんだん、その範囲を拡げてはいけないのは何故か?という議論になりつつあります。
生まれてきた子供が、そういう遺伝性の疾患を持っているというのは大変だから…という議論もありますが、じゃあ、すでに生まれてきて、今生きているけれど、その遺伝性疾患を抱えている人たちの存在を否定することにはならないのか?という問題の追及があります。
一部の遺伝性疾患には「これは子孫にも遺伝されるので、極力子供を作らないように…」という記述が書いてあるパンフレットも、平成のはじめ頃までは配布されていたのだ…という話も聞きました。
「授乳で感染するHTLVの感染を防ぐために、完全ミルクで育児しましょう」という話とは比べものにならないくらい、重たい話になってしまいます。
こんな話を、産婦人科医だけで考えていても仕方ない…ということで、もっと広くに意見を求めるようになったのだ、という話でした。
そして、議論は、すぐに結論が出る話でもない、ということ。
立場が変わると、それだけで、主張する内容が変わります。だからといって、相手を完全に否定するでもなく、相手の意見にまるごと同調するわけでもなく、喧嘩わかれするでもなく…。それぞれの意見をぶつけあいつつ、相手を尊重して、議論を続けることが必要なのだそうです。
うーん。難しい話ですよねえ。
時代が変われば、倫理の境界線が動くことも結構、あります。
以前は「出生前診断の話題を取り上げることすら、公序良俗に反する可能性がある」とされていましたが、今は、もう少し公平な視点で、情報提供するべきだ、ということになってきているようです。
もう少し時間が経てば、また価値観も変わってくるのかもしれません。
とはいえ。不妊治療をする方には、その「もう少し」が待てないところにおられる方も多いわけです。
良い道筋が見つかることを祈っております。