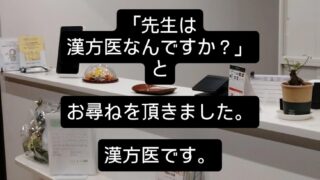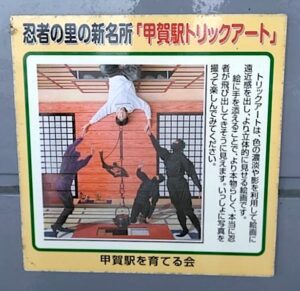選択の余地

昔、高校の時に、けっこうな田舎の学校から転校してきた友人がいました。なんでも、その田舎では、「男子は野球部、女子はバレー部しかなかった」のだそうです。
そもそも同級生の人数も少ないでしょうから、あまりいろいろクラブを作っても、どれもチームができない人数しかいない、ということになりかねませんから、何かに集中させて、ひとを集めないと、という判断なのでしょうか。うーん。人数が少ないから、仕方ない…と言っても良いのでしょうか?
そのとき提供されているクラブにもともと入りたかったとか、うまいこと馴染んでいられる状態とかであるなら、さほどつらいことではない…のかも知れませんが、いわば部活動の選択を「強制」されている、という状況です。
野口整体の創始者である、野口晴哉氏は大正時代から昭和にかけて活躍をされた方です。当時、さまざまな民間療法を寄せ集めて、治療家の団体を作っていたこともあるようですが、その中に「断食療法」というものがありました。
太平洋戦争前後の話になります。戦中から戦後にかけて、食糧がぜんぜん足りない時代がありました。
「あなたのところはそもそも断食で健康になると称しているわけだから、ちょうど良いのじゃないのか?」みたいなことを言ったけれど、どうにもその主宰者の方は食べ物を集めるのに汲々としていた。「食へぬ」と「食はぬ」と、たった一文字の違いで、大きく違う…ということを書いておられます。
強制的に食糧が手に入らない環境にされて「食へぬ」と、ひとはどこかで生きることを諦めがちになりますが、むしろ自分で心を決めて断食をするなど「食はぬ」ならば、それは健康への道になったりするわけです。食事が身体に入ってこない、という点だけに注目すると、とても似たようなことが起こっているようにも見えるのに、結果が大きく違う、というのは、本当に不思議ですよねえ。
そういえば、大手の衣料品販売店では「こんな色のアイテム、誰が買うの?」という色合いのものが置いてあったりするらしいですが、そうした「妙な色合い」との比較選択で、オーソドックスな色目のアイテムがよく売れるという仕掛けがあるのだそうです。何かのビジネス関係の文章で読みました。自分で選ぶ、とか、自分で選んだ、という心の動きは、ずいぶんと重要なことなのでしょう。
とはいえ、「あなた、じぶんで好きで選んだんでしょう?」という形で、責任をおっかぶせるのも、それはそれで違うように思います。
自分で選んだ、にもいろいろな段階がありますから。
やむにやまれぬ 人生は綱渡りだ
選ぶつもりで選ばされる手品だ
と、これは中島みゆきさんの歌「愛だけを残せ」の冒頭ですけれど、まさにそのような、「選ばされる手品」が増えてしまっているようにも思います。
心理学的な技術が、中途半端な選択肢の呈示と選択(「今すぐ、とてもつらい目にあうのと、今はすこしつらいけれど、将来は楽になるかもしれないのと、どちらが良い?」なんていうのは有効な選択肢じゃないと思います)を介して世の中を操作する形で用いられるようになって久しいわけで、なかなか、大変な時代になってきています。
とは言え、やはりきちんと自分が自分の人生を、選び取っていくことが大事なわけですし、そういう選択の余地が許されてあることが、ひとが生きる時の余裕になっているのだろうと思います。