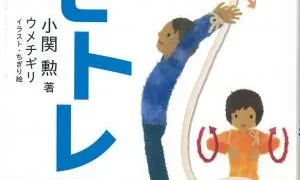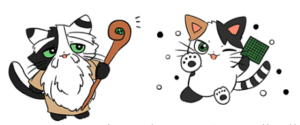青年と老年のあいだ(『心コレクション』から)
わたしの精神科の師匠が紹介してくださった関係で、植島啓司という宗教学者の先生を知ることになりました。
かなりの数の本を執筆・出版されているのですが、植島先生の本領は「注釈」をつけた時に発揮される、というのが師匠の意見で、先生が集めておられた言葉に、注釈をつけた、という形の本が、以前出版されたのでした。
『心コレクション』
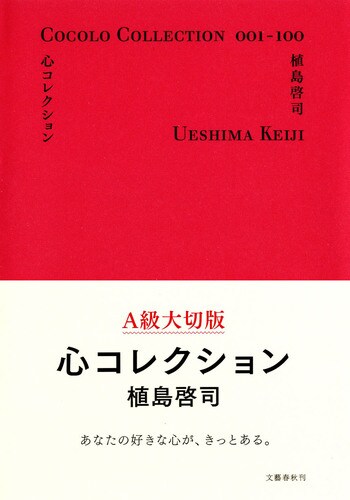
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163733906
とても素敵な本です。
わたしも発売された頃に購入していたはずなのですが…どなたかに貸したままになっているのか、手元には見当たらなくなっていました。今は新刊としては販売もしていない様子で、中古で入手しなおしましたが、奥付を見ると2010年の出版になっています。もうこれが出版されてから15年が経過したんですね…。時の流れは早いものです。
久しぶりに、本をめくっていたら、こんな文章が載っていました。
生涯で、青年と老年のあいだに、一本のかなりはっきりした境界線を引くことができると私は思っている。青年は利己主義をもって終わり、老年は他者のための生活をもって始まる。
ヘルマン・ヘッセ「ゲルトルート」
この言葉の冒頭には「自分もひとりの他者となる」と冠してあり、また、植島先生の注釈が次のページにあります。
人生をマラソンにたとえるとどこに折り返し点があるのだろうか。同じ道を走りながらもある点で折り返すと自分の精神の持ち方まで変わってしまう時期がやってくる。必ずしも利己主義が悪いということもないのだが、人間のもっとも気高い姿は他者を思いやる精神に起因するものであることは間違いない。他者を思いやり、自分もひとりの他者となるのである。
今の世の中は、アンチエイジング、と呼ばれるような、ともすると「老年」を否定するような行動が推奨されているかのような雰囲気もあります。ひとが老いていく、ということをどこまでも否定してゆくのか、それとも、他者を思いやる、という形で、自分自身の世界を拡げていくことをはじめるのか。
子どもが生まれて、母になり、父になった大人は、大抵は、子どものために、ということが先になってくる…のがある種の理想であると思われています。
もちろん、子どもと生活を共にしつつも、自分がいちばん、という親もありますし、それにしんどい思いをしてきた子どももいるのだと思います。
今どきの話でいうなら、老年になっていくことを拒絶しつつ、子どもと一緒にいる、なんていう、そういうひともそこそこいるのかも知れません。
なにしろ、明治維新と、太平洋戦争の戦後と、の2つのタイミングで、日本人は、大人を否定することを、社会全体としてやってきました。いまさら、成熟した大人…あるいは老年、というものを、文化の中に持ち合わせていないのかもしれません。
けれども、ここにひとつ。
他者のための生活をもって、老年がはじまる、とあるならば。
成熟という道は、ここにあるのかも知れません。
そして、植島先生がきちんと書いておられますが
「自分もひとりの他者となる」わけです。
自分自身をないがしろにすることを許容しているわけではなく、自分自身を大事にしつつ、他者のために、という生き方を選んでゆく。
その中に、何かの答えのようなものが、あるのかもしれない、と思っています。