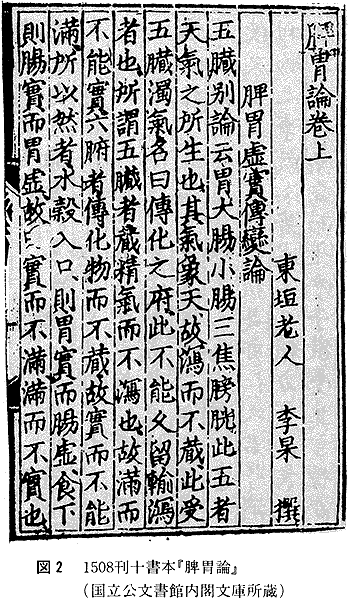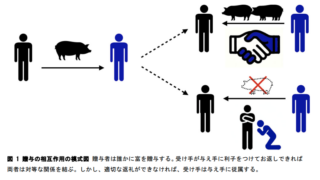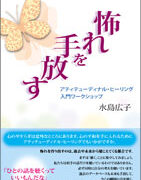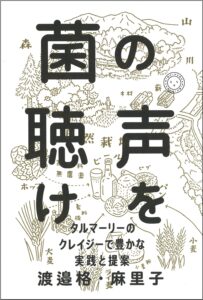食欲不振と漢方
先日、10月18日には、健康教室を開催しました。今回は「食欲不振と漢方」というお題でお話をしたのでした。
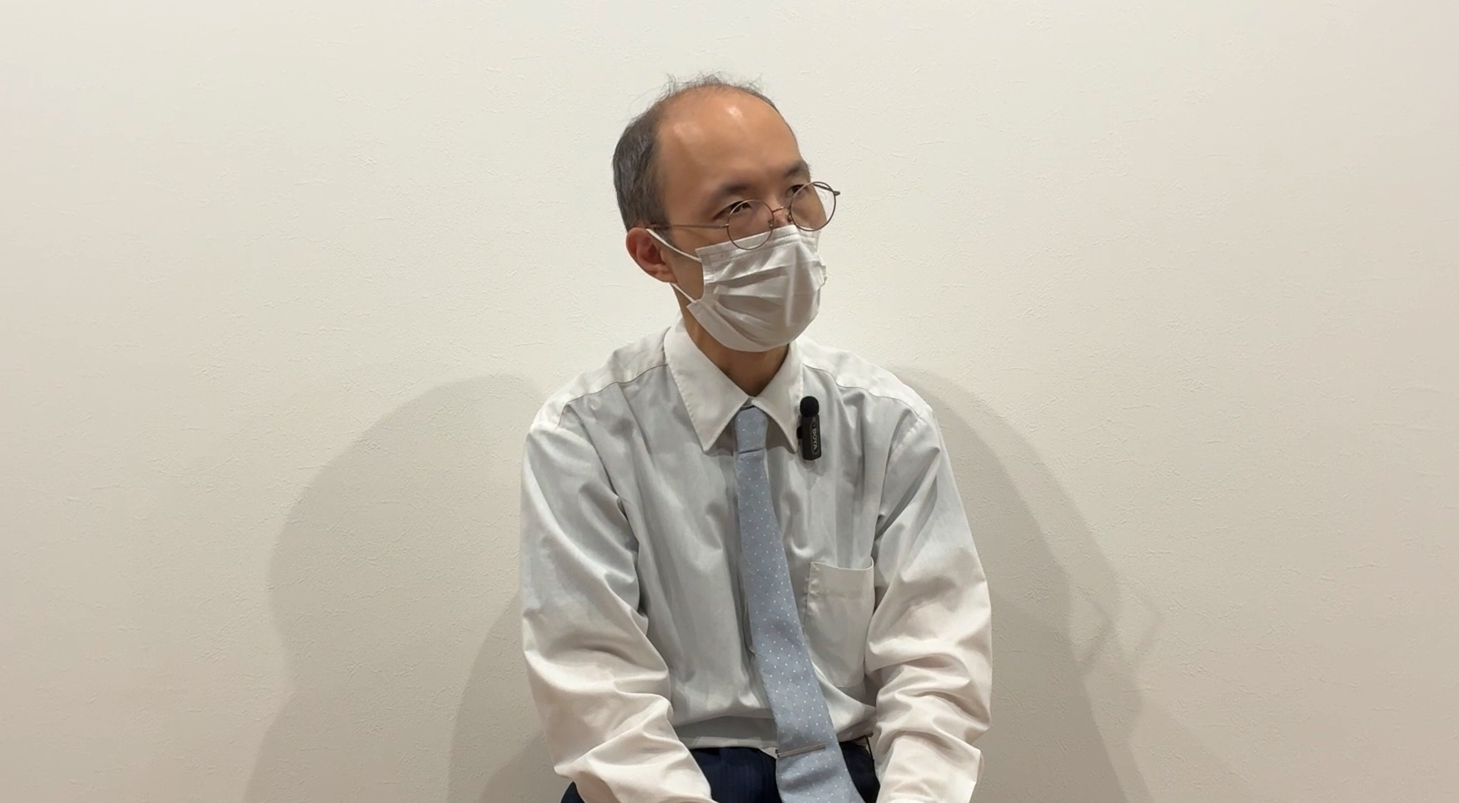
以前から何度かお話していますが、胃腸…漢方では「脾」をこれに配当していますが…つまり消化吸収のはたらき、というのは、生き物としてとても大事な部分です。
ここが不調になると、全体に身体が動きづらくなります。
食欲不振、っていうのは、そういう意味でもとても大きな問題になったりします。
秋は、「体育の秋」とか「読書の秋」などの表現がありますが、「食欲の秋」でもあります。「天高く馬肥ゆる秋」というのは古くから言われた言葉でもあります。
秋晴れの空が、どこまでも澄み渡るように感じられますから、天が高く見える、というのは、秋に特徴的なんだそうです。いや、夏の青空もけっこう高いよねえ…?なんて混ぜっ返してしまいそうですが、入道雲が出ている時期から、早速「秋」なのかも知れませんし、真夏の照りつけるような気候のときには、あまり空を見上げたりしないから、かも知れません。
脱線が過ぎましたが、こうして、馬だけでなく、ヒトも食欲旺盛になり、コメの収穫の時季と重なること、そして、冬に向けて蓄える時期でもあるわけですから、しっかりと食べよう、という話になります。
まあ、現代は飽食の時代と言われます。飽きるほど、ではなくて、ほどほど、というのも大事ですが。
そんな「食欲の秋」になってくるはずなのに、食欲が出ない、という場合。何を考えて、どのような漢方を使うか?みたいなことが「食欲不振と漢方」の話になります。
秋の食欲とは多少ズレる話なのですが、産婦人科医として、いちばん有名な、「食欲不振」に、「つわり」というのがあります。これは妊娠の初期に、胃腸の調子が悪くなり、吐き気がするとか、飲み込むのがつらい、とか、そういう症状のことを指す言葉です。
一部の方は「食べつわり」と呼ばれるような、何かを食べていないと気持ち悪い、という症状になりますので、これはいわゆる食欲不振には該当しませんが、このつわりの吐き気にも漢方薬が有効だとされています。
小半夏加茯苓湯というのが、このつわりに有効なのだ、という話がありますが、他にも、「伏龍肝(ぶくりゅうかん)」と呼ばれる生薬が使われたりしていたようです。
この伏龍肝、黄土で作られたかまど…の古いもの、の中央部の焼け土を取ってきて使う、ということになっています。土??って思いますよねえ。これ、胃腸を温めつつ、気を降ろすはたらきがある、とされているそうです。
昔、鉄欠乏性貧血の症状のひとつに「異食症」というのが出てくる、と聞いた覚えがあります。氷をものすごく食べたくなる、とか、壁土を食べるとか。壁土!って思いましたが、ひょっとすると、これも「黄土」に近いものだったのかもしれません。
おうど色、の「黄土」ってこれなんでしょうねえ。
ほかにも、桂枝湯がそのままつわりに効くことが多いのだそうです。
つわりは、胃の気が逆流している状態で引き起こされる吐き気です。これは、下腹部にいる胎児からの気の放散が、胃の部分で、胃気と衝突して逆流する、という病理が起こっているからと考えられます。
脾虚肝乗の状態…つまりいろいろと頭が忙しくなって考え込み、悩みを抱えているような状態は、頭に気が昇ります。この気は、本来胃腸を守るところから移動しますので、胃腸の調子は維持しづらくなりますし、加えて、胃気の流れが逆流しますので、食欲が低下する場合があります。
ストレスで食事が入らなくなるタイプは、こういうことが起こっているのだろうと思われます。
もちろん、ストレスの時に、食事が増えるタイプもいらっしゃいます。それは、胃腸がやはり強い方なのでしょう。胃腸の強い・弱いは、個人差がありますので、あまり胃腸が弱い方が無理に強い方の食生活をマネしても、なかなか追いつかないというか、むしろ胃をこわす方も出てきますので、ご注意頂きたいところです。
食事が入らない理由のひとつとしては、胃腸の力が落ちている、ということもあります。これには、脾気虚に加えて、食滞というものもあります。つまり、食べたものが、先の方で溜まったまま、渋滞してしまっている状態です。そのような時にも食欲が出なくなります。まあ、一種の食べ過ぎなのですが。
この食滞には消導薬というのが用いられます。漢方の中で有名な生薬としては、山楂子、麦芽、神麹などが知られています。あまり医療用の漢方エキス製剤には含まれていませんが、山楂子は酸っぱい木の実で、砂糖と混ぜた形のお菓子が売っていたりします。こういうものも、食滞の改善には有効です。
麦芽はビールの発酵の時にも用いられる、デンプンの分解酵素を含む生薬です。
山楂子と麦芽、神麹とを組み合わせた処方としては「焦三仙」というものが知られていて、これをもとに作られている製剤(晶三仙)があります。
その他、消化酵素として有名なのは、大根のジアスターゼや、パイナップルのブロメラインなどが知られています…って書きましたが、パイナップルの消化酵素の名前はしりませんでした。タンパク質分解酵素、って話では、わりと有名です。ゼリーのゼラチン(タンパク質)を分解してしまうので、パイナップルゼリーを作るのは難しいのだとか。
大根おろしなど、生で摂取すると、消化に良い、という話があります。
大根役者、というのは「あたらない」ということを言った表現ですが、これは、大根での食中毒が無いことを取り上げて使われるようになったのだそうです。
漢方では、大根の種を「らいふくし」として生薬で使っていたりします。これもエキス製剤に含まれてはいない生薬ですが、消導作用があるとされています。
こうしたものを用いて、胃腸の調子を整えると、食欲が改善する…というのはとても有効な治療法です。
が、同時に「食べ過ぎによる食欲不振」には、少食にする、というのもひとつの治療法としては有効だったりします。
絶食療法とか、少食療法と呼ばれる治療方法があります。「断食(だんじき)」と呼んだりすることもありますが、断食と呼ぶ時は、宗教における修行の意味合いを伴うものが多いようです。
冒頭に脾の力、という話を少ししましたが、食べたものを取り込み、自分の身体の一部にしてゆく「同化」というはたらきがとても大事なわけです。口から何かが入った、ということを「食べる」ということでは大きく話題にしますが、本当に大事なポイントは「食べたものを消化吸収出来た」というところになります。
これをおろそかにして、口からたくさんものを詰め込んでも、胃腸が疲弊するばかりで、消化吸収のはたらきを発揮できなくなります。
そういう時には、いっそのこと、一度お腹を空っぽにして、食欲が出てくるまで待ってみる、というのが、この絶食療法のひとつの考え方です。
なんらかの不調が発生したときに、その身体に「何かを与える」ことを、わたしたちはしばしば考えがちですが、いったん「与えているものを減らしてみる」という考え方は、示唆に富んでいると思います。