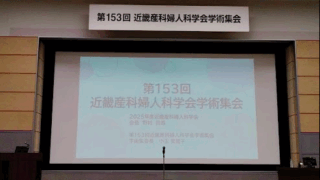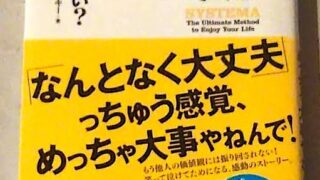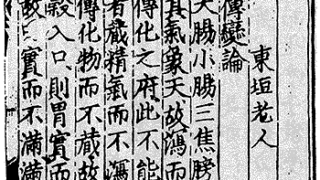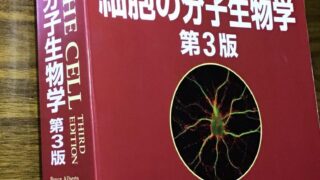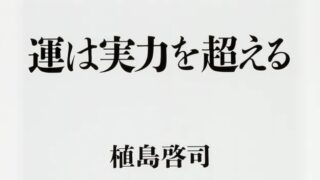あとのまつり再考

先日あとのまつりについて、ちょっと書いていました。
いわゆる慣用句としての「あとのまつり」というのは、祇園祭の「後祭」と関係があるのか、無いのか、というのがテーマでした。
ところで。祇園祭なのですが、前祭山鉾巡行のあとで、神幸祭というのがあります。これで、八坂神社から、四条御旅所まで神様のおみこしがやってくるわけです。
http://www.gionmatsuri.or.jp/schedule/
一週間程度、このおみこしが、御旅所のところに鎮座ましますわけですが、後祭山鉾巡行と花傘巡行のあと、還幸祭というのがあり、御旅所に滞在されていたおみこしが、八坂神社までお戻りになります。
16世紀くらいの、いわゆる前近代の人々にとっては、前祭、後祭がどうこう、という話よりは、この「神様がおこしになっている」ところが主題になっておられたのではないでしょうか…?


(前祭の船鉾…神功皇后の出征を故事として作られたもので、凱旋を故事とした大船鉾とは対になっているようです)
言ってみたら、前祭が「歓迎パレード」で、後祭が「送別パレード」なわけです。
あるいは、オリンピックの「開会式」と「閉会式」です。
オリンピックの閉会式は、それはそれで見どころがありますが、かと言って、競技を見たい、という方が、たどり着いたら閉会式だった、というのであれば、それは「あとのまつり」と言いたくなるかもしれません。
つまり、「あとのまつり」がみすぼらしいから、とか、あるいは「役に立たないから」ではなくて、「お招きした神様がお帰りになってしまっておられるから」ということであれば、「あとのまつり」は手遅れ、という話になります。
…となると、「あとのまつり」ってやっぱりそれなりに、祇園祭の後祭を参照された表現なのかもしれません。
あるいは、中世ないし近世の時代に、先祭・後祭とするような、そんな神事があちこちで開催されていたのかもしれませんね…。