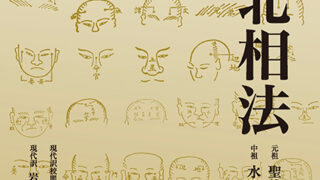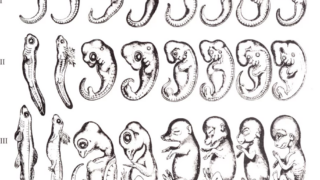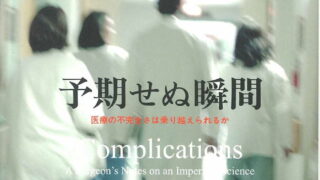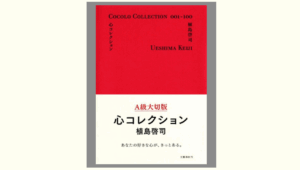ことばの重さ
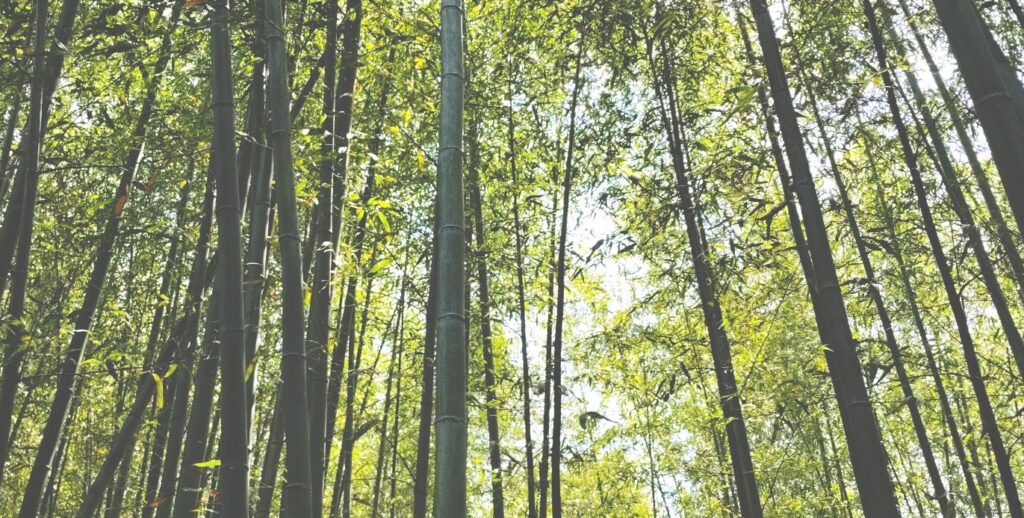
ボディートークの創始者、増田明氏は、声…の基になっている「息」に注目をしていました。「息はいきかた」というのが彼のことばでした。
ギリシアの神話には、パン神と知り合った人間の話があります。
口元に手のひらを持ってきているのを見かけたパン神が人間に「いったい何をしているのか?」と尋ねます。
人間は「息で手のひらを温めているのだ」と返事します。
その後、暖かいところに移動して、シチューを供された時に、人間が口元で何かしているのを見たパン神はふたたび「いったい何をしているのか?」と尋ねます。
人間は「息を吹きかけてシチューを冷ましているのだ」と返事します。パン神は「先程は手のひらを温めていた、その息で、今度はシチューを冷ますというのか!?人間は信用ならん!」と、その場を去って行きました。
呼気の温度は「フーッ」と吹いても、「ハーッ」と吹いてもおよそ35℃くらいで、あまり変わらないのだそうですが、まあ、厳密な温度の話は別としても、実生活の中で、ひとは暖かい息と、冷たい息を使い分けます。
増田氏はこれを「暖息」と「冷息」と呼びました。
さらに、増田氏は、息の「方向」が、ひとによって、心の状況によって異なるとして、これを分類しました。
明るく、躊躇いのないような、外交的な息を「外に向かう息:外息」、やや引っ込み思案的な、内省的な息を「内に向かう息:内息」と名付けました。
外に向かう、暖かい息は「喜」を、冷たい息は「怒」を。
内に向かう、暖かい息は「楽」を、冷たい息は「哀」を、端的に代表しているのだ、というのが氏の話でした。
そして、ひとのことばは、こうした息に乗って出てきます。
わたしたちはもっぱら「意味」の世界で生活をしていますから、文字が並んだところから、その意味を拾い上げることもできますし、ひとが喋っていることばの「意味」を拾って聞き取る、ということをやっているわけですけれど、ひとが話をする、いわゆる「口話」には、「ことばの意味」と「息の状態」の二種類の情報が含まれているわけです。
そして、息の状態は、身体の状態を反映します。
今、口から出たことばを、どのくらい本人が…あるいは本人の身体が…真剣に思っているのか?これがきちんと一致することを「身口意」と仏教で呼びますが、まあ集注の極意みたいなものになっています。
つまり、大抵の場合は、どこかでズレているわけです。このズレが大きいほどに、ことばは「軽く」なります。
ご自身のことばが、どのくらいずっしりと重みがあるでしょうか?
心にもないことを、ついつい、ことばとして、口から放っていないでしょうか?
本当に、そのことばは、心の底から、納得して発していますか?
自分に嘘を、ついてはいませんか?
ことばを見直すこと。
ことばの基になっている息を見直すこと。
それで開ける道もあるように思っています。