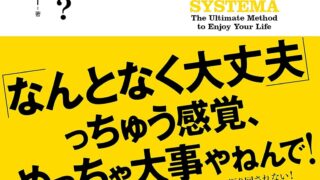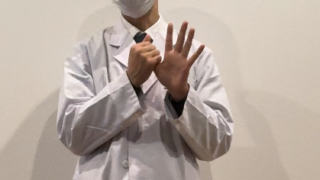せんせいは漢方医ですか?
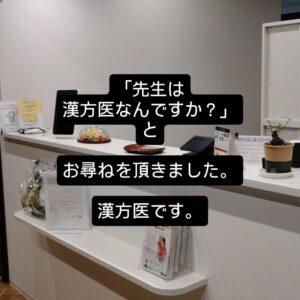
先日、そんなお尋ねをいただきました。
「はい、漢方医です」とお返事したのですけれど、漢方医、って、いったいどんなひとのことを言うのでしょう?
...って改めて考えてみる…という面倒くさいことをやってみました。
まず、大前提として、日本で医業を行うには、医師である必要があります。
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
医師法
とあります。
この医業の範囲がどこからどこまでなのか、というのは古来、議論の対象になっていて、
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
と、厚労省はそのような通知を出したりもしておられます。
まあ、細かい話を言い出すと悩ましいところではあるのですが、漢方医と名乗るためには、やはり医師であることが必要なのかもしれません。
一方で、日本の制度の中で「医師」というのは、西洋医学の教育と訓練を受け、国家試験に合格したもの、ということに決まっています。
わたしも、西洋医学の教育と訓練を受け、国家試験に合格し、また、その後に卒後臨床研修制度というシステムで、卒後研修を修了しています。制度的にいえば、立派(?)に、西洋医学の医師です。
そんなわたしが「漢方医です」と名乗るには、なにが必要なのか?と考え込んでしまったわけです。
こちらの記事では、漢方内科とは…という話をしました。
漢方には、それはそれは歴史がありますから、「漢方とはなにか」という疑問に対する答えも、歴史的にはさまざまな答えがあったでしょうが、にしむらは「気」のことに焦点をあてた形で「漢方とはなにか」に答えました。
このあたりも、漢方について学んでいらっしゃった方によっては議論が分かれる可能性があります。
日本東洋医学会は漢方専門医を認定しています。ここの専門医を取得すると、広告に記載することができるようになります。学会は専門医について、このような医師である、とその様子を記述しています。
漢方専門医とは専門医像
漢方専門医の診察風景を簡単に紹介してみましょう。まずは「望診(ぼうしん)」という診察です。あなたの全身をみて、顔色や姿、立ち居振る舞い、皮膚の状態などをみます。その後「問診(もんしん)」に移り、症状はもちろんのこと、必ずあなたの体質について聞きます。例えば、暑がりか、寒がりか、疲れやすいか、汗をよくかくか、便の状態はどうか、イライラしたり落ち込んだりするかなど、多岐にわたります。その際、声の調子や話し方にも関心を払う「聞診(ぶんしん)」という技術も用います。そして漢方独特の診察をします。まず「舌診(ぜっしん)」で、舌の色や形、苔などをみ、次に「脈診(みゃくしん)」で、両腕の脈をみて、 さらに「腹診(ふくしん)」でお腹を丁寧に診察します。
こうした漢方医学独特の診察を行って、みなさん一人一人の今の状態にどの漢方薬が最も適切かを見極めます。こうして、あらゆる具合の悪さや病気で悩み苦しむ方々に、現代医学とは異なる方法で、症状の改善もしくは治癒を目指す最適な漢方治療を提供します。
わたしも、漢方の専門医を取得していますので、こうした教育訓練をうけてきた、ということになりますし、実際に今の診療でも、ここに書かれた診察風景に近いことをやっています。いろいろ省略したりすることもありますが…。
ただ、これは「漢方専門医」の像です。
漢方医にはまた別の風景があるのかもしれない…なんて考えると、だんだん分からなくなってきたりしませんか?しませんか。そうですか。
ひらたくまとめると、医師の五感をつかって、いらっしゃった方の診察をして、「気」や「血」「水」などを中心とした見立てを行い、漢方薬を処方する…のが、漢方医、かなあ、なんて思います。
ついでに、やっぱり西洋医でもありますので、時々西洋医学的な診察や検査を混ぜることもあります。これが現代日本の漢方医の、ひとつのあり方なのかなあ、と思っています。