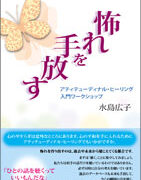どげんかせんといかん

わたし(にしむら)は幼少期から高校生までの期間を、福岡県の郡部で過ごしました。
なので、一応、博多弁を使っていた…のだと思います。今ではみるかげもありませんが。
もう、ずいぶんと前になりましたが、東国原氏が、タレント(そのまんま東氏)から、宮崎県の県知事選挙に出馬され、県知事に当選されました。
最初の所信表明で「どげんかせんといかん」とおっしゃったそうです。
福岡の言葉でも似たような表現がありましたので、大変懐かしく聞いたのでした。
この「(宮崎を)どげんかせんといかん」ですが、2007年の流行語大賞に選ばれたのだそうです。
どげんかせないかん、とか、どげんかせんといかん、というそういう思いは、結構大変です。
県知事としては、なんとかかんとか、県の知名度をあげて、経済がまわってゆくように、ということを考えておられたのではないかと思います。ずいぶんとテレビなどでも宮崎県の物産をアピールされていました。
どげんかせんといかん、という思いで頑張っておられた方は、本当にそれはそれで、大変だったのだろうと思います。
標準語?に無理矢理に書き直すと「どうにかこうにか、なんとかしなければならない」というような言葉になるでしょうか。
クリニックにいらっしゃる方の中は、そのような「なんとかせねばならない」という強い思いに、どこか押し潰されそうになっておられる方もいらっしゃいます。
押し潰される前に、なんとかせねば。それこそ「どげんかせんといかん」わけです。
薬を処方したり、お話を聞いて、整理してみたり、ちょっとした提案をしたり。そのような診療を重ねている中で、ふと、背中の力が抜けてくる、そんなタイミングがあります。
「なんとかせねば」から、「まあ、なんとかなるか」くらいの変化でしょうか。
どげんかせんといかん、という、いわば「背負い込んだものの重さ」を、いったん脇に置いて、なんとかなるか。と多少気楽に観察できるようになるだけで、身体はどれほど楽になることでしょうか。
もちろん、なんともならないことだって、あります。
ところで、とんちで有名な一休さんの遺言を、みなさん、ご存知でしょうか?
一休禅師は、お亡くなりになる前に、「もしもこの先、どうしようもなく困ったときに」とおっしゃって、手紙を遺しておられたのだそうです。
そして、没後しばらくして、お寺が大変な危機を迎えたのだと言います。
お弟子さんの一人が、この手紙のことを思い出して、引っ張り出してきたのだとか。一体なにが書いてあるのだろうか…?
ひょっとすると資産を埋めた場所の地図でしょうか?
あるいは何かの権利書でしょうか?
期待をこめて、手紙をあけた、そこに書いてあったのは3つの言葉だったのだそうです。だいじょうぶ
心配するな
なんとかなるいや、もうちょっとマシな言葉とか無かったのですかねえ?って言いたくなるような、そんな言葉でした。
が、不思議と、お寺の関係者みな、その言葉に、肩の力が抜けて、笑顔になったのだとか。https://diamond.jp/articles/-/281408 から内容をお借りし、にしむらが脚色しました。
どげんかせんといかん、と頑張ることも、時には大事です。それで実績をあげる方もいらっしゃいます。
が、疲れているとき、責任感に押し潰されそうな時には、ちょっと、一歩引いて「だいじょうぶ。しんぱいするな。なんとかなる」ってご自身に言い聞かせるのも、良いのかも知れません。