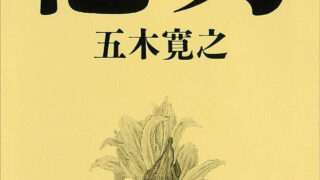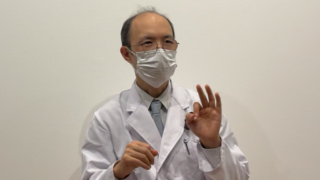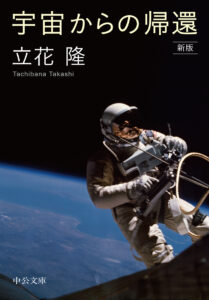ないものねだりをしても仕方ないのだけれど

昔、総合病院の産婦人科で働いていたころ。「産婦人科女医のワークライフバランス」という話題を、上司が聴いてきたことがありました。
曰く、常勤の産婦人科医の仕事と妊娠・出産・育児を両立させるにあたって、必要条件が3つあると説明されたのだ、と。
もうずいぶん前の話なので、いささかあやふやですが、こんな話だったと思います。
「ひとつ、夫の理解と協力」
「ひとつ、実家の親(ほとんどは母)の積極的な協力」
「ひとつ、本人の強い意欲」それら3つが揃わないと、妊娠・出産・育児と、仕事を両立できないのだ…。
そういえば、わたしも常勤の産婦人科医をしている時は、月に10回くらい当直していましたし、早朝の呼び出しも、帰宅が遅くなることもありましたので、家庭のことは本当に妻にまるまる、放りっぱなしになっていた、と言えます。
(最近は「医師の働き方改革」が進みましたので、あの頃のような長時間勤務は認められなくなっている…はずです)
産婦人科女医のかたで、「そこまで夫は理解も協力もしてくれない(あるいは、夫も拘束時間の長い仕事をしている)」とか「実家が遠いなどの事情で手助けが期待できない」とかってことだってあるでしょうし、「そもそも、そこまで無理してキャリアを続けたいとも思わない」という方もいらっしゃるでしょう。
そういう先生方も、臨床に出ておられることで、医療を提供できる範囲は拡がる可能性があるわけです。
そこを「サポートできないので、キャリアを諦めてください」って話にする、っていうのも、ちょっと違うような気がします。
なんてことを考えて、サンタクロースに、「そうじゃなくても仕事と家庭が両立できる環境が欲しい!」ってお願いしてみる?みたいな話をしたことがありました。
最近、SNSを見ていたら「昨今の、核家族による育児は、いわば、駆け落ちしたカップルが子供を育てているような状況だ」という記述をみかけました。
地縁も血縁もないところで、本当に両親だけで子供を育てる…のだけれど、父親はたいていの場合は、外で日銭を稼ぎに行かねばなりません。となると、ものの言えない子供と、母親が密室で二人きり、というような状況が続きます。
それまでに母性のスイッチが入って、子供と一緒に過ごす時間が幸せ、という感性になっていれば、まだ多少は楽なのかもしれませんが、今どき、なかなか母性のスイッチが入らないのも珍しくありません。
そういう状況を考えるほどに、現代社会って、妊娠出産育児と、相性が悪いよなあ…って思います。
制度を設計する人たちが経験していない、というのもあるのでしょうけれど…。
とはいえ、地縁が急に濃くなって、近所のおばさま方が、みんな、子供を勝手に抱っこして、あるいは子育てに手出し・口出ししてくる、というのも、現在の状況から考えるなら、本当に恐怖でしかなかったりします。
なかなか難しいことではあります。
どうか、良い環境で、伸びやかに子育てができる、そんな社会になってほしいと思うのですが…。
なんとも無いものねだりになってしまいそうで、本当に難しいことだなあ、と思います。