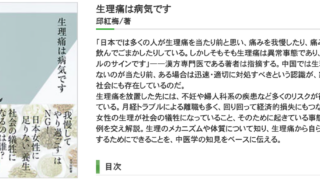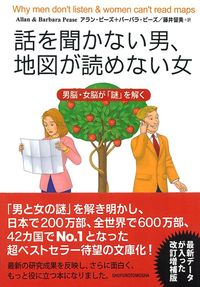なぜ祈りは届かないのか
最近、いろいろとご縁が重なって、仏教に関する本をいくつか続けて読んでいます。仏教の説明されている本にも、本当にいろいろあるんですよねえ…。
仏教の中で、特に日本で有名なお経に「般若心経」というのがあります。このお経、きっと一番短いものなのだそうです。漢字でおよそ260文字くらいなのだそうです。
「短い割に難解」なんていう言い方もされていたりします。短い割に、なのか、短い故に、なのか、あたりもいろいろと議論がありそうですけれど。
いわゆる「色即是空(しきそくぜくう)、空即是色(くうそくぜしき)」の出てくるお経です。
そもそも「空(くう)」って何だよ、って話になるわけです。この般若心経の中心的なテーマが「空(くう)」らしいので、その話ばっかりになるのは仕方ないのかもしれません。
そして、その「空(くう)」っていうのがとっても難しい。
ずいぶんと前になりますが、どこかの政治家の方か、あるいは大臣だったでしょうか。英語の通訳を介した対談の中で、この「色即是空、空即是色」という言葉を引用されたのだそうです。で、通訳の方がお困りになられたのだとか。
そこをこの政治家のセンセイ、「カラー(色)イズ(即)スカイ(空)、スカイ(空)イズ(即)カラー(色)」ってご自身で自信満々に英語を披露されたとかっていう話を読んだことがあります。
それで良いのか?(いいやよくない)とは思いますが、いろいろな所にでてきます。なので、わりと人口に膾炙したお経になっています。
西遊記の物語で、三蔵法師が、孫悟空の頭に金色の輪っかをつけます。「緊箍児(きんこじ)」と呼ばれますが、これは、三蔵法師が呪文を唱えると、孫悟空の頭を締め付ける…という、そういう不思議な働きをします。この時に三蔵法師が唱えるのが「般若心経」になっている…という話がありました。実際には、この般若心経を西方から頂いてきて、玄奘三蔵が翻訳をするので、行きの道行きで唱えているのが般若心経、という描写はいろいろと無理があるのですが…。ドラマの演出としては、お経といえば般若心経!くらいに持ち出されるのが、このお経だった、ということのようです。
絵心経、なんていうのもあるんですよねえ。

アマゾンの出品者さんから画像をお借りしました。
この絵心経、もともと、文字が読めない方が般若心経を覚えるために作られたもの、なのだそうです。
これもまた面白い話がいくつかあって、「しき」って書いてあるところのアイテム、現代の標準語では「鋤(すき)」なのだそうです。「つ」って書いてあるところのアイテムは「乳(ち)」…羽織の紐をつける部分…なんだそうで。そういう音韻の変化から、このオリジナルは東北地方の、特に岩手県あたりと想定される…だったかしら。なんだか、そういう研究も進んでいるようです。
ええっと。そんな話をいろいろと考えつつ、般若心経の解説本(これも本当にたくさんあります。古くは弘法大師がお書きになったという『般若心経秘鍵』なども、いわば、こうした解説の1つと言えるでしょうし)の1つを読んでいたのでした。
『こだわりを捨てる 般若心経』ひろさちや、中公文庫
中公文庫では検索にひっかからなくなっていたので、ひょっとすると廃版なのかもしれません。
この本のいちばん最後のあたりに、明恵上人という方の言葉が紹介されていました。
明恵上人の言葉に至るまでの部分を、いちぶ引用してご紹介します。
じつは、わたし(著者であるひろさちや氏:にしむら註記)は子供のころ、祖母からこう教わりました。
「ほとけさまを拝むとき、絶対にお願いごとをするな!“ほとけさま、ありがとうございます”と拝め!」
と。
なぜ、願いごとをしてはいけないのか、祖母に理由を尋ねても、「知らん」と言います。(中略)
祖母の教えをわたしなりの言葉にすれば、
——請求書の祈りをするな!領収証の祈りをせよ!——
となります。ほとけさまに「ああしてください」「こうしてください」と請求書を突き付けるような祈りは、本当の仏教の祈りではありません。「ほとけさま、ありがとうございました」と祈る、領収証の祈りが本当の仏教の祈りです。なぜか?そのことを、鎌倉時代の華厳宗の学僧の明恵(1173〜1232)は次のように言っています。『栂尾明恵上人伝記』(巻下)から、引用します。
(中略)
《又仏は、方々の御事をば、一子の如く思食し候に、叶へても進せられ候はぬは、何にも様こそ候らめ。譬へば、をさなき者毒を知らで食したがり候を、親の奪ひ取り候をば、甚だ恨みて泣き候が如し。一旦は本意なき様に候へども、終にはよかるべきはからひ也。されば仏をも神をも御恨み有るまじく候》
ええと、最後の文章が明恵上人が書き残されたお言葉です。
「…また、仏は、みなさんのことを、それぞれご自分(仏様自身)の子供であるかのようにお考えでいらっしゃいますから、(みなさんが求めているにもかかわらず)叶えられない、ということがあるならば、それは、叶えてはならないことなのでございましょう。たとえば、小さな子供が、毒が入っていることを知らずに食べたがっているものがあったとして、親がそれを奪い取ったなら、(その子供は親を)ひどく恨んで泣くことでしょうが、それに似たものがあります。(願いが叶わないということが)一見は、とても残念なことのようではございますが、最終的にはそれでよかった、となるようなお計らいがあるのです。ですから、神や仏をお恨みなさいませんように」
祈りが届かない、と嘆くよりも前に、自分自身の祈り方を点検することが大事、なのかもしれません。
そして、ひろさちやさんのお書きになった、「請求書の祈りをするな!」という指摘には、我が身を振り返って、思うところがあります。
ひとの欲望には限りがない、ということを揶揄した古い戯れ歌がありました。
いつも三月花の頃
お前十九でわしゃ二十歳
死なぬ子三人親孝行
使って減らぬ金百両
死んでも命がありますように
そのようなひとの欲を「祈り」というような体裁に仕立てたからとて、それに応えてくれるわけもありません。
こういう事情をもって、祈りが「届いていない」と、にんげんが考えるのかもしれません。
神や仏のはからいは、そうした思いも含めたうえで、もっと大きな視野でわたしたちを見守っているのだ…ということになるでしょうか。
キリスト教の中にも「かつて、キリストは奇跡を数多く遺したが、近年、そのような奇跡が少ないのは何故か?」ということについて議論があるようです。
わたしが聞いた1つの答えは「人間もだいぶ成熟してきたから、奇跡に頼らなくても良いようになってきたので」という話でした。
成熟してきたから…の部分は、いろいろと考えることもありますが、安易な奇跡に依存することなく、自らの足で立つ、ということを考えてゆかねばならない、というのは間違いないのだろうと思います。
その上で、そうした「自らの足で立つ」という心構えさえも、神や仏は見守っていてくださるのだ、というあたりが信仰になるのかもしれません。
ちょっと抹香臭い話になってしまいましたが。