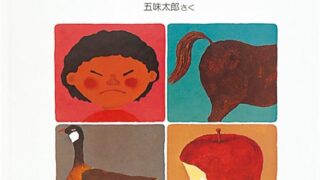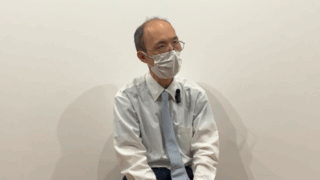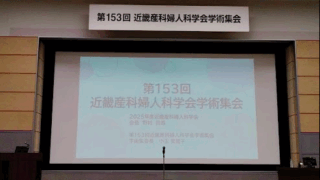ものものしい

少し前の話になりますが、先日、地域の防災訓練がありました。
防災用のヘルメットとか、集合場所にたてる幟とか、そういう準備がけっこうあるのだそうです。
「ずいぶんとものものしいいでたちだねえ…」とそんな言葉が口から出たのでした。
ものものしい。
漢字で書くなら「物物しい」ということになるようです。
ものものし・い 【物物しい】
(形)《文シク ものもの・し》
① 人を威圧するような感じである。いかめしい。「警官隊は―・い服装で出動した」
② 厳重である。きびしい。「―・い警戒態勢」
③ おおげさである。「―・く包帯をする」
ところで、どうして「もの」「もの」しい、という言葉がそんな意味を持つようになったのでしょうか?
賑やかな感じを言うのに「にぎにぎしい」と言ったりします。
華やかな感じには、「華々しい」なんて言葉があります。
そのほか「仰々しい」とか、「騒々しい」とか、こういう言葉をふたつ重ねて「しい」をつける表現は、ずいぶんと日本語の中にはあるようです。
まあ、似たような表現があるわけですから、それに倣った、ということなのかもしれません。
賑やか、とか華やかとか、そのままでも意味が通じる言葉が多いのですが…。「もの」って一体なんだろうかしら?と思ったのでした。
ふと、古語辞典を手に取ってみたところ。
「ものものし」がありました。なるほど。古語扱いされている形容詞なのだそうです。
ここはもうひとつ、「もの」を調べてみたら、雰囲気が分かるのかもしれません。
もの 【物】
名詞
①物。衣服・飲食物・楽器など形のある存在。▽前後の関係からそれとわかるので明示せずにいう。
源氏物語 須磨「ものの色、し給(たま)へる様など、いと清らなり」[訳] 衣服の色、なさっているようすなど、大変すばらしい。②物事。もの。芸能・音楽・行事など形のない存在。▽前後の関係からそれとわかる事柄を明示せずにいう。
源氏物語 絵合「道々に、ものの師あり」[訳] 物事のそれぞれの分野に、物事の(=その道の)師匠がいる。③もの。こと。▽思ったり話したりすることの内容。
竹取物語 かぐや姫の昇天「常よりももの思ひたるさまなり」[訳] いつもよりもものを思っているようすである。④人。者。
竹取物語 かぐや姫の生ひ立ち「竹取の翁(おきな)といふものありけり」[訳] 竹取の翁という人がいたということだ。◇「者」とも書く。⑤ある所。
枕草子 僧都の御乳母のままなど「あからさまにものにまかりたりしほどに」[訳] ちょっとある所に出かけていた間に。⑥怨霊(おんりよう)。鬼神。物の怪(け)。超自然的な恐ろしい存在。
竹取物語 かぐや姫の昇天「ものにおそはるるやうにて、あひ戦はむ心もなかりけり」[訳] 何か恐ろしいものに脅かされるような状態で、戦い合おうという気持ちもなくなったのであった。
もの- 【物】
接頭語
〔形容詞・形容動詞などに付いて〕なんとなく…。▽漠然とした様態を表す語を作る。「もの恐ろし」「ものめづらし」「ものはかなし」「もの清げ」「ものまめやか」https://kobun.weblio.jp/content/%E3%82%82%E3%81%AE#goog_rewarded
なるほど。物の怪、なんかも「もの」なんですねえ。
漠然とした、という表現を作る接頭語というのもありました。
そういえば、徒然草の冒頭に「あやしうこそものぐるほしけれ」という表現がありましたっけ。あやしい+もの+くるおしい、という表現ですねえ
ものものしは、この漠然とした「もの」と「ものし」の組み合わせ…?なんてことはあまり無くて、たぶん「形がしっかりしている」みたいな意味合いだったり、あるいは「物の怪みたいにおどろおどろしい」…もうひとつ畳語+しいの単語が飛び出てきました…とか、なのかもしれません。
コトとの対比で「モノ」なのだ、という解説も見かけました。
うん?と思って調べたところ、「ものものしい」だけじゃなくて、「ことごとしい」という表現もあるのだとか。これもまた古語なのだとか。
ことごとし・い 【事事しい】
(形)《文シク ことごと・し》〔古くは「ことことし」と清音〕
大げさだ。ものものしい。「―・く言うほどのことでもない」
意味は?なぜか「ものものしい」って書いてありますが…それぞれの意味、微妙に違っていたのではないか、と勝手に想像しています。