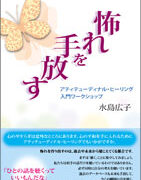わすれることのよしあし

認知症、と呼ばれる前の時代には、「痴呆症」とか「痴呆」とかいう言葉が使われていたのでした。そんな状態や、言葉がひとに知られるようになったのは、有吉佐和子の『恍惚の人』あたりがきっかけだったのだとか。
わたしの母の祖母(曾祖母)は、そんな「恍惚の人」が著されるよりもずっと以前に、手強い認知症だったのだ…と時々、その思い出話を聞きました。
あまりにもひどい痴呆のために、施設入所することになり…とはいえ、勘がそうとう良い人であったらしく、その老人施設に連れて行くミッションを申しつけられた、当時独身、若手の母が、「このひと痴呆なんです」と言っても、先方の職員さんが納得されず、病状の説明にずいぶんと困ったのだとか。
老人施設の受け入れ面談?で、ほぼ完璧な受け答えをした、その曾祖母は、いっけん、問題が無いような振る舞いだったのだそうです。
ここで、施設長の方が一計を案じて、孫(母)をいちど引き離したのだと。
施設をぐるっと回って見学してきてから、「おばあちゃん、この子、知ってる?」と声をかけたら「どこのお嬢さまか知りませんが…」と他人様に対する返事が出てきたのだ、ということで、ここで記憶の強い障害があることが認識されたのだということでした。
そこから血統書付きの認知症の家系…というわけではありませんが、その娘である、わたしの祖母も、そして、母のいちばんうえの姉である、伯母も、けっこうきつい認知症を経て、いまは鬼籍にあります。
あれは、祖父の葬儀の時だったでしょうか。コタツに入って、祖母とふたり。
「寒くないかい?」
「うん。寒くないよ。ばあちゃんだいじょうぶか?」
「こっちも大丈夫だよ」
の会話を、30秒か1分ごとに繰り返したのでした。
時々、バリエーションを入れようか…と思いなやんだのですが、バリエーションの意味もなかったようです。
認知症の方が、わすれることについて、どのように緊張されているのか、彼らの頭がどのくらいいっぱいになっておられるのか、は、分かりません。当時はそのような見方をすることすら知らなかった、ただの子供でしたので…。
ですが、何もかもを覚えておかねばならない、という緊張を手放すことは、結構大事なことであるのかもしれません。
忘れることによって、前に進むことができることもある。
思いを、手放すことで、自由になれることもある。
それを「忘れる」ためには、たぶん、どこかで「自分を許す」ことが必要なのだろうと、そんなことを考えます。
そして、自分を許して、上手に忘れることが、次の人生の扉を開く、そんなこともあるのだろう、と思います。