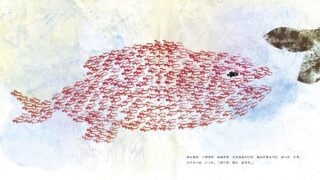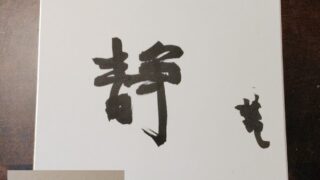アイメッセージ

iPhoneとか、iPadとか、iPS細胞とか。いろいろアップル関連で、そういう名称が増えました。(iPS細胞はアップルとは直接関係なかったですねえ…)iMessageというサービスもアップルで提供されていますが、今日の話はそちらではありません…。
心理学用語で「わたし」を主語にしたメッセージ法があります。それを「アイメッセージ」と呼びます。
この表現方法は、わたしの感情を相手に伝える、という形で用いられることが多くなります。
具体的な例をあげてくださっている方がありました。
「(わたしは)連絡がなくて寂しい」
「(わたしは)そう言われると悲しい」
「(わたしは)少しイライラしている」
「(わたしは)その場所に行くのが心配だ」
https://www.direct-commu.com/chie/mental/i-message1/
このような文章の形で、わたしを主語にして、自分自身の感情を述べるのが中心になります。ここで重要なのは、相手の行動を「こうすべきだ」と押しつけないこと。
自分の感情を相手に伝え、判断は相手に任せること
というのが、特徴です。
判断を相手に委ねる形の文章になっている、というのが重要なポイントなのかもしれません。
もちろん、アイメッセージの形をとっているのであれば、全ての表現やメッセージに問題が無い、というわけでもありません。アイメッセージでさえ、ひとを操作するために用いる方もいらっしゃいます。アドラー心理学では、そもそも感情というのは「使う」道具ですから「わたしが不快である」という表明をすること自体、相手の行動をなんらかの形で変更させたい、という意思表明になっているわけです。
なので、このアイメッセージも、主語を「わたし」にして、そのまま主張したら、自分の希望がそのままで通じる、というわけではありません。
たとえば「(公園で、戦車のラジコンカーを使っている子どもがいたときに)そのオモチャの音がうるさくて、(わたしたちが)遊ぶのに邪魔だと感じている」ということを表明したとしても、できるのは「お願いすること」までです。強制や強要はできません。
(このラジコンカーのたとえ話は、ミヒャエル・エンデの児童文学作品『モモ』の中に出てくるエピソードです。その時の登場したおとなたちも「頼むことしかできないのだよ」と言っていたはずです)
とはいえ、課題の分離をする上で、今の言葉の「主語は何か?」ということをきちっと考える、ということはとても重要なポイントがあります。
もともと、日本語はわりあい、主語が曖昧なままでも会話が成立しうる文章構造をとっています。主語を明確にする、英語などに比べると、どうしても、主張している物事の「主語が何か?」という点について、注意が必要なのでしょう。
そういえば、学生運動の時代に「われわれはぁ!」と主張をしはじめた時に、「あ、その『われわれ』の中から、僕の分だけひいておいてくれ給え」と茶々を入れた方があった、という話も聞いたことがあります。
おそらく、学生運動も後半に入って、一体感が喪失されてきた時期のことなのだろうと思いますが、われわれ、という主語にまとめられることに違和感とか、嫌悪感が出てきた、ということなのかもしれません。
そういう点においても、あまり大きな主語を使わずに「わたしは」という形でものを語るのが大事なわけですが…ついつい「わたしは」と言うところを、「わたしたちは」と言いがちです。主語が大きくなると、なんだか、自分一人の責任が緩和されるから、なのでしょうか。
わたしの高校時代の恩師は「人間は…とかって言うな。わたしは、って言え」って、繰り返し指摘してくださいました。どうしても大きな主語にしがちな、特に思春期の話を、そうやって、明確に指摘してくださったことは、大事なことだったのだなあ、と今になって思います。